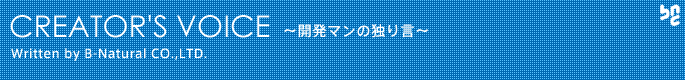大腸の検査
ああ怖かった・・・の大腸検査を受けてきました。
実際には苦痛もなく、怖がる必要も無い検査ですし、
ましてや、検査の結果は「心配なし」だったのですが・・。
行くまでは、かなり長い時間、気をもみました・・・。
この話の端緒は、思い起こせば2001年くらいの人間ドックで腫瘍マーカーのCEA?とか言う・・・の数値が高い・・・と出たのがきっかけでした。
大腸がんの場合などに数値が高くなるマーカーで、この検査自体は血液検査なのですが、なんでも愛煙家の場合は癌でなくても高い数字が出ることも「まま」ある・・・ということなのですが・・・それでも念のための大腸の精密検査・・・内視鏡の検査を薦められていました。
それから6年・・・・。
まあ、気が重かったり、問題の便の潜血も、ある時は在ったり・ある時は無かったりだったりで、自分をつい騙してきたのですが、昨年の人間ドックでは、便の潜血と腫瘍マーカーがセットで出てしまいまして・・・またしても検査を薦められ、とうとう人間ドックの担当の医師に紹介状を書かれてしまいました・・・。
で、気が重いのは変わらないのですが、とうとう意を決して評判の良さそうな検査専門のクリニックをネットで調べて、そこに2月下旬に予約を入れて、最短で予約が取れたのが、やっと4月10日・・・で検査に行ったのです。
大腸の検査はかなり苦痛を伴うと言うウワサでしたが、このクリニックは評判どおりで、なんら苦痛は無く、検査もあっという間ですし、内視鏡の機材の消毒や、使い捨ての処置具の導入など大変先進的で納得のいく内容でした。
やはり、プロといいますか、専門家・・・と言うのは凄いですね・・・。
検査の内容をご説明しますと、それは前日の食事の段階からスタートでした・・・。
前日は3食、食べてよいのですが、繊維抜きをします。
普段の逆で、体に良いとされる繊維質のものを食べないようにするのです。
単純には野菜・果物・海草類・のり・きのこ・・・などを食べてはいけないのです。
検査のときに大腸に繊維が残っていて邪魔になるそうです・・・。
ですから、食べるのは、ご飯、うどん、そば、肉、魚で3食食べて、寝る前に下剤を飲んで寝ます・・・。
小生は朝がフレンチトースト、昼がのり抜きのマグロ丼、夜は肉うどんでした。
さらに検査当日は朝から200ccの水で溶かした下剤を飲むことから始まり、検査の4時間前から2時間かけて1800ccの水溶きの下剤を飲みます。
もうお腹は空っぽで、下剤と言うより、水で大腸を洗い流している感じでした。
消化液などの関係でしょうか?薄く黄色く色がついた、澄んだきれいな水しか出てこない状態になると前処理が完了です。
この、腸をきれいに洗う工程は、嫌だといえば嫌ですが、小生の場合は途中から結構楽しんでしまいました。下剤を飲んでトイレに通うのは嫌なんですが、きれいに澄んだ状態にするという目標がありますと・・・つい綺麗にしようと頑張って楽しんでしまいました。
「うーん、これなら完璧だ・・・などと」
で実際の検査ですが、クリニックで使い捨ての検査着に着替えて横になり、鎮静剤を静脈から注射して、内視鏡を入れ、まず盲腸のところまでカメラを進めてしまって、そこからカメラを戻しながらジックリ見てくる感じでした。
患者の前には大型の40インチくらいの液晶の高画質のモニターがあり、自分の大腸の中を見ながら検査を受けるのです。
それは大変不思議な感じで、意外に腸の中がきれいなことに驚きながら見ていました。
また腸の中は感触が無いらしく、今どこに内視鏡の先端があるか?などの感覚がありませんでした。
小生の場合は4mmほどのポリープが一個あったので、それをその場で切除して(焼ききるようです)もらい終了でした。
先生の話では50歳代で何も無いケースはほとんど無く、たいていはポリープの一個や二個があるのが普通だそうです。
問題は数やポリープの状態だそうです・・・。
次回の検査は、3年から4年後で良いでしょう・・・と言われ胸のツカエが降りました・・・。
結果の如何によっては、感慨はもっと別のものにもなったとは思いますが、それでも、どっち道検査をした方が安心・確実であるならば、もっと早く受けるべきでした。
(名医のクリニックでの検査でしたら?)そんなに怖がる内容や痛いことではありませんでしたから・・・。
新アンプなど導入しました
先日来、自作スピーカーの話が続きましたが、アンプなどの新兵器を導入しましたので、そのご報告でございます。
小生、自作は大工仕事で済むスピーカー工作と、真空管アンプのエレキットの製作くらいまでで、電子回路はお手上げなのです・・・。
ですので、基本的にアンプなどは購入しています。
最近あるサイトの主催の方の主張に妙に納得しておりまして、かなり勉強しました。
それは「プロケーブル」さんのサイトです。
曰く、高級な民生のアンプはボロイ・・・。
高級な接続コード類は音をグツグツにしてしまう・・・。とか・・。
メッキの端子の電源プラグは音が駄目になる・・・。とか・・。
小生が読んでいて大変納得したのは、世界のスタジオ・録音現場で使っているケーブル類と同じケーブルをCDプレーヤーからアンプへの接続や、MDデッキなどの接続に使うのが、音の再現と言う観点では正しい・・・という考えでした。
オーディオの再生では、スタジオの逆に信号が流れるだけ・・・接続ケーブルが録音現場と同じだと再現できる・・・。・・なるほどです。
エンジニアの方がスタジオで音決めして、それをパッケージにしたのがCD・・・。
CDの再生はその逆の行為・・・。
アメリカのスタジオは多くがベルデンの8412というケーブルを使っているそうです。
日本の録音スタジオでは、カナレかモガミ電線・・・だそうです。
このケーブル類、オーディオ用としては安価です。
小生はベルデンの8412と言うケーブルで、RCAプラグは世界標準と言われるプラグ(スイスのノイトリック社のもの)で作ったケーブルを購入して導入しました。
このケーブルは安価で、2本一組1mで確か3,000円くらいでしたか・・・。
このケーブルが良い音かどうかは、残念ながら小生の耳には分かりませんでしたが、これがスタジオの標準なのだ・・という安心感があります。
それと、しいて言うと、高音域の癖が取れ、低音が豊かになったような感じはありました。
さらにスピーカー・ケーブルは、アメリカの古いウエスタンエレクトリック社の16GAという太さのものを、すでにプロケーブルさんから購入し、昨年の夏から使っていました・・・。
これも1mで1000円くらいで、スッキリとして癖の無い、良い音だと思います。
スピーカーケーブルについては、その良さが分かりやすかったように記憶しています。
音(の広がり)が晴れ晴れした感覚・・があったのを覚えております。
スピーカーの自作写真にも写っている内部配線の赤い電線がウエスタンエレクトリックの16GAの電線です・・・。
また、このサイトではアンプも・・・レコーディングスタジオで使う、プロ用のラックマウントの1Uの物を推薦されています。
アメリカのクラウン社のアンプです。 クラウンD-45(日本名ではアムクロンD-45)。
片チャンネル25W、ステレオで50W。
お値段6万6千円少々・・・これが最強のアンプと紹介されています。
トランス電源のアンプですので、トランスのうなり・・・「ウーンという雑音」がありますが、音は確かに良いと思いました。
リスニングポジションから離れたところにアンプを設置したら、この「ウーン」は気にならないと思いますし・・・。
音の感じは、ナチュラルでフラットな音・・・と言うのはこういうことか・・と思いました。
余計な響きなど無く正確に再現する・・・と言う音と感じました。
思えばこういう音を求めて、今まで真空管アンプやら色々と行脚してきたように思いますし・・・。微妙な心理状態です。
結果としては、真空管アンプはこれと聞き比べますと、ある意味で対極でした。
真空管独特の響きが付加されていると思いました。
しかし、真空管の響きは、これはこれで倍音の多いチェロなどを聞くと大変捨てがたい魅力があります。
真空管アンプの良さは「響き」「つや」だと気付かせてくれたものも、対極にあるクラウンのアンプと言う言い方も出来ますね・・・。
クラウンのアンプの音は真っ直ぐに音楽を確認できる感覚で、これはプロのモニターの世界なのだろうと思いました。
ケーブルとアンプに関しては、小生がもともと高級なケーブルや超高級アンプや超高級電源ケーブルなどと無縁で、拙宅では、せいぜい自分で半田付けした秋葉原で買った古川電線や日立電線のケーブルを使用・・・でしたので、激変はありませんでした。
(ある意味で小生の自宅のシステムは貧乏システムなので健全だった??のかもしれません・・・だって電源コードに数万円などというのは小生の感覚では・・・あり得ないアンバランスさ・・なのです)
ちなみに、プロケーブルさんではスピーカーも、PAまたはSRでしょうか・・・のプロ用を推薦なさっています。JBLのSR用のものは38cmウーハーで1台が29800円・・・。
これが「良い」そうで・・・今までの感覚からすると絶句する値段です・・・。
でも、この方の耳は確かだと思いますので・・・。
いずれ導入したいスピーカーです・・・。
ちょっと目からウロコ・・・の体験でした。
さらにもうひとつの新兵器は電源トランスです。
これも買いました。
単層200ボルト(専用のアースつき)・・・3芯の単層200ボルトとも言うそうです・・・。
の電源工事をしてもらって、ダウントランスを入れました。
3芯のアースつきの200ボルトは、バランス伝送で電源を供給していて、ノイズを食っていない綺麗な電源・・・とのことで、これから電圧を落として100ボルトのオーディオ機器に電源を供給します。
トランスの前後に12個のコンセントがあるのです。
オーディオ用のダウントランスというのでしょうか・・プロケーブルさんのオリジナル商品だと思います・・。
CDやMDやレコードプレーヤーなど、みんなこのトランスから供給しました。
このトランスの導入も、小生の自宅では劇的・・・ではないものの、CDの音はスッキリとし、静寂になったと思います。(このトランスもトランスですから、少々うなりますが、ボリュームを上げたらマスクされます・・・)
アンプもトランスも全体的に、拙宅では地味目な効果ですが、すべてプラスの方向に作用してくれています。
もともと、真空管アンプ、フルレンジのスピーカー、ケーブルにはお金をかけない・・・と言う拙宅の音は、意図しておりませんでしたが、運良く「健全なオーディオ」だったのかもしれません・・・。
色々高級ケーブルなどを導入して悩んでいる方の場合には、正常化が効果的で、激変が期待できるかもしれませんが、もともと貧乏オーディオの小生でも、かなり満足いたしましたので・・・。
ファミリーフェイス
「ファミリーフェイスにちょっと意見が・・」
自動車のファミリーフェイスと言うのに・・・にちょっと考察を・・・。
これは生産する車種が少ない、「ブランド名」がそのまま「車名」になって行くような会社の『特例的な話・・・』、ではないか?と思いました・・・。
唐突ですが・・・。
たとえばドイツのBBBBBとか、MMMMMとか・・・は一族の同じ顔・・で良いと思いますが。
社名の跡に「車種名」が来るような会社では、ファミリーフェイスの実現は事実上、無理じゃないか??と思いましたんです。
この話、ある会社の車で、車種・車名が違うのに似たデザインとか、似た顔を採用していることに対して、すごく違和感があったので、なぜ自分は違和感を感じるのだろうか?って自問して考えた事からなのです。
社名が車種・ブランド名で、それが統一的な品質感や理念で作られて、売られていくなら、同じ顔、同じアイデンティティー・マークなどに拘っても良いのかな・・と思います。
だって、その会社では、お客様にお届けしたい車の理念・理想が車種が違っても同じだから・・・。
でも、割り切った安いものや、大衆的なもの、高性能なプレミアムなものなど・・・コンセプトから相当異なるものが混在する量産メーカーの場合は、「ファミリーフェイス」はお互いのアイデンティティーの殺し合いになり、『有り得ない・・』と思ったのです。
チープと、スタンダードと、高性能と、プレミアムと、贅沢と、広さ、乗り心地・・・が同じ顔でしょうか?
すでに商品の性格が「ファミリー」ではないですよね・・・。
だから、こういうメーカーのファミリーフェイス・・・デザイナーさんのエゴかなぁと・・・これは勘違いだぞーと思ったのです・・・。
単純な話、ユーザーの気持ちでも・・・、同じような顔をした車種が片方は500万円で、片方がそっくりで170万円・・これだと500万円を買うときに腹が立ちます・・・よね。
排気量が、でかいのと小さいので、どちらもそれぞれのクラスでは非常に高価でプレミアムな存在なら・・・まだわかりますが、片方は量販のクラスのど真ん中で、真っ向価格競争していると・・・同じ顔の高級車は、いい面の皮・・・。
1800ccの大衆車と同じ顔の4000ccオーバーのV8エンジン高級車はつらいでしょうね。
『性質・理念の違う車に、同じ顔や同じアイデンティティーは有り得ない』・・と思います。
それから、先日言っておりました上を向いた切れ長のヘッドライト・・・。
メーカーさんによっては、やっていませんでしたね・・・。
北欧のボボボボとか・・・。
英国のローローローとか・・・。
この手のライトをあまりやっていないようで・・・見識??を・・・感じてしまいます。
小生的には、うれしいのです。
逆にフランス車とかは、目いっぱいヘッドライトのガラスの造詣でモダンに遊んでるように思います。エスプリ?でしょうか・・・。
でも、やっぱりコンサバな小生には、「あだ花」に感じます。
だってヘッドライトは上を照らさず、前を照らすものだから・・・。・・まだ言ってます・・・。
大変ごめんなさい・・・でございました。
これに関連してちょっと・・・悪っぽい・・・とか言う顔も無理があると思っています。
珍しいがゆえに新鮮味があり、一時期は良いですが・・・。
小生は嫌ですぅ。
端整とか、品とか、バランスとか、美しいとか・・そういう単語のほうがピンときます。
少なくても「悪」よりは・・・。
車は運転者によっては凶器になりかねない・・・ものですから・・・。
それから、クロスオーバーカー・・・出ましたね。
四角い車・・・。ホンダさんから・・・。
写真ではサイドビューなどアメリカのHHMMのミニチュアみたいで、これはこれで良いと思いました。
まだ実物見ていませんが、小さなサードシートを畳んだら荷物も積めそうで・・・いいです。
これで日本の車もデイ・キャンプやバーベキュー・オンリーから、やっと脱却でしょうか?
泊まれるキャンプの車でしょうか?
それから、最近の自動車雑誌で見ましたが、好きな形のXTRTRTRが、かなりキープコンセプトで行きそうで、本当に良かったですね・・・。
変に宇宙的だったり、獰猛だったり、生物的だったりと、丸く改悪されずに済みそうですね。
(4輪駆動なのにスティングレイルックのような見にくいウインドウ処理を採用して、対向車とのすれ違いで運転席側を崖側にして見切るような林道を本当に走らせる気・・・なのでしょうか・・・。そういう4輪駆動の使い方は考えてらっしゃらないかも知れませんが・・・。)
四角いままの、この車種で、ラージ・サイズは(待っていても)、出ませんですかね・・・。
欲しいんですが・・・。
アウトドアに荷物だらけで行って遊ぶ人が、こういう車のデザインを担当してほしいですー。
できれば、この手の車種のデザイナーさんは、すくなくても「ゴルフをしない人」が小生のイメージなのですが・・・。
ところで、このクロスオーバーというカテゴリーの名前・・・非常に嫌いです。前にも言いましたが、嫌なカテゴリー名称です。
こう言う車が、男性たちに必要な、アクティブな車であって、クロスオーバー??なんて業界のカテゴリーの話は、知りたくも「ない」のでございます・・・・。
ワンボックスのDDDDDが出ましたですね。
4輪駆動の性能で、昔から憧れ、注目していたワンボックス。
しかし、発売までには相当、フロントの改悪??がありましたが・・。
サイドから見て、Aピラーとボンネットのラインがハサミのようにクロスする造形なんですが・・・。これは某、売れ筋の軽自動車が以前からやっている「処理」だと思います。
だから、ちょっと、がっかりしました。
DDDDDは、弄らずに、ショーモデルのような無骨なまま・・・で出すべき・・・だったんじゃないでしょうか。
小生は個人的にですが・・・かなり、そう思いました。
でも、そういうことを言っても、それはそれで十分に魅力的な他社にない車・・・なのですが・・・ど素人・老年の小生には残念なフロント変更・・に映りました・・。
それから、デザインの素人の勝手な意見ですが、高性能な車の猛禽類化デザインはやめていただく方が心地よい・・・と思っています。
高性能車は速いし、後ろにピタッと着かれるだけでも、すごく嫌で、非常に高圧的に感じる存在ですから、姿くらいは優しくあるべき・・・と思います・・・。
睨み付ける顔や、獰猛な感じ、はもう沢山に思います。
小生は感覚的にも獰猛系はもう流行らない・・・と感じています。
ちょっと古い感じ?・・もするのです。
いまさら攻撃的なんて・・・。
とでも言うのでしょうか、ECOの時代ですから、高速・高性能車は時代を錯誤しているように感じます。
ドイツのBBBBBなどのデザインはジックリ見ると、かなり怖いし・・・。
今後、お客さんの皆さんの感覚は、どっちに行きますでしょうか・・・。
小生とは逆に獰猛・猛禽類が大流行になるのでしょうか・・・。
この世相においても・・・。
小生、なんの自信があるわけでもないのですが・・・。
四方山話で大変失礼いたしました・・・。
スピーカーの自作 しょの7
「スピーカーの自作 しょの7」
07年2月のスピーカーのラインアップです・・・。
『しょの7』は図面だけのご説明です。
ご興味ない方・・・本当に申し訳ございません・・・。この回で一応、当面のお伝えしたいネタ?は終了ですので・・。ご辛抱をお願いいたします・・・。
今までは、作ったスピーカーの話をしてまいりました。
実際は、この他にも代行製作的に、友人に頼まれて作っただけ・・のモノもございます。
また、設計はしたのですが、場所の問題や、お金の事など、結局設計だけで終わっている図面も結構、多数ございます。
そこで、今回はその図面だけをご紹介いたします。
たいしたお役にも立たないことと思いますが、ご参考になれば幸いでございます。
また、一部に長岡先生の設計を土台にさせて頂きながら、意図があって「改」として、設計を変更をしている物もございます。
ご了承いただければと思います。
(1)D-102 改スーパー4
長岡先生のブックシェルフ型バックロードは小生、とても好きです。で、色々作りましたが、まだやり残しがございます。
10cmの強力型ユニット、FE108ESⅡ用のブックシェルフをまだ作っておりませんのです。
それの図面がD-102の改スーパー4です。(また勝手な命名でごめんなさい)
この「改」は、実は図面段階でだんだんに4種、検討して修正してきておりまして、現在は4つ目の図面なのです。で、スーパー4(すうぱあよん)と言っております。 オリジナルのD-102との比較では、音道のスロート部のはじめから、悩んだ結果の形になっております。全体のサイズも一回り大きくなり、ブックシェルフとしては、相当大型になってしまいました。
ホーンの開口を正方形以上に確保して、後は空気室容量への配慮とスロート周辺の板材の使い方、ホーンの取り回し方、音道の補強材の入れ方・・・などに小生なりの工夫がチョットだけあります。
これは、ブックシェルフを色々作った反省を込めていますので、きっと作れば結果は良いだろうと思っています。
小生、口径10cmのバックロードは現在持っておりません。スーパースワンを手放していますので、いつかは作りたいスピーカーなのですが、CW形で行くか、ブックシェルフで行くか、トールボーイ前面開口のスワンタイプで行くか・・・大変悩んでおり、それを楽しんでいます。
・D-102 改スーパー4 図面1
・D-102 改スーパー4 図面2
(2)10cmトールボーイ・スワンタイプ
スワンの音を、前面上部開口でトールボーイ型で実現したい・・・と考えた設計したものです。非常に板材を多く使いますが、強度の高い良い箱になるとは思います。
砂利や鉛を入れるスペースも設けた設計です。これも出来れば作って検証してみたいのですが予算と場所が問題です・・・・。
・10cmトールボーイ・スワンタイプ 図面1
・10cmトールボーイ・スワンタイプ 図面2
・10cmトールボーイ・スワンタイプ 図面3
(3)D-118 改 前面の平面を解消したもの
これは殆どD-118なのですが、正面からの顔をD-37などと同様に彫りを深くしたくて改造したものです。音道は短縮になっていますが、途中の広がりは工夫して確保しています。音はそれほど変わらない??のではないか??と思っています。
格好は正面からの様子が・・堀が深く、こっちの方が良いと個人的には思いますが・・・。
(4)8cmミニバックロード
自分でも8cmを設計してみました。どうなるのか??は不明です。作ってはいません。
でも顔はやはり階段状のパーツなどバックロード風にしております。
バックロードらしいデザインと設計の計算からすると、結構良好な音になるのではと思いますが、先日のミニバックロードの方が作りやすさの点で優れていると思います。
こちらのミニを選択する場合は、「らしいデザイン」と「ホーンが長くて、より低音に期待できそう」ということが決め手になると思います。(最近の勉強から考察しますと、空気質の容積が少々大きいのではないか?という点と、スロートが大きくないか?の2点が気になってはおります)
スピーカーの自作 しょの6
「スピーカーの自作 しょの6」
申し訳ございません。シリーズ第6弾?『しょの6』でございます。
ご興味ない方・・・本当に申し訳なく思います・・・。
今回はスピーカーの自作「偏」の6回目でございます。
前回までに、
①D-101S(スーパースワン)からはじまり、
⑥FE88ES-Rのトールボーイ型バックロードホーン(オリジナル)まで書きました。
そこで、今回は残った自作スピーカー(小物など)をまとめてご紹介いたします。
(作ったもののご紹介はこれが最後です。この後、図面だけのモノをご紹介いたしまして当面の最後といたしますが・・・。)
長い間、本当にすみませんでした。
で、今回の内容は、
(1)D-37ESというD-37のMAKIZOUさん仕様のESバージョンのご紹介
(2)FE83Eという定番の(普通の)口径8cmスピーカーを使ったミニバックロードホーン
(たぶん静岡に在住?の方が、ネットに公開して下さっているバックロードの図面の通り製 作したものです。ミニでも音は良いです・・。)
(3)長岡先生のBS-28という評価の高いバスレフ型のスピーカーの若干の設計変更・ユニ ット変更のバージョン。
(4)ミニミニ・テレビサイド用バスレフ 8cm
3台の写真です。D-37ESとBS-28改、(D-99(改)ES-R)がありました・・。
の4点が主なメニューです。
では、まず
(1)D-37ESです。
長岡先生のD-37は、9年程前に2台目の自作スピーカーとして作り、大変気に入って使っていました。しかし、その後FOSTEXさんから、使用していたFE168SSというユニットの次世代版となるFE168ESという超強力ユニットが登場しまして、小生の心を揺さぶりました。この新ユニットが気になりました。
音も相当良い。低音が出る・・。高域も延びている・・・。など、欲しくなる話です。
なんとかコイズミ無線さんで予約して、真鍮リングと共に購入し準備を始めました。
ですが、D-37のエンクロージャーを流用して、ユニットの交換だけをやっても、この新ユニットの能力を引き出せないと言う雑誌記事などが参考になり、箱から作らなくてはダメだなぁとも思っていました。
ネットなどで調べて検討・勉強しますと、FE168ESを使いこなす処々方法がありましたが、小生は広島の「MAKIZOU」さんのD-37ES版を良いな・・・と思いました。
MAKIZOUさんでは従来のD-37の幅だけを20mm?広げて、後は全く同じと言うD-37ESを用意していらっしゃいました。
小生はこれを注文しました。例によってスーパー・シナ・アピトン材の15mmでお願いしました。
届いたのは相当前(1年以上?)ですが、製作する意欲のダウンや仕事の環境変化・・また、スーパースワンなど他のスピーカーを売る決心がつかず、従って、作っても置き場所が無いなど・・重なりまして、作らずに材料のまま、ずっと置いておいたのです。
結局2006年の秋になって、スワンや他のスピーカーを売る決心がついて、スペースも空くので、めでたく??D-37ESの製作開始となりました。
組み立ては長岡先生の『こんなスピーカー見たことない(一刊目)』という本に詳しいです。
幅が20mm広がっただけですから、こちらをご覧くださいませ・・。
組み立て式、通りに作りました。このESでは面倒な三角材は入れていません。
一部で三角材は入れないほうが低音が出る・・・などの話もあり、今回は入れないでやってみました。正直に言えば、この頃、製作の「根気」が落ちて・・・いましたし・・・。
写真がありますので、ご覧ください。
完成してトゥイーターT900Aを乗せました。 バッフルの裏を加工しています。
音道の中もステインで事前に着色します。 三角材はつけていません。
空気室下の空間はミクロンウールを充填 音道の平面に白の3mmフエルトを・・・
組み立て前に油性のオイルステイン(メープル)で着色し、組み立て後、2液性ウレタンのクリアで3回ほど、ガン吹き塗装をしています。
このD-37ESでは吹き付けたままで、スプレーのツブツブを消しておらず、コンパウンドでは磨いておりません。
ツヤツヤではなく「しっとり」した光沢にしています。磨くのは後からいつでも磨けますので・・・塗料を吹き付けたまま・・に敢えてしています。これはこれで味かなと思いまして・・。
(最近、チョットだけ磨きました・・・。)
肝心な音ですが・・、やはりハイスピードで飛んできます。
小生のレベルの耳では家庭用としてこれ以上は不要では?と思うほど、音離れ、抜け、切れ、粒立ち・・などが良いと思いました。・・・何を聞いても「凄い」のです。
聞き込むと少々疲れるくらいの情報量ですし・・・。
しかも、エージングという概念はあまり関係ないみたいで・・・もちろん一ヶ月程度でユニットの馴染みが出て、さらに素直というか、角が取れるといいますか、柔和?に・・良くはなりますが・・・、鳴らしはじめから、しっかり低音が出ており、大変驚きました。
低音感は従来のD-37のFE168SSというユニットの時とは、比較にならないくらい、しっかりありました。
8.5cmのFE88ES-Rとは異なり、低く沈み込んだ音域から低音が出ており、音楽全体の重心がしっかり下がって安定する感じです。
特筆はバランスの良さでしょうかね・・・。上も出ていますし・・・。
ただしトゥイーターは必要だと思いますですが・・・。
アナログの再生とのマッチングも良いようで、音にうるさい方で、元PCM音楽放送局の方が拙宅に遊びにこられた時、アナログでビートルズのレット・イット・ビーを聴かれ、ご本人曰く、「不覚にも涙が出た」とおっしゃった・・ことがありました。
ビートルズがこんなに良い鳴り方で、きちんと音が出ているのは珍しいことで、久しぶりに驚いたんです・・・とのことでした。
小生はそれほど耳に自信がありませんがうれしい話でした。
ちなみに小生は、もうオッサンで年ですが、モスキートーンは宇宙人のレベルは無理なものの、その手前までは全部聞こえます・・・。何の参考にもなりませんで・・・すみません。
(2)FE83Eのミニバックロード
ネットを見ていたら、おそらく静岡?にお住まいの方が、ミニのバックロードを設計され、図面を公開されておられました。一見して良さそうに思える合理的な設計で、「これは良い」と作ってみました。
何ら変更していません。図面どおりです・・・。
http://www2.tokai.or.jp/livesteamloco/index.htmがその方のホームページです。
オーディオと言う項目の中に図面がありました。
有難うございました。作ってみました・・。
作ってから、下地に「との粉」を水で溶いて、少々(水5にボンド1くらい)木工ボンドを加えたものを塗り、目止め(塗料が染み込み過ぎないように)をして、さっと紙やすり(400番)で表面をサンディングしました。これで塗装の下地はできます・・。・・面倒でしょうか?
それから水性のウレタン塗料のメープルカラーを完全に乾かないうちに、3回ぐらい重ねて塗っただけです。
会社でチョット聞く用に使っています。十分良いです。小さくてもバックロードのピュアな感じはありますし・・・。
もちろん、組み立てに際しては、ユニット固定に爪つきナットを使うなど、小生の組み立て方は踏襲しています。
カワイイし、これは意外なほど良い音です。
写真が、組み立て途中の様子からありますので、ご覧ください。ご参考に・・・。
ミニでも一応バックロードらしく、ホーン開口部に階段状の音道があります。
このスピーカーは意外に十分良くて・・・かえって考えさせられます・・・。
これでも良いのではないか・・・と。
じっくり聞き込まなければ、低音の沈み込み不足などの欠点も大して感じませんし、破綻も感じません・・・。複雑な思いです・・・。
フルレンジスピーカーというのはそう言うものなのでしょうね・・・。まとまっているんですね・・・。
(3)BS-28改造版の製作
これがバックロード好きの小生にしては、珍しい?と言いますか、初めて挑戦したバスレフ方式のスピーカーです。
キッカケは月刊ステレオさんの記事でした。
BS-28は侮れない凄いスピーカーで、長岡先生の傑作、「モアイ」と言うスピーカーの片鱗を感じるような音・・・とか。
それを読んで、小生いつかは作ろうと思っていました。
しかし、時は流れ、流れて・・。
FOSTEXさんのこのスピーカー用のユニットが廃盤になってしまいました・・・。
もうオリジナルと同じユニットが入手できませんから、作れないのです・・・。
で、ガッカリしていたのですが、ある時ふと遊び心が湧いてきました。
台湾製の安価なユニットですべてを置き換え、非常に安価に作ると言う風に目標を置き換えたのです。面白そうですから・・・。
このスピーカーは片側にウーハー2個左右で4個 トゥイーターも片側に2個左右で4個使います。つまりユニットは8個・・・。
でも台湾製。ウーハーもトゥイーターも1個2,980円でした。激安ですね。
で、片側11,920円でユニットが揃います。
(最近ですとトゥイーターがネオジウム磁石で970円と言うのもあります・・ますますこの手の改造では・・・ねらい目ですね)
それで、左右でもその倍23,840円。ベニヤは15mm厚のシナ合板で1枚6千円くらいでしょうか?板も相当、余りますが・・。
小生はトゥイーターを一段落として、表面上は面一な感じで埋め込むために、バッフル版は
15mm厚のシナベニヤの上に、4mmのシナベニヤを重ねています。4mmのシナベニヤを入れても、板代は安いですが・・・・・・。
(段落ち・・にするには、素人は「彫る」より、「貼る」・・にしました。写真でご確認ください)
この設計の特徴は、ネットワークにアッテネーターが無い、長岡式なことです。
つまり8Ωのウーハーを並列の結線で4Ωにして使い、8Ωのトゥイーターを直列の結線で16Ωにして使います。
バランスとしてウーハーをブーストして、トゥイーターへの入力のパワーを下げることになり、結果的にアッテネーター(ボリュームつまみの事です)無しで音のバランスを取る・・十分な低音を狙う・・・と言うネットワークを嫌う長岡先生らしい面白い工夫と設計なのです。
ですので、ネットワーク回路のパーツもウーハー用のコイルとトゥイーター用のコンデンサだけです・・・。
このスピーカーは、確かに月刊ステレオのオリジナルとは、ユニットも台湾製で異なりますし、箱のサイズも奥行きを20mm増やしたりと、遊んでいますので、なにかと違いますから、なんとも言いにくいですが、「なかなか良い音で、これはこれで十分」でした。
正確に、正直に言いますと、バックロードホーンを聞かなければ、これはこれで、何の不満も感じない、とても良い、メインになれるスピーカーだと思いました。
その後、小生はこれを2WAYスピーカーの代表例のような感じで扱っています。
専用の台も作りました。
置く位置を耳の高さに合わせたら、このスピーカーのかなりの能力が初めて分かりました。
音場感が、かなり良い・・のです。
バックロードホーンの自作の時に、聞き比べる対象にも使っているのです。なんとなくですが、このスピーカーは小生から見て、妙にまとまった音質で、市販品っぽいなぁ・・と言う感覚もあるのです。
バックロードとの比較で、不満を言えば、トゥイーターの力がまだ少々強く、若干、低音不足気味に感じると言うことでしょうか。
精細・精緻な音で、音場が縦に高く、また横にも大きく広がるようにできる感じで、仮想同軸型の特徴でしょうか・・・独特なイメージがあります。
これは好みの問題もあるでしょうが、「相当良くて侮れません」。
明瞭な音の感じが好きな方には、おそらく堪らない魅力?ではないでしょうか・・・。
価格を考えたら、この程度の低音不足の話は言ってはいけない・・・欲張りすぎな要求なのかもしれませんが・・。
と言いますのは、ユニット片側4個のお値段はD-99ESRの真鍮の「リング代1個」とほぼ同じ(やや安い)ですから・・・。
まあ激安ですが・・・これは面白いスピーカーです・・。・・・・写真がございます。
 台湾のユニット(ウーハー)のポリプロピレンの透明コーン
台湾のユニット(ウーハー)のポリプロピレンの透明コーン
が見えます。中が透けて面白いです。
完成写真とバッフル。トゥイーターを一段落として平面的に取り付けたいので、二重構造です。ユニットの円が上手に切れていません。円がガタガタです。寸法のミスや、やり直しで汚くなりました。
内部のバスレフポート・・簡単な構造です。 バッフル裏の爪つきナットの写真
箱の接着と内部のネットワーク配線、吸音材の貼りこみで、箱は完成です。後は仕上げ・・・
との粉とサンディングで下地の調整をした後、
水性のウレタンニスをさらっと塗ってみました。
(4)FE87E使用のミニミニ・テレビサイド用バスレフ
これは自宅の14インチのテレビの横に置くための防磁型ユニットのバスレフです。
図面もありますが、何の事は無い、普通のスリット型ポートのバスレフでございます。
よろしければ、ご参考に図面と写真をお使いください。
水性のニスを塗って手軽に使っていますが、じっくり聞いてみますと、やはり血統は争えないといいますか、FE88ESRに近い音質を「ちょいと」・・・感じます。
FOSTEXは、FOSTEX・・なんですね。
まあコーン紙など似ていますからね・・・。
人によっては、FE88ESRと大して変わらない・・・などとも言います。ただのバスレフですが、結構これ、鳴らすと鳴ります。
侮れませんです・・・。
大きな音を出さなければ相当良いのです。
こじんまりと小音量で聞くなら、十分な性能があるのが、FOSTEXさんの8cmフルレンジだと思います。
8cmは良いです。トゥイーターが不要ですから・・・。
写真をどうぞ・・ご覧ください。
下地は定番のとの粉です。塗料は水性のウレタンニスです。乾くと水を弾くので、やや濡れたうちでないと塗り重ねが利きません。
簡単に仕上げができますが・・・。そこそこ?のできばえが限界ですね。
スピーカーの自作 しょの5
「スピーカーの自作 しょの5」
まだ続いておりますシリーズ第5弾?『しょの5』でございます。
いつも大変申し訳ございません。
ご興味ない方・・・まことに申し訳なく思います・・・。
今回はスピーカーの自作「偏」のとうとう5回目であります。
前回までに、
①D-101S(スーパースワン)から
⑤D-99ES-R(FE88ES-R用 ブックシェルフ型)小生の図面あり・・・の話まで書きました。
そこで、今回は、
⑥FE88ES-Rのトールボーイ型バックロードホーン(オリジナル)について・・を書きます。
そもそも、このトールボーイの設計は3つの理由で始めました。
前回のD-99ES-Rがお嫁に行ってしまった。(とても寂しい)
それでも好きな音のユニットだったので忘れられず、どうしてもまた聞きたい。(相当にお気に入りのユニットです)なんとかオークションで入手できましたし・・・。
現スーパーエース・スピーカーのD-37ESは素晴らしいのですが、トゥイーターを使いますので、高音域にホーントゥイーター独特の癖(やや刺激がある)はあります。
また、良いスピーカーですが、情報量が多すぎ、大変「強い音」なので、楽しいけど疲れる・・・ので体力が要ります。それで、普段、気楽に聞く小型スピーカーも欲しい・・・のです。
しかし、作るとなりますと、また同じFE88ES-Rというユニットを選択して作るのでも、従来と同じ設計ではなく、さらに言えば根気・根性のいる砂充填のスタンドが不要な設計のバックロードにしたい!!とも思いました。
そこで、スタンド不要といえばトールボーイ(背の高いスピーカー)です。
もちろんバックロードホーンで・・。
板材の取り都合(とりつごう)からして、設計以前に高さは90cmでほぼ決定です・・・。さてさて、どうなりますか・・・。バックロードは作ってみないとわからない(長岡先生のセリフです)スピーカーの代表ですから・・・・。
それでは、早速ですが・・。
口径8.5cmの大好きなユニットを使用した、トールボーイ型バックロードホーンの製作です。
まず、ユニットの復習から・・。FE88ES-R。このユニットは何と言っても40khz(キロヘルツ)まで延びた高域のさわやかさに特徴ありです。本当にトゥイーターが不要で、これが大変・大変、大きなメリットだと思います。
さらに、今回は、このユニットのスペック表から特にQ0(キューゼロ)を気にして再設計してみました。
このユニットは強力という話とは裏腹に、良く見るとQ0は意外に大きいのです。
10cmの限定生産のユニットで0.23(FE108ESⅡのQ0)
8cmの限定生産のユニットでは0.31(FE88ESのQ0)
で、このFE88ES-Rでは0.46です
数字が大きくなるとバックロードでなくても、バスレフなどでも使える、マイルドなユニット・・と言う事になるようです。
ですので、絞り率には少々考察が必要と思ったのです。
実際、ES-Rの時、特定のCDの一曲位ですが、低音の強いパルスの入力には「弱い」のを感じていました。
音がボコボコ言う感じになるのです。
いままでの勉強からしますと、Q0が小さい超強力ユニットのバックロードの設計ですと、絞り率90%とかでOKで、あまり絞らないでも良いようだったのですが、こう言うQ0が大きいマイルドな特性のものは、70%くらいに絞り込んだ方が良いのでは?という考えを持ちはじめました。
スロートを音が通過する時のプレッシャーで、ユニットのコーン紙が動きすぎてしまうのを防ぐ感覚です。空気バネで動き過ぎを止める!!とでも言いましょうか・・・。そう言う設計をしようと思いました。
1.設計の留意点・・
一応、小生の計算の内容をお話ししておきますと、まずスピーカーの後ろの部屋の大きさ・・・→空気室の容積を(D-99の1200ccをガイドラインにしつつD-99ESRの経験から)1400ccに設定しています。
低音時のユニットのバタつきを抑える意味で、非常に感覚的な事を頼りにした設計で恐縮なのですが、大きすぎない1400ccです。
この後、検証するとしたら1300ccくらいがどうか?が気になりますが・・・。
(実際2月18日現在の状況では100cc程の木のブロックを一つ入れ、計算では1300cc程にしており、結果は良いように感じます。さらに、もっと体積を小さくする時は、ウッドブロックにフエルトをまいたもの等を追加し、空気室に放り込めば完了で、簡単です。体積を増やすのは殆ど不可能ですが、縮小するのは粘土の塊など、何か物を入れるだけでも出来ますから・・・それで大き目の提案が安全と言うことになります。)
ちなみにFOSTEXさんの、このユニットの説明書に示されてある、バックロードホーンの設計(例)では空気室1200ccで、スロート面積30平方センチです。
長岡先生のD-99では1200ccで良い結果でしたが、少々大きい8.5cmのこのユニットでは、空気室も少々大きくした方が良いのでは?と思っております。
次に難しいのはスロート(ラッパの入り口・・の面積)の絞り方です。
スピーカーの振動板面積の何%にスロートを絞るか?が大変重要なのですが、小生は当初の設計では84.7%くらいにしていました。
どうも、この位が良いのでは?と言う事で暫定的に採用した数字なのですが、このユニットは意外にもQ0(キューゼロ)が大きく、噂に聴くよりは、超強力ではない特性で、バスレフ方式でも使えるくらいなので、スロートは70%位の絞り方でも、低音でユニットのコーン紙が暴れずに済んで、かえって良い結果の可能性が高い・・と考え直しました。
実際に小生の実験では、スロートを26.4平方センチ、絞り率71.7%まで絞り、聴感上は好ましい結果を得ています。(小生は測定用の機材を持っていません・・・聴感の話ですみませんです)
(この写真のスロート部に、調整後、さらに1枚、4mm厚のシナベニヤを加えています。バッフル板の裏側からは打ち込んだ爪つきナットが4個見えます。空気室の下のデッドスペースにはミクロンウールをギッシリ詰め込んでおります。)
後はホーンのカットオフ周波数を、よく採用する24ヘルツ・・に設定して、計算したとおりのホーンを箱の中に組み込んでいます。
スロートから何センチ進んだら、スロートのホーン断面積の何倍・・・1.3倍とか・・になるかを計算していきます。(早見表があります)
設計上留意したのは以下の点です。
A.スリムでホーンの開口部をユニットに近い上部に持ってくる!!
B.音道の中のデッドスペースには板材を贅沢に投入し共振を防ぐ
(と言っても、板取り上は3×6定尺合板2枚から、すべてのパーツを切り出せ、問題なく収まっていますので、補強には目一杯板を使ったほうが効率が良いのです・・。)
C.開口部周辺や底部には、板材の2枚重ねと3枚重ねをおごり、強度を上げる
D.三角材として、10cm角材の半割を、2箇所は必須として、低音の吐き出しをスムーズにする
です。
しっかり低音を出すためには、ホーン開口部周辺の贅沢な補強が必要と感じております。
図面をご覧下さい。
・FE88ES-Rの
トールボーイ型バックロードホーン(オリジナル)図面を表示
組み立て時の写真は、設計の修正前で、小生の自宅用のものです。
ですから、ホーン途中の板材の塊のような⑫~⑯の部分の枚数変更(写真で4枚を3枚に変更)や、開口部の下側の板材の枚数変更(写真で2枚を3枚に変更)をしたりしています。
設計変更後の「図面」を「正」としてくださいませ。
作った後に気が付く補強の合理性・・・などで、あくまで良い方向に、少々設計の変更をしているからです。
2.板材の手配
板は15mm厚で、広島のMAKIZOUさんに、お店のオリジナル素材である、スーパー・シナ・アピトン合板で、オーダーカットをお願いしました。
MAKIZOUさんにオーダーカットをお願いするのは、D-37ESの時に続き、今回で2回目ですが、本当に素晴らしい精度と情熱で対応していただけます。
梱包の丁寧さや、組み立てを意識したカット寸法のアドバイス、パーツの同梱の配慮など・・・愛情までを感じさせるお仕事ぶりです。本当にいつも感心いたします。
MAKIZOUさんでは、丸い穴も四角い穴も開けてくれますので、送って頂いたら後は丁寧に組み立てるのみです。
今回は側板にはネジを打ち、強度を充分出し、美的な面では、ネジを隠すように、その上から3mmのシナベニヤで化粧をする方法をMAKIZOUさんとご相談して選択しましたので、木口テープは3mmのシナベニヤを貼った後からしか、貼れません。
そのため、木口処理の加工はセルフサービスでやりました。
でも難しくありません。G17などのゴム系ボンドを木口に塗って乾かして、その上から初めからのり付きの木口テープをドライヤーなどで温めてから剥離紙をはがして、貼るだけです。出っ張りはカッターで切り取ります・・。
15mm幅の木口テープはMAKIZOUさんから購入しました・・・・。
側板用の20mm幅のシナの木口テープは東急ハンズさんで買いました。(側板は15mm+3mmです)
3.パーツ確認と下準備
パーツをそろえて過不足を確認し、組み立ての開始です。
まずは、寸法の確認からです。
音道構成パーツはすべて幅120mmです。
平らな板の上で、120mm同士のすべてのパーツを背比べするようにきっちりくっつけて揃えて見ると、狂いがある物が出っ張ったりします。この段階で出っ張るパーツにカンナを掛けたり、ヤスリで削ったりして綺麗に均しておきます。これはコツです。後々の組み立てが楽になるので是非やっておきたいものです。(MAKIZOUさんのカットでは、誤差のあるパーツは、一つもありませんでした・・・凄いです。)
事前の準備としては、さらにフロントバッフル板に、裏側からスピーカーの取り付け用の爪つきナットを打ち込んで、つけておきます。
この程度の小型のスピーカーユニットでは取り付けるネジは4mmを使います。従って爪つきナットも4mm径用です。(爪つきナットは8個入って100円くらいです。)
取り付けは、この爪つきナットの外形が5.5mmくらいですから、ドリルの穴は5.5mmの穴となります。穴の位置は図面的にも割り出しますが、早いのは現物での確認です。
穴の中心を出すためには、穴を開けて切り離した丸い不要な部分を中心に入れて、中心からネジまでの距離をコンパスで墨付けしてから、丸い部分を外し、穴にユニットを置いて、ユニットの取り付け用の穴にコンパスの線が見える範囲で、キリでチョットだけ穴を開けると安心です。(ハンズさんからはこの穴の内部の丸い板も送られてきます・・ご安心を)
・・・この墨付けと現物あわせの併用をやりますと、ユニットがバッフルの穴に対して偏ってしまいませんし、寸法のミスも現物で確認可能ですから安心です・・。
爪つきナットを打ち込みますと、実際はユニットの丸い開口の内側の部分に、ナットの一部(金属の針部分)が少々が出っ張る筈です。
これはナットを打ち込んだ後で、ヤスリで削ります。
木口テープも大部分は事前に貼ります。
①の上下、⑰の上、⑳から(22)の上、⑯の上側・・を先に貼っておきます。
側板(23)(24)の周囲は、組み立て後に貼り付けます。
ボンドを指で塗り伸ばし、乾燥後、温めた木口テープを貼ります
ステイン着色後のパーツを並べて乾燥します
その他の準備では、今回は組み立て前に着色をしています。
メープル色のオイルステインで、見えそうな範囲の音道内部からその周囲、さらに3mmの側板の化粧板など、すべて塗っておきました。
ステイン塗装は刷毛で塗ったら、すぐにきれいなボロ布・・でふき取り、ムラにしない・・という塗装方法です。
⑳の裏側や三角材にも着色が必要です。
シナの木口テープの後加工の部分にもステインを塗ります。
テープには何故か色が付きにくいので、木口テープだけはステインの2回塗りをしますと、周りの部分との色合いが揃います。
端子に半田付けしたコード 組み立て時の端子の取り付け
さらに、スピーカー端子を⑰の上部に取りつけておきます。
2個の穴(10mmくらい)に、あらかじめ半田付けしておいたスピーカーコードを通し端子を木ネジで取り付けておきます。
穴の位置は⑰の上端から35mmくらいが穴の中心になる感じです。
使うスピーカーコードは、何しろ長めが肝要です。
コード自体は38.5cmの箱の後ろ側にあるスピーカー端子から出て、バッフルの穴を抜け、箱の上に乗せたユニットの半田作業などの余裕を見るのですから、80cmくらいの長さで良いと思います。
4.組み立て・・音道から・・
一応、組み立て式を書いてありますので、その通りに組むのが無難です。
初めての方は、側板(23)の上に①~(22)までを並べ、まずあたりをつけてみることをお薦め致します・・。作る段取りのイメージが湧きますから・・・・。
組み立ては、まず、空気室部分を構成をするパーツ⑤に②~④を取り付け、さらに⑦とその上の★の4mm厚の2枚の板で、スロート部分を作っておくことからスタートです。
⑦の後に⑨も取りつけておきます。
①のバッフル板には⑥を取りつけておきます。
⑫~⑯の板の塊は、先に貼り合わせて作っておきます。
一般に板の貼りあわせは、ズレたら困るので、まずボンドを付けずに板同士をきっちり合わせ、下穴をだけ穴あけします。ドリルの刃はこの場合は板3枚を貫通しない程度に、ドリルからの刃の出方を45mm以下に調節します。
6箇所くらい穴あけしてからボンド付けし、貼りあわせ、ボンドが落ち着いたら、ネジが貫通して飛び出ないようにやや短い40mmくらいの長さのコースレッドで締め付けます。
こうして貼りあわせは「穴が先」「・・それからボンドで接着」「コースレッドを締める」とやると、ズレにくく、うまく行きます。
もちろん穴あけした時の通りに貼り合わせませんと、穴がずれ意味がなくなります。
ボンド付けのとき、部品の裏返しをしないように、貼り合わせる面が分かるマークをしておきます。
この時、平らな板の上で組み立てると塊の部分自体の精度も上がりますし、L字型の部位との接合もネジレ無いで組み立てられ、うまく行きます。「平らな板の上で組みたてる」がポイントです。
この塊を⑪につけますとL字型が出来上がります。この順番でないと段取りが悪くなります。
塊の後は⑪への三角材の取り付けになります。
で、さらにその⑪を②・⑤に取り付け、その後②~⑤の上に①を取り付ける段取りです。
ここまでで上部のパーツ部分が出来ています。
空気室周辺の組み立てから、上部の音道全体の組み立てへ・・
つづいて後部のパーツの組み立てです。
⑰に⑧、⑩を取り付けます。
その後、先に⑱と⑲を貼り合わせておき、⑰に取り付けます。
⑱と⑲に⑳を打ちつけ、⑳に対してあらかじめ貼りあわせた(21)(22)を付けて行きます。
音道全体が見えます。開口部近くは板を厚く使い、相当の補強がされています。
三角材は切り出しが大変です
2個目の三角材もこの後に付けます。三角材は下からの固定で良いと思います。
(三角材は一辺が10cmくらいの角材を斜めに半分に切ったものを片側2個使います。
三角材は開口部へ低音を押し出すために大変有効なパーツのようです。小生の場合は、1辺が10cmくらいの角材を手のこで(のこぎりで)斜めに裂いて使っています。これは「のこぎり」の縦刃(たてば)で無いと、うまく切れませんので、両刃の「のこぎり」がぜひ必要です。
これを鋸で切るのはかなり難しいですがホームセンターなどでは斜めのカットはやってくれませんので、練習してコツを体得してからやる以外に方法は無いようです。音道の途中には高音吸収用のフエルトを貼る・・・という工程もあります。)
さらに、この「後部」と「下部」のブロックを「上部」のブロックに付けると、構造体が完成します。
この後、手作りのスペーサーを必要とする組付けになります。
この出来上がった構造体を側板にネジ止めするのですが、この構造体はまだブラブラで、
パーツ間の寸法がガタガタしてしまうからです。
構造体を並べ、音道のそれぞれの幅30mm、40mm、50mm、70mm、85mm、115mm、130mm、165mmなどのパイプ状のスペーサーを厚紙などで作っておき、それらを所定の場所に入れますと、構造体が寸法的に落ち着きます。そうしてからボンド(乾燥の遅いもの)を構造体に付け、ネジの位置を鉛筆でマークした側板を乗せて、穴あけ、ネジの頭部のザクリ、ネジ締めとなります。
側面の板がズレが無いように角を決め、コースレッドをまず四隅に打ちます。
ボンドが落ち着いてきたら、5cmおきくらいにドンドン下穴をあけ、ザクリ、コースレッドを打ち込みます。
はみ出た木工ボンドは水溶性ですから、ぬれ雑巾でドンドンふき取っておきます。
片面で50本くらいのコースレッドを打つでしょうか?
狭くて5cmから、広くて10cmくらいでネジを打ちます。
ドリル径は2.5mmを使い、ネジ頭用のザクリはそれに向く専用のキリを使います。
写真参照ください。
コースレッドは32mmを中心に~1部には38mmを使っております。
ただし三角材の固定用には、51mm~65mmなども使います。
(小生は組み立て用に、ドライバー・ドリルを3台同時に使います。
下穴あけ用、ザクリ用、とネジを締めるドライバーの3台の使い分けをするのです。
3台使うと刃やドライバーを、その都度、付け替える時間と手間が短縮でき、早いのです。)
側板が片側に付いたところで、フエルトの貼り込みをします。
1mmくらいの薄いフエルトを⑤の下の部分と⑪の上面に木工ボンドを薄くつけ、貼ります。ホーンの中の高音を減衰させるためです。
⑲の上にも三角材に掛けてフエルトを貼りこみます。(高音の反射対策)
バックロードホーンの開口部からは低音のみを出すのが理想で、高音は減衰しているのが良いのです。フエルトなどは高音吸収用です。システムの中・高音はスピーカーからの音を直接聞き、低音はスピーカーの後ろに出た音をラッパを通して大きくして聞く・・のがバックロードホーンですから・・・。
もちろん反対側の側板をつけた後(両側取り付け後と言うこと)では、先ほどのスペーサーは二度と外せませんので、音道に残ってしまいます・・。必ず片面が終わったらこのスペーサー郡は外します。これは本当に注意してください・・・。残して組んだら最後ですから・・。
根気のオプション三角材!! コースレッド(木ネジ)だらけの側版の写真
側板の取り付けが左右両方とも済みましたら、小生の場合、化粧用の3mmのシナベニヤの板を側板の上から貼りつけました。
この貼り付けはボンドのみで実行です。
貼ってから体重を掛けてスピーカーに〇〇分間も乗っていました。
側板の化粧板貼り付け後、側板周囲の木口テープを貼ります。
G17などのゴム系ボンドを使用します。
その他
写真にはその他の三角材が写っております。
これは、根気のある時のオプションとお考えください。
やる気があったら、やるのも、また楽しい・・・です。効果の程は未確認ですが、気のせい程度の効果・・と言う方もいるくらいです。
小生は、このスピーカーがサブとは言え、期待するエースの1台ですから、ちょっと根性で三角材を作って入れました。
三角材は面倒ですが・・・。
5.組み立て・・・配線
組み立てが終了しましたらユニットの取付けです。小生の図面では先に真鍮のリングを付けてから、スピーカーの取り付けです。
リングの後にコードを通し、ユニットの端子に半田付けしました。
半田付けは賛否両論のようで、ファストン端子というハメるだけの端子にする方もいますが・・。
小生は半田付けを愛用です・・・。
6.仕上げなど・・。
これで組み立ては完了ですが、塗装など、仕上げが待っています。
仕上げは個々の趣味ですが、小生はこのスピーカーでは、木目を活かす作りとしましたので、「メープル」カラーの油性オイルステインの上から、透明の2液性ウレタン塗料のクリアをハケ塗り塗装をしました。ウレタン塗料は手指乾燥するまでは30分くらいで速いですが、重ね塗りのためには5~8時間くらい後の硬化するまでの時間を見ます。ちなみに水ペーパーで削るためには、完全硬化する20時間後を目安としています。
塗るのは7時間おきとして、朝8時、午後3時、夜10時の一日3回が限度でしょうか・・。
そして、削るのは翌日、丸1日後・・ですね。
時間を空けながら4回ほど重ねて塗って、その上から翌日に1000番の耐水ペーパーで水研ぎをして、刷毛の目を削り、その後、Tシャツのボロなどに自動車塗装の仕上げ用の研磨剤(コンパウンド)をつけて根気良くゴシゴシ磨いて仕上げます。
コンパウンドは自動車補修用品の売り場で購入し、細目から極細目を使い分けして、愛用しています。
耐水ペーパーのくすんだスリ後が消えて、ピカピカ・艶々になります。
まるでプロの仕上げの感じになります。塗装は、実は塗るより磨く感じが正解?!です・・。
このクリアもそうですが、ウレタン塗料はいつも「おもしろ塗装工房」さんで通販で買っています。
http://www.tosou-ya.comをご覧ください。
2液性のウレタン塗装は、高級家具の様なフィニッシュになります。
この塗装は2液を混合したりなど、色々面倒ですが、手間を掛けて厚塗りすると、まるでプロの高級家具そのもので、完成するととても綺麗なので、お薦めできます。
7.完成
いよいよ・・・完成です。
空気室へのウッドブロックの投入やスロートの調整でかなり良い音がしました。
全体のまとまりが良く、良い音です。
特定の録音のバスドラムの素早い低音など・・ごく一部の音の再生を期待しなければ、コントラバスやベースの低音は充分すぎるほど出ています。
やはりハイスピードで音が飛んできます。
エージングもしていないのに、のっけからかなり良い音なのはD-99ESRの時と同じです。
8.5cmとは思えない低音の豊かさに、最高40khzまでの高音の抜け。
スッキリ繊細なのはブックシェルフの時と同じ傾向です。
D-99を上下に周波数を拡大した・・・性能と言う感じです。
アン・サリーさんのCDの中にある、バスドラムとベースの重なった難しい低音・・これでも、音量を欲張らなければ、何とか破綻せずに鳴ってはいます。・・これは今まで難しかった再生なのです。ギリギリ出ているでしょうか・・・。
リー・リトナーの「カラーリット」のエレガットの抜けは大変良好です。
BEST OF FOURPLAY の一曲目、MAX O MANも最高に音が抜けてきます。
女性ボーカルも申し分ありません。松任谷由実さんの初期のアルバムが涙モノのリアリティーで、生き生きしています。
ジャズの女性ボーカルでは、SACDのダイアナクラール。声の余韻が素晴らしいです。
コントラバスの低音も問題なしです。チェコフィルの2人の演奏になるデュオ・ディ・バッソのチェロとコントラバスが、とんでもない凄い音になって飛んできます。
やはり、弱点は特定の音質で録音した場合の、大音量時の低音のパルス的な短い音、バスドラムとか・・・、これが大音量再生ではモコモコ、ボコボコする傾向が、少々ですが・・・残ったことでした。
ユニットのコーン紙が大きく前後に動いていますが、さすがに8.5cmの限界があるのでしょうね。潰れた低音と言う感じになります。低音のパルス・・には弱い様です。
しかし今回はスロートを絞る調整をしたので、少しは良くなっているようです。
・・音が良いので、ついつい欲が出ますが、大音量時の限界はやはり、ありますですね。
優秀なスピーカーシステムでも、口径8.5cmは8.5cmと言うことでしょうか・・。
このスピーカーは現在、小生の小型スピーカーのエースです。
小生には、たまらなく良い音がします。
聴いていると、「なんて良い音なのだ」とシミジミ感じます。・・・また、意外な事に、結構な大きい音量で聞いていても、うっかり寝てしまったりします・・・気持ちの良い音とは、そう言う感じの音なのですね・・・。
※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。
耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。
有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。
スピーカーの自作 しょの4
「スピーカーの自作 しょの4」
とうとう?あらあら?シリーズ第4弾?『しょの4』です。
これまた期待は・・・明らかに・・されていない!!ですよねー・・。
大変申し訳ございません。
ご興味ない方・・・今回も無視してください。恐縮でございます。
今回はスピーカーの自作「偏」の4回目であります。
前回までに、①D-101S(スーパースワン)から
④D-99(エイトマン・・8cm、FE88ES用 ブックシェルフ型)まで書きました。
で今回は、
⑤D-99ES-R(FE88ES-R用 ブックシェルフ型)小生の図面あり・・・の話を書きますです。
そもそも、D-99ES-Rなんて長岡先生のスピーカーの品番は存在しません。
小生が長岡先生のご逝去後に発売になったFOSTEXさんの新ユニット、FE88ES-Rで、先生のD-99エイトマンを下敷きに、適宜変更を加えて書いた図面で制作したものを、便宜上勝手にこう言う呼び方をしているだけなのです。
大変申し訳ございません。
この型番には、Dもつけていますので、甚だ勝手に詐称しているようで、まことに申し訳ない思いで、恐縮の限りです。
しかし、もともと先生のD-99に基づいて、新ユニットFE88ES-R・・向けに諸般、計算を繰り返し、何回か手直しをして完成したもので、小生のオリジナルではないのです。しかし、板取りなど、多少の工夫も盛り込んでありますし、寸法に至っては一回りも大きくなっていますので、微妙ですが・・・、図面はお見せして良いのではと判断しています。
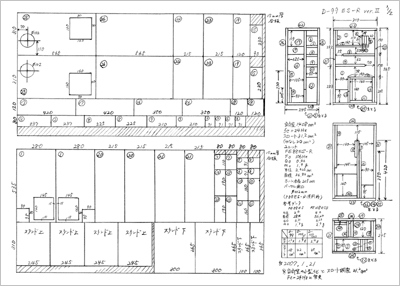
で、恐れながら、敢えてエイトマンの名前を踏襲してD-99ES-Rなどと言っています。(長岡先生のファンの皆様お許し頂ければと思います。)
設計内容については、実際の制作の結果も踏まえて何度か修正してありますので、さらに今後も検証は続けたいものの、この図面通りですと結果は、まずまず良いのでは?と思っています。(多少の自画自賛は入っております・・・念のため)
それでは、
口径8.5cmの大好きなユニットを使用した、D-99ES-Rです。
ブックシェルフ型バックロードホーン、D-99の派生ですので、(エイトマン“R”)でしょうか。
このユニットは何と言っても40khz(キロヘルツ)まで延びた高域のさわやかさに特徴ありです。本当にトゥイーター不要です。
このことの意味の大きさが分かる方には分かっていただけます・・・。好結果を期待できます。では、、、
1.設計変更の留意点・・
一応、小生の計算の内容をお話ししておきますと、スピーカーの直径(=口径)の大型化8cm~8.5cmに・・に伴い、エンクロージャーの少々の大型化を考えました。
まずスピーカーの後ろの部屋の大きさ・・・→空気室の容積をD-99の1200ccから1400ccに増やしています。
初期のこのモデルの制作においては1600cc程度でしたが、低音時のユニットのバタつきを抑える意味で、非常に感覚的な事を頼りにした変更で恐縮なのですが、実験の結果、縮小の方が良いと感じましたので、狭めて図面を書き直しました。さらに実験するとしたら1300ccくらいがどうか?が気になりますです・・・。
(さらに体積を狭める時はウッドブロックにフエルトをまいたもの等を、空気室に放り込めば完了で、簡単です。体積を増やすのは容易ではないですが、縮小するのは粘土の塊など、何か物を入れるだけでも出来ますから・・・それで大き目の提案が安全と言うことになります。)
ちなみにFOSTEXさんのこのユニットの説明書にある、バックロードの設計例では1200ccで従来のD-99と同じでした。
しかし、ユニットが異なる8cmのFE88ESと、8.5cmのFE88ESRが同じ空気室容量と言うのはかなり抵抗がありました。
D-99では1200ccで良い結果でしたが、8.5cmのこの新ユニットでは少し大きい方が良いのではと思っています。
次に難しいのはスロートの絞り方です。
スピーカーの振動板面積の何%にスロートを絞るか?が大変重要なのですが、小生は当面の設計で84.7%くらいにしています。
どうもこの位が良いのでは?と言う事で採用した数字なのですが、このユニットは意外にもQ0(キューゼロ)が大きく噂に聴くよりは、超強力ではない特性で、バスレフ方式でも使えるくらいなので、スロートは70%位の絞り方でも、低音でユニットのコーン紙が暴れずに済んで、かえって良い結果なのかも知れません。小生の手持ちのスピーカーで、同じユニットを使ったトールボーイ型のバックロードホーンスピーカーの実験では、スロート面積26.4平方センチまで絞りましたが、結果は良好に感じました・・・。
ちなみに上記FOSTEXの事例と、この設計の比較で面積換算しますと、絞り率の差は、3.2%でした。
FOSTEX版の設計が12cm幅のホーンで高さが2.5cmのスロートで、30平方センチです。これは81.5%くらいの絞り方です。
(当方は8cm幅で、高さ3.9cmのスロートであり、31.2平方センチです。この時の絞り率は、前出の84.7%になります。)
今後の実験ではスロートをさらに絞って8cm幅で高さ3.5cmに変更し、スロート面積28平方センチ、絞り率76.0%位が相当宜しいのでは・・・と考えております。
●このスロートの再縮小版の図面も、書いてありますので、おってこちら(スロート8cm幅で高さ3.5cmの図面)も時間を見て、このブログの下の方にアップしておきます。もし作られますなら、こちらの図面がより良いのでは・・と思います。お勧めいたします。
空気室とスロートが決まれば、後はホーンのカットオフ周波数を24ヘルツに設定して、計算したとおりのホーンを、箱の中に組み込んでいきます。(修正前のカットオフ周波数は28ヘルツを表から選択していました。しかし、この修正の結果で、実際の音道の変化は?・・殆どありませんでした・・・)
スロートから何センチ進んだら、スロートのホーン断面積の何倍・・・1.3倍とか・・になるかを計算していきます。(早見表があるのです)
工夫したのは前から後ろへの折り返し部分で、後ろ側で断面調整の板を2枚使って受けています。スムーズに音道が広がるようにするためには、この2枚の板が結構・・重要だと思います。このパーツの導入で組み立ては難しくはなりませんが、従来のこの種の設計には無いパーツですので、組み立て取り付け順(段取り)には注意が要ります。
順番を間違いますと、取り付けが大変(不可能か、ネジを斜めに打つ必要がでる)になります・・。
そして、その他の大きな留意点としては、ホーンの開口部のサイズ・形状を正方形で確保した事です。
ブックシェルフでしっかり低音を出すのは、ホーン開口部:ここの形状と補強が重要と感じております。
図面をご覧下さい。
組み立て写真は設計の修正前のものですから、空気室のスロート部のパーツや途中の音道の作りなどが少々異なります。
しかし、もし制作をされる場合は、修正版の最新の図面でお作りになるほうがよろしいと思います。
2.板材の手配
板は15mm厚と21mm厚のシナベニヤを東急ハンズさんの渋谷店で購入し、カットを依頼しました。(小生の実際に作ったものは、①のパーツや天地、左右などの部分に21mm厚のシナベニヤをおごり、補強強化したものでした。・・図面ではすべて15mm厚になっています)
渋谷のハンズさんでは、丸い穴も四角い穴も開けてくれますので、送って頂いたら後は組み立てるのみです。少々加工賃が掛かりますが、これは楽ですね。加工の精度も結構良いとおもいますし・・・。
3.パーツ確認と下準備
パーツをそろえて過不足を確認し、組み立ての開始です。
まずは、寸法の確認からです。
音道構成パーツは前面側はすべて幅80mmで、後ろ側は120mmです。
平らな板の上で80mm同士、120mm同士のすべてのパーツを背比べするようにきっちりくっつけて揃えて見ると、狂いがある物が出っ張ったりします。この段階で出っ張るパーツにカンナを掛けたり、ヤスリで削ったりして綺麗に均しておきます。これはコツです。後々の組み立てが楽になるので是非やっておきたいものです。
事前の準備としては、さらにフロントバッフル板に、裏側からスピーカーの取り付け用の爪つきナットを打ち込んで、つけておきます。

爪つきナットの打ち込みと、取り付け穴周囲の角を削った写真・・音の流れをスムーズにする
この程度の小型のスピーカーユニットでは取り付けるネジは4mmを使います。従って爪つきナットも4mm径用です。(爪つきナットは8個入って100円くらいです。)
取り付けは、この爪つきナットの外形が5.5mmくらいですから、ドリルの穴は5.5mmの穴となります。穴の位置は図面的にも割り出しますが、早いのは現物での確認です。
穴の中心を出すためには、穴を開ける時に切り離した丸い不要な部分を穴の中心に入れて、中心からネジまでの距離をコンパスで墨付けしてから、丸い部分を外し、穴にユニットを置いて、ユニットの取り付け用の穴にコンパスの線が見える範囲で、キリでチョットだけ穴を開けると安心です。このキリの穴があると、ドリルでの穴あけの時、刃が落ち着きやすく、真っ直ぐ穴を開けられます。(ハンズさんからは、この穴の内部の丸い板も送られてきます・・ご安心を)
・・・この墨付けと現物あわせの併用をやりますと、ユニットがバッフルの穴に対して偏ってしまいませんし、寸法のミスについても、現物での確認をするわけですから・・当然防げます・・。
爪つきナットを打ち込みますと、実際はユニットの丸い開口の内側の部分に、ナットの一部(金属の針部分)が少々が出っ張る筈です。
これはナットを打ち込んだ後で、金属用のヤスリで削ります。1000円くらいと少々お高いですが、ステンレス用の片側が「かまぼこ状」になっている「半丸」で、半分が「平面」のヤスリがお勧めです。
小生の経験では、ステンレス用でないと、ヤスリが弱いのか?なかなか削れなかったりしました・・。
4.組み立て・・音道
前後を分ける①のパーツが要です。このパーツの上に音道を構成をするパーツ②~⑬を並べて、こんな感じに取り付けるのだな・・と、あたりをつけます。
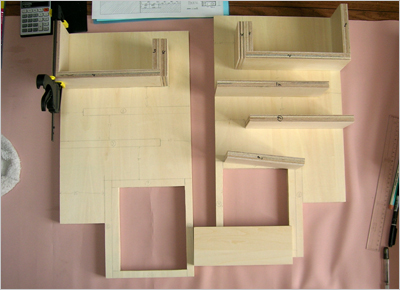
(左)鉛筆の線が見えます。並べて確認し、速乾ボンドで接着、落ち着いたら裏返して木ネジで!
①の板には図面どおりの寸法でパーツの来る位置に鉛筆でラインを入れておきます。
そうしましたら、いよいよパーツに木工ボンド(この場合「速乾」タイプを使います)を付けて、図面通りに板に描いた線に合わせて貼り付けます。

体重をかけ3分~くらい押し付けていますと、木工ボンドも落ち着きまして、一瞬板を裏返す間くらいは剥がれず、ズレず、にいてくれます。
このズレない程度の状態が重要です。
そこで裏返して、裏からドリルでネジ用の下穴を開け、ネジの頭が出っ張らずに入り込むようなザクリもやってから、コースレッドと言う細身の木ネジを打ちます。(裏からもパーツの位置のネジを打つラインは事前に引いておきます)
ネジの間隔は適当です。
狭くて5cmから、広くて10cmくらいでネジを打ちます。
小生の場合、組み立てには釘は使いません。
コースレッド(木ネジ)は下穴など面倒ですが、強力に締め付けられますから強度抜群になるのです。
もっとも面倒がって直径2.5mmの下穴をきちんと開けませんと、板が割れる事がありますから、工作は少々面倒になりますが・・・。
ドリル径は2.5mmを使い、ネジ頭用のザクリはそれに向く専用のキリを使います。
コースレッドは32mmを主に使っています。

木ネジの頭が出ない様に円錐型に削る刃(ドイトさんで見つけて愛用) 右は普通の2.5mmのドリル
このやり方での、作業効率アップのために、小生は組み立て用に、ドライバー・ドリルを3台同時に使います。
下穴あけ用、ザクリ用、とネジを締めるドライバーの3台の使い分けをするのです。
3台使うと刃やドライバーを、その都度、付け替える時間と手間が短縮でき、早いのです。
最近はAC(家庭電源)の電動ドライバー・ドリルもオークションで1500円くらいですし、充電型のものでも3000円くらいで結構良いのがあるので、3台使っています。
パーツ③~⑥は事前にボンドでくっつけておき、それを②に付け、さらに②に⑦を付けておきます。⑩~⑬も先にボンドで箱状に作っておきます。この時、平らな板の上で組み立てるとL字型の部位や、箱状の部分がネジレ無いで組み立てられ、うまく行きます。
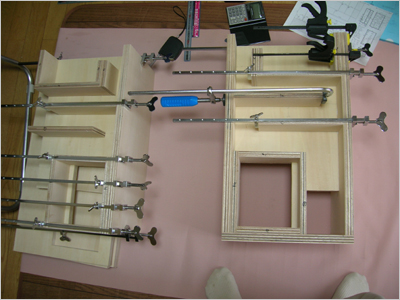
このボンド、裏返しネジ止め・・作業の繰り返しで、前面側の音道は完成します。

表側の音道完成・・コードも通してあります(チョット短くて失敗ですね)
裏面側も基本的に同様ですが、板の貼りあわせがあります。
まず、⑮の上にボンドで⑭を貼っておきます。(しっかり重量を掛け、ズレ無い様に・・コースレッドの25mmを1~2本打っても良いです・・)
それから⑯に⑭と⑮貼り合せたものをつけます。これはボンドとコースレッド32mmの併用でつけます。
その後⑭と⑮のついた⑯にたいして、⑰と⑱をボンドとコースレッド25mmで貼り合わせの要領でつけていきます。
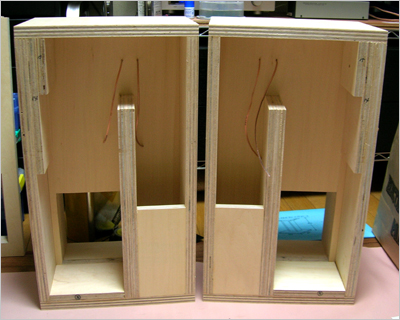
裏側の音道完成・・・結構複雑になっています
このパーツは左右がありますので、同じ作り方で2個作らないようにしませんと、1個が取り付けられなくなります。
左右対称は意外と注意が必要で、やり直しが続発する部分なのです。
一般に板の貼りあわせは、ズレたら困るので、まずボンドを付けずに板同士をきっちり合わせ、下穴をだけ穴あけします。ドリルの刃は板2枚を貫通しない程度に、ドリルからの刃の出方を30mm以下に調節します。
4箇所くらい穴あけしてからボンド付けし、貼りあわせ、ボンドが落ち着いたら、ネジが貫通して飛び出ないようにやや短い25mmの長さのコースレッドで締め付けます。
こうして貼りあわせは「穴が先」「・・それからボンドで接着」「コースレッドを締める」とやると、ズレにくく、うまく行きます。
もちろん穴あけした時の通りに貼り合わせませんと、穴がずれ意味がなくなります。
ボンド付けのとき、部品の裏返しをしないように、貼り合わせる面が分かるマークをしておきます。
裏面のパーツもこれで①に着けられ、音道の概要が完成します。
そうしましたら、後は組み立て順どおりに、その他のパーツを取り付けていきます。
5.組み立て・・・配線
前面のバッフル板と後面の板を取り付ける前に、スピーカーのコードを通し、端子を装着する準備をしませんと、後からでは取り付け不可能になりますので、段取りを忘れないように、あせらずじっくりやる必要があります。
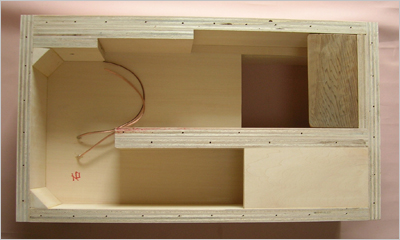
コードの長さも重要なポイントです。十分な余裕を見て、後ろの端子の穴から出る部分が
30cm以上とたっぷりにしておきます。
前のバッフル板からも40cm以上の余裕を見ます。長い分には後で切れますから・・・。
特に前面はコードの長さに余裕があると、スピーカーユニットの取り付け、半田付けなどの時に、スピーカーユニットを箱(エンクロージャー)の上に乗せて作業が出来ます。
この余裕が45cmくらいなのです。
本体25cm、後ろ30cm、前45cmでで、トータル100cmです。意外に長いですね。余り過ぎたら、後で切ってください。
①に直径4mmくらいのコードの通る穴を2箇所あけ、スピーカーのコードのプラスとマイナスを通しエポキシ系ボンドで穴をふさぎます。
想定するコードの接着位置にマジックなどで印をしてからコードを板の厚み分の15mm程、引き出して、その出した部分の周囲全体にボンドを塗り、印までコードを戻すと、穴の中までボンドが行き渡ります。
コードを回転させて、ボンドを馴染ませるのも良いと思います
なぜエポキシボンドかと言いますと、穴の奥まで固めるためなのです。
溶剤系で乾燥させるタイプのボンドを使用すると、空気の入らない奥の方が固まらず液状のままになってしまうのです。
その点、エポキシ系のボンドはA・B、2液の反応で固まるタイプであり、空気・乾燥を必要としないので、穴の中の奥でもきちんと固まるのです。
配線後に後面の板をつけるとき、事前に端子用の穴・・大体10mmの穴を二つ・・開けておきます。そして後面の板にはコースレッドを締めるための穴を開ける位置に、鉛筆で線を入れておきます。
この状態で本体側に木工ボンド(速乾ではない普通の)をつけて、後面の板の端子の穴にコード2本を通し、先を軽く結んで!!抜けないようにし、接着します。
6.組み立て・・・後面とバッフル~開口部の三角材
後面の板がズレが無いように角を決め、コースレッドをまず四隅に打ちます。
ボンドが落ち着いてきたら、5cmおきくらいにドンドン下穴をあけ、ザクリ、コースレッドをねじ込みます。
はみ出た木工ボンドは水溶性ですから、ぬれ雑巾でマメにドンドンふき取っておきます。
開口部の後ろ半分の部分に(24)をつけておきます。(24)の上には三角材がきます。
三角材は一辺が8cmくらいの角材を斜めに半分に切ったものを使います。
三角材は開口部へ低音を押し出すために大変有効なパーツのようです。

茶色く見えるのが一辺8cmくらいの角材から切り出した三角材
長岡先生の設計では使われておりませんが、準備される事をお薦めします。
小生は1辺が8cmくらいの角材を手のこで(のこぎりで)斜めに裂いて使っています。これは「のこぎり」の縦刃(たてば)で無いと、うまく切れませんので、両刃の「のこぎり」がぜひ必要です。
これを鋸で切るのはかなり難しいですがホームセンターなどでは斜めのカットはやってくれませんので、練習してコツを体得してからやる以外に方法は無いようです。
音道の途中には高音吸収用のフエルトを貼る・・・という工程もあります。
①の前後の音道を連絡する穴、95mm×90mmの部分の下に、薄い1~2mm厚くらいのフエルトを木工ボンドで貼っておきます。
そして、最後に前面バッフルの装着で、組み立て終了です。
本体側の板に木工ボンドを付け前面バッフル板を貼ります。この時、コースレッドを使う方法と、仕上げを気にしてボンドのみで行う場合があります。
ボンドのみでの固定には、ハタ金という本体を挟んで締めつけておく工具が6本とか8本とか必要になります。(1本1,500円くらいしますので、あまり使わない方にはもったいない工具ですが)

表に傷が入らないように、捨てるベニアの切れ端などを挟んで締めます。ガチガチ!!
ハタ金を使わずコースレッドで組む場合は、ネジの頭をパテなどで隠す工程が必要になります。
その場合は、ネジの頭を隠したパテ跡が目立ちますから、木目を活かした自然な塗装・・生地仕上げ・・・などは出来なくなりますので、黒など不透明の濃色のペイント仕上げが通常になります。
小生も黒で仕上げるならネジを打ちますし、木目で行くならボンド・ハタ金です。
7.仕上げなど・・。
これで組み立ては完了ですが、塗装など、仕上げが待っています。
仕上げは個々の趣味ですが、小生はこのスピーカーでは、前面バッフルをボンドで取り付けて木目を活かす作りとしましたので、「メープル」カラーの油性オイルステインで全体を塗りました。
ところが、実際は、不幸にもシナベニヤが、表面に部分的に油分を含んでおり、オイルステインを塗ってもこれを弾いてしまい、大きなムラ染めが発生し、何度やってもダメでした。
で、結局この塗装の修復が不能と諦め、本物のメープルの「つき板」を購入し、熱で貼る(アイロンで貼っていく、熱で解けるボンドがついていました)事になりました。
これは難しい作業で、時間を要しました・・・。やり直しが何回も必要で・・・。


つき板を貼る前に、ムラになった濃い目の塗装です・・やり直し前の状態です。
長岡先生オリジナルのD-99(黒色)とのサイズの比較が出来ます。
一回り大きくなっています・・。[台はD-99用の(赤)にとりあえず載せています。]
この「つき板」は正面、天板、左右、の4面仕上げにしました。
それから、やっとメープルのつき板に対してオイルステイン塗装の再登場です。
今度はちゃんと綺麗に染まりました。
ステイン塗装は刷毛で塗ったら、すぐにボロ布でふき取り、ムラにしない・・という塗装方法です。
ステインの乾燥後、その上から透明の2液性ウレタン塗料のクリアをガン吹き塗装をしました。3回重ねて吹いて、コンパウンドで磨いて仕上げます。
コンパウンドは自動車補修用の中目~細目くらいを使用しています。
磨くとピカピカ・艶々です。
このクリアもそうですが、ウレタン塗料はいつも「おもしろ塗装工房」さんで通販で買っています。
http://www.tosou-ya.comをご覧ください。
2液性のウレタン塗装は、高級家具の様なフィニッシュになります。
完成するととても綺麗です。
8.完成
いよいよ・・・試聴です。

左上がBS-28改、左下がD-99ES-R、右がD-37ES・MAKIZOU版です。
こうして見ますと、スピーカーが多すぎです・・・。
かなり期待通りの音がしました。
まっすぐで繊細。
ハイスピードで音が飛んできます。
エージングもしていないのに、のっけから凄く良い音なのはD-99の時と同じです。
8.5cmとは思えない低音の豊かさに、最高40khzまでの高音の抜け。
スッキリしています。
D-99を上下に周波数を拡大した・・・性能と言う感じです。
リー・リトナーのエレガットの抜けも最高に気持ちが良いです。
女性ボーカルも申し分ありません。エラ・フィッツジェラルドさんのマックザナイフが生き生きしています。
コントラバスの低音も問題なしです。チェコフィルの2人のデュオ・ディ・バッソのチェロとコントラバスが、とんでもない凄い音になって飛んできます。
一方、弱点も露見しました。
大音量時に低音のパルス的な短い音、バスドラムとか・・・、これがモコモコ、ボコボコします。
ユニットのコーン紙が大きく前後に動いていますが、さすがに8.5cmの限界があるのでしょうね。潰れた低音と言う感じになります。低音のパルス・・には弱い様です。
もっと頑張るなら、もう100cc程、木のかたまり等の何かを入れて、空気室を小さくしてみたり、スロートに薄いベニヤを貼って2mmくらい絞ってみたり・・・という実験もして見たくなります。
しかし・・音が良いので欲が出ますが、大音量時の限界はありますですね。
優秀でも口径8.5cmは8.5cmと言うことでしょうか・・。
このスピーカー(初期設計版・・)には、少々後日談があります。
これを聴きに来た友人が、僕も作ると言い出したのです。
彼は昔、小生のスーパースワンを聴きに来て、これに感動し、初心者ながら制作にチャレンジして、1年がかりでものにした・・ツワモノ・・・でクラシック好きなのですが・・・。
今回も「気に入ってしまった。どうしても作る」・・となったのです。
彼は図面を持ち帰り、勇敢にチャレンジし、これを作っているようです。
さらに、彼の義理のお兄さんまでが、同じモノを作られたとの事です。
義兄さんも音質の良さに相当驚かれ、ご友人を招いては口径8.5cmとは思えぬ低音をお見舞いし、カルチャーショックを与えているそうです。
ともあれ、とても満足され、大変気に入っておられるとの事で、小生も嬉しくてたまらないお話しでした。
それから、図面にもありますが、この茶色の台は相当苦労して作っています。
柱の部分の中に乾燥させた砂を充填しているのはD-99と同じです。
根気と根性だけは必要な台ですねー、これは。
で結局、この小生のACEスピーカーのD-99ES-Rが今どうしているか?ですが、これは非常に気に入り、仕上げにも相当拘ったものでしたが、お世話になっている方のお宅にお譲りいたしました。
今までの全部がそうですが、良いものだと思ったからこそ、お知り合いの方にお譲りしています。
このES-Rは大田区方面で活躍中です。オペラなどのソフトの再生に大忙しと聴いています。
で、小生は次の興味へ・・・。
設計の変更や仮説の検証がしたくなって、次を作るのです。
次回はまた、小生が大変気に入った、この同じユニットを使用します。
FE88ES-R用のスリムなトールボーイバックロードです。
これは最近作ったばかりの機種です。
これも完全に自分の書いた図面ですから、皆さんに公開出来ますので・・・。
出来れば多少ご期待いただけると、やる気が出るのですが・・・。
※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。
耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。
有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。
松任谷由実さんの曲
「松任谷由実さんの曲」
今まで、なかなか人に話していないのですが、小生、自分達の世代の・・・同時代を生きるアーティスト・・・松任谷由実さんの「隠れ大ファン」なのです・・・。
松任谷由実さんは、確か小生の1歳年上で、学年は二つ上だったと思います。
あまりにもポピュラーと言うか、この人の曲を好きだと言うと、男のくせに女々しいと思われるのでは?とか、色々考えすぎもし、さらに、なぜか多少の気恥ずかしさも有り、この件あまり言っていませんでした。
・・・ですが、松任谷由実さんの曲が、大好きなんですねー。
アルバムもアナログレコードの時代に、レンタルしてカセットにコピーしたモノを殆ど持っていたのです。
このカセット!気合の入ったメタルテープにドルビーBを掛けてダビングしていました。
メタルテープです!!・・・カセットでは、気合いの「よそ行き」・「一張羅」のメタルを投入していた特別なアーティストさんが松任谷由実さんなのです。
もちろんレコードもかなり持っていました。
もともとの松任谷由実さんの曲との出会いは、当時の年下の女子の友人に・・「凄く良いから聴いてみてよ・・」とレコードを借りた事がキッカケでした。確か、「コバルトアワー」と「14番目の月」・・と言うアルバムを貸してくれたのです。
一発で嵌りました。
・・・買いました。この2枚から・・・。
で次に数ヶ月掛けて1枚目と2枚目の「ひこうき雲」と「ミスリム」を買いました。
いきなりレコード4枚を手に入れたわけですが、当時ですから、小生も浪人から大学1年の頃で、お金がなくて・・・、レコードは安いものではありませんでしたが、だんだんに買っていったのです。
そこには「歌謡曲」とは違う、なにか新鮮なセンスが溢れていました・・・。
演奏では、バックの方も今にして思えば、大変な大御所の方たちのようで、細野晴臣さんとかが支えていたようです。凄いです。
『シンガーソングライター』・・・新鮮な響きでした。
へえ、自分で詩も曲も作って、しかも歌うんだ・・・と驚いたものです。
松任谷さん・・いや旧姓の荒井由実さんは、何と言っても小生に、最初に『詩』というものを意識させてくれたアーティストなのです。
『詩』が良いのです。荒井由実さんは・・・。
言葉の選択、響きの選択、これがとっても良いのです。
それと由実さんの声の質・・・。
たまらなく切ないというか、品が良いというか・・。
油性でこってりと歌い上げる歌唱では無いのですが、心に強く残るし、飽きない歌声・・。
『ザ・透明感』とでも言うのでしょうか・・・。
当時小生は、全く勝手に、荒井由実さんのイメージを決めていました。
「深窓の令嬢歌手」・・・良いお家・・に育った、凄いお嬢さんのシンガーソングライター・・・と決めていたのです。
だって、ピアノが弾けて、美術の大学に通ってて、曲を書いて、歌うんですよ!!
こう言う才能が育まれる環境は・・「ええとこのお嬢」・・ですから。
声も好き、詩も好き、曲も良い・・・でした。
ビックリしたのです。
海を見ていた午後・・では「ソーダ水の中を貨物船が通る」・・・んです。
情景描写なんですね・・高度に現代の流行などを使いつつ、実は感情まで表現した・・・。
「サーフボード直しに、ゴッデス(GODDESS)まで行くと言った」・・・んです。
「茅ヶ崎までの間、あなただけを思っていた」んですから・・。
じゃあ茅ヶ崎を過ぎたら他の人を思うのか?って突っ込んではだめで、そう言うタイミングや気分がきっと素直なんだなって・・・、そう言う理解を・・・。
格好良いというか、当時の旬と言うか、チョットだけミーハーと言うか・・。軽さもあるし・・・。
でも、確実に時代の気分を写し取っている情景描写に感情が緻密に織り込まれているのです。
難しくないし、すーっと心に入ってくるし、でもかなり心に響く、残る表現だし・・・。
巧みです。
本当に、当時の同世代の人の気分や・・・当時の若者が憧れるような人たちの姿・・ライフスタイル等を表現していた・・と思っています・・・。
現実の小生は、サーファーでもないし、サーフボードも車も無いし、ダサいし、もてない奴でしたから・・・。
とりあえず法学部に通ってて、志もなくて、スキーだけ大好きで、バイト漬けで・・・。
こうして松任谷さんに若い時に共感?して以来、その後30歳でも、40歳でも松任谷さんが好きでずーっと来ています。
こういう人、実は結構多いんじゃ?と思います。
小生の「青春の音楽」が、松任谷さんなんだ!と一番自覚したのは、30歳くらいの頃、人生の転機があった時でした。
色々生き方が下手で、回りにも迷惑をかけ、ノイローゼにもなり、かなり落ち込んで職も辞して、転勤先から東京に逃げ帰るように戻る時、新幹線の中で聴いていたのは、ウォークマンに入れたユーミンのカセットでした・・・。
海を見ていた午後・・とか聞きながら東京・・・つまり故郷に帰ってきたのでした。
本当に落ちてました・・・あの時。
そう言う時に聞きたいと思うんですから、やはり何か心が求めるものが・・・あるんですね。そう思います。
透明感・・・。素直さ・・・。
特に初期の荒井由実さんは、聞いていた当時の自分の年齢・感受性の影響もあって最高!最高!なのです。
それから、そうそう、彼女の歌で学んだ事も多かったですね・・・。
真珠のピアス・・・なんて『詩』に驚きます。
ベッドの下にワザと片方捨てた真珠のピアス・・を新しい彼女と発見するだろうって詩です。
たまげました・・・。そう言う子は殆ど存在しないでしょうが・・・。でもあり得るし・・。
他にも沢山あるから名曲をあげたらキリが無いのですが、気になる度に更新すると言う事で・・・。
例えば、
『さざなみ』・・・これは曲として、最高で、僕にとっては「ザ・ユーミン」です。
本当にセンスの良い曲です。曲のテンポ、メロディー、歌詞、すべて松任谷さんで無いと出来ない曲では・・・と思います。
『中央フリーウェイ』・・高速道を扱ってドライブものの曲はもう出てこないのではと言う決定的な曲・・・。調布基地を追い越し、山に向かっていけば、たそがれがフロントグラスを染めて広がる・・・。・・・右に見える競馬場、左はビール工場・・・情景の描写が自分のドライブ時に再現する・・・シミュレーションなんです。
愛してるって言っても聞こえない風が強くて・・・これはオープンカーですね。
本当に優れた曲だと思います。いまでも中央道通る時は聞きたいし・・・。
『14番目の月』・・詩のインパクト・・・次の夜から欠ける満月より14番目の月が好き・・考えたものだ・・・最高の手前の感覚・・・女性らしいなあと思いましたね・・。
またまた、だんだん紹介しますね・・。
それから、レコードなどはどうなったかですが、CDの時代が来てしまい、もうレコードはダメだな・・と誤解してこれらを処分し、CDをそこそこ買いました。
音楽フォーマットの変遷の被害者・・・。大げさですね。
現在ではCDも殆ど買ってますし、アナログも結構買いました。
かつて金が無くて買えなかったのですが、今はオークションなどを利用して安価に揃えて行けますから・・・。
残念なのは高音質のSACDが一枚も無いことです・・・。
松任谷由実さんの仕事が、デジタルでは、圧縮やサンプリングで「切られた物」しか存在しない・・・。
これは「悔しい気持ち」ですね。良い仕事はそのまま記録して欲しいですね。
全作品をSACDにして欲しいです。
もし、SACDがあったら、時間を掛けて根性で揃えていきますね・・・きっと。
スピーカーの自作 しょの3
「スピーカーの自作 しょの3」
いよいよシリーズ第3弾『しょの3』です。
いよいよって言っても、これまた期待されていないですよねー・・。
今回はスピーカーの自作「偏」の3回目。
前回までに、
①D-101S(スーパースワン)です。
②D-37(16cm、FE168SS用 CW型)
③D-102(10cm、FE108Σ用 ブックシェルフ型)と
きましたが、
今回は④D-99(エイトマン・・8cm、FE88ES用 ブックシェルフ型)
の話を書きます。

頭のDは故長岡先生がバックロードホーンにつけた命名の・・確か「ダイナロード」だった?・・・の略の「D」だと思います。
先生が、かつて、どこかのスピーカーのメーカーさんの依頼で、バックロードのスピーカーシステムのネーミングを頼まれて考えた商標・・だったように?思います。(確か何かの理由で使われなかった名称で、それが権利を取れたかどうか?など詳細はウル覚えですが・・・)
このダイナロード・・・略してD、・・先生設計のバックロード方式のスピーカーの型番の頭・・に使われています。
では・・・。
口径8cmのD-99です。
ブックシェルフ型バックロードホーンD-99(エイトマン)。
これも長岡先生がご逝去後に、追悼特集の雑誌、不思議の国の長岡鉄男①・・で製作記事を見て、興味を持ちまして、制作する事にしたスピーカーです。
先生の図面の通りに作り、アレンジは開口部の奥の三角の材料と、その下の部分に板の補強用でベニヤを追加したのみ・・・が変更点です。
もともと、この手の形のスピーカー制作では、D-102の制作経験もありましたが、ホーン開口が前面で、低音を前に出すタイプのブックシェルフ形のバックロードホーンは好きでした。
ユニットも小さな口径で25khz以上まで伸びていると言われる、このFE-88ESと言うユニットを使用します。
これはツイーターも不要なので、相当音も良さそうに仕上がると感じられ、かなり気になりました。
このユニットの購入は、たまたま秋葉原のコイズミ無線さんにフラッと立ち寄った時に、偶然見つけました。で、制作とか設計の目的があったわけでは無いのですが、「限定ユニットは買っておくべき」・・と言う発想で、小型ゆえお値段もそこそこでしたし、お小遣いで「買い置き」してありました・・。
長岡先生は、かねてから雑誌の記事で、D-102は珍しいブックシェルフ型のバックロードホーンで、大変完成度が高いので、なかなかその後の発展が出来ない・・・と言うような主旨のことを言っておられました。
ですので、原型のD-102は小生が10年ほど前に作った時点より、さらに相当以前の設計で、古い作品だと思いますが、その後の改善版などの発表が無いので、皆さん新しいユニットを使用するケースでも、これを土台にして作っていたようでした。
そういう状況の中、今回は新しいFE88ESユニットの発売を期に、雑誌社などから、このユニットを使った新機種の設計を多数依頼されて、やることにした・・・的な経緯が書いてありました。
小生にとっては長岡先生の久しぶりのブックシェルフ型バックロードです。なんと嬉しいことか!!ですねえ。
小生はD-102の時に「この設計は天才的だなあ」と言う感覚があり、是非また新しいユニットで・・この類で、新しい違うのを作りたい!!と思っていたので、限定発売のFE88ESという口径わずか8cmでも大変強力なバックロードホーン用のユニットを使うこのD-99は、『作ってみたい工作』・・の最右翼になりました。
先生はこのスピーカーD-99を発表した製作記事中で、「超ハイCP機」「誰もが納得の高音質」と言ってらっしゃいましたし、制作当日同席した一般読者参加の試聴会で、これが欲しい・・持って帰りたい・・と言う人が出てきて編集部が慌てた・・・というくだりも在って、なおの事、作りたいと思ったのでした。
{CPはコストパフォーマンスの事です。・・・価格対性能比・・ハイCPは価格が安くて性能が良いということです・・・。}
小生は図面上の素人判断からでも、このD-99を直感的に「良い」と感じていました。
と言うのは、つまらない経験からの自己流解釈なんですが、以前のD-102では開口部の高さが低く、潰れた横長の形の穴であり、それがこのスピーカーの低音が出にくい原因か・・とも素人的に考えた事があるのです。
先生ご自身も「本当は開口部をもっと大きくしたかったのだが・・・」的に、何かの原稿で書かれていましたし・・・。
で、その開口部の大型化という視点で、今回のD-99を見ますと、開口部は平たいどころか「縦長」で大きいのです。
小生は勝手に、今回は開口部の形や補強など、D-102で残った課題を解決しているのだな・・などと一人悦にいったものです。まるで、先生と会話をしている気分でした。
ということで、この小型で可愛いD-99の工作なのです。(今回からは、比較的最近の製作ですから、結構デジカメの写真もありますし・・・)
1.板材の手配
板は15mm厚のシナベニヤをドイトさんで購入し、カットを依頼しました。
もちろん直線カットのみで、丸いスピーカーの穴あけや、四角い開口部の穴は自分のドリルとジグソーで開けます。
2.パーツ確認と下準備
パーツをそろえて過不足を確認し、組み立ての開始です。
まずは、寸法の確認です。
音道構成パーツは前面側はすべて幅70mmで、後ろ側は100mmです。
平らな板の上ですべてのパーツを背比べするようにきっちりくっつけて揃えて見ると、狂いがある物が出っ張ったりします。この段階で出っ張るパーツにカンナを掛けたり、ヤスリで削ったりして直します。
これは後々、組み立てが楽になるコツみたいなものです。
事前の準備としては、さらにフロントバッフル板に、裏側からスピーカーの取り付け用の爪つきナットを打ち込んで、つけておきます。
この程度のサイズのユニットでは取り付けるネジは4mmです。従って爪つきナットも4mmです。
そうしますと、この爪つきナットの外形が5.5mmくらいですから、穴は5.5mmの穴となります。穴の位置は図面的にも割り出しますが、早いのは現物での確認です。
穴の中心を出すためには、穴を開けて切り離した丸い不要な部分を中心に戻し入れて、中心からネジまでの距離をコンパスで墨付けしてから、丸い部分を外し、穴にユニットを置いて、ユニットの取り付け用の穴にコンパスの鉛筆の線が見える範囲で、キリでチョットだけ穴を開けると安心です。
・・・この方法ですとユニットがバッフルの穴に対して、左右などに偏ってしまいませんし、寸法のミスも現物で確認可能で安全です・・。
3.組み立て・・音道
長岡氏の図面のパーツの番号で、前後を分ける①のパーツが組み立ての要です。このパーツの上に音道を構成をするパーツ②~⑨を並べて、こんな感じに取り付けるのだなと、まずは、あたりをつけます。
①の板には図面どおりの寸法で、取り付けるパーツの線を、鉛筆でライン書きして入れておきます。
そうしましたら、いよいよパーツに木工ボンドを付けて、板に描いた線に合わせて貼り付けます。
体重をかけ3分~くらい押し付けていますと、速乾の木工ボンドも落ち着きまして、一瞬板を裏返す間くらいは剥がれず、ズレず、にいてくれます。
このズレない程度の状態が重要です。
そこで裏返して、裏からドリルでネジ用の下穴を開け、ネジの頭が出っ張らずに入り込むようなザクリもやってから、コースレッドと言う細身の木ネジを捻じ込みます。
ネジの間隔は適当です・・。
狭くて5cmから、広くて10cmくらいでネジを打ちます。
小生の場合、組み立てには釘は使いません。
コースレッド(木ネジ)は下穴など面倒ですが、強力に締め付けられますから、釘より強度抜群になるのです。
もっとも面倒がって直径2.5mmの下穴をきちんと開けませんと、板がネジに押し広げられて割れる事がありますから、工作は楽ではありませんが・・・。
ドリル径は2.5mmを使い、ネジ頭が出っ張らないように円錐型の穴を開ける・・・ザクリは・・・それに向く専用のキリを使います。
コースレッドは32mmを主に使っています。
写真をご参照くださいませ。
このやり方で、作業効率アップのために、小生は組み立て時はドライバー・ドリルを3台同時に使います。
下穴あけ用、ザクリ用、とネジを締めるドライバーの3台です。
3台使うと刃やドライバーを、その都度付け替える時間が短縮でき、早いです。
最近はAC(家庭電源)の電動ドライバー・ドリルもオークションで1500円くらいですし、充電型のものでも3000円くらいで結構良いのがあるので、3台使っています。
このボンド、裏返しネジ止め・・作業の繰り返しで、前面側の音道は完成します。(写真)
裏面側も基本的に同様ですが、板の貼りあわせがあります。
板の貼りあわせは、ズレたら困るので、まずボンドを付けずに板同士をきっちり合わせ、下穴をだけ穴あけします。ドリルの刃が板2枚を貫通しないように、ドリルからの刃の出方を30mm以下に調節します。
4箇所くらい穴あけしてからボンド付けし、貼りあわせ、5分くらいでボンドが落ち着いたら、ネジが貫通して飛び出ないようにやや短い25mmの長さのコースレッドで締め付けます。
こうして貼りあわせは「穴が先」「・・それからボンドで接着」「コースレッドを締める」とやると、うまく行きます。
もちろん穴あけした時の通りに貼り合わせませんと、穴がずれ意味がなくなります。
ボンド付けのとき、部品の裏返しをしないように上が分かるマークをしておきます。
裏面のパーツもこれで①に着けられ、音道の概要が完成します。
そうしましたら、後は組み立て順どおりに、その他のパーツを取り付けていきます。
4.組み立て・・・配線
前面のバッフル板と後面の板を取り付ける前に、スピーカーのコードを通し、端子を装着する準備をしませんと、後からでは取り付け不可能になりますので、段取りを忘れないように、あせらずじっくりやる必要があります。

コードの長さも重要なポイントです。十分な余裕を見て、後ろの端子の穴から出る部分が
30cm以上とたっぷりにしておきます。
前のバッフル板からも40cm以上の余裕を見ます。長い分には後で切れますから・・・。
特に前面はコードの長さに余裕があると、スピーカーユニットの取り付け、半田付けなどの時に、スピーカーユニットを箱(エンクロージャー)の上に乗せて作業が出来ます。
この余裕が45cmくらいなのです。
本体25cm、後ろ30cm、前45cmでで、トータル100cmです。意外に長いですね。余り過ぎたら、後で切ってください。(写真ではコードが短くて失敗し、後からやり直しています)
①に直径4mmくらいのコードの通る穴を2箇所あけ、スピーカーのコードのプラスとマイナスを通しエポキシ系ボンドで穴をふさぎます。
想定するコードの接着位置にマジックなどで印をしてからコードを板の厚み分の15mm程、引き出して、その出した部分の周囲全体にボンドを塗り、印までコードを戻すと、穴の中までボンドが行き渡ります。
コードを回してボンドを馴染ませるのも良いと思います
なぜエポキシボンドかと言いますと、穴の奥まで固めるためなのです。
溶剤系で乾燥させるタイプのボンドを使用すると、空気の入らない奥の方が固まらず液状のままになってしまうのです。
その点、エポキシ系のボンドはA・B、2液の反応で固まるタイプであり、空気・乾燥を必要としないので、穴の中の奥でもきちんと固まるのです。
配線後に後面の板をつけるとき、事前に端子用の穴・・大体10mmの穴を二つ・・開けておきます。そして後面の板にはコースレッドを締めるための穴を開ける位置に、鉛筆で線を入れておきます。
この状態で本体側に木工ボンド(速乾ではない普通の)をつけて、後面の板の端子の穴にコード2本を通し、先を軽く結んで抜けないようにし、接着します。

5.組み立て・・・後面とバッフル~開口部の三角材
後面の板がズレが無いように角を決め、コースレッドをまず四隅に打ちます。
ボンドが落ち着いてきたら、5cmおきくらいにドンドン下穴をあけザクリ、コースレッドを打ち込みます。
はみ出た木工ボンドは水溶性ですから、ぬれ雑巾でドンドンふき取っておきます。
オリジナルの図面では、開口部の後ろ半分の下側に板がありませんが、これは追加でベニヤ1枚を補強に加えるべきと思います。
断裁したときの余りのベニヤ板から切りだして、ボンドと裏からのコースレッドでしっかり固定し、その上に三角材をつけます。

三角材は開口部へ低音を押し出すために大変有効なようです。
小生は大きな柱の様な、一辺が8cmくらいの角材を手のこで(のこぎりで)斜めに裂いて使います。これは「のこぎり」の縦刃(たてば)で無いと切れませんので、両刃の「のこぎり」がぜひ必要です。
これを鋸で切るのはかなり難しいですがホームセンターなどではやってくれませんので、練習してこつを体得してやる以外無いようです。
音道の途中には高音吸収のフエルトを貼ったりという工程もあります。
そして、最後に前面バッフルの装着で、組み立て終了です。
6.仕上げなど・・。
これで組み立ては完了ですが、塗装などの仕上げが待っています。
仕上げは個々の趣味ですが、小生はこのスピーカーでは、「との粉」を水3、木工ボンド1くらいの割合で溶いて塗って目止めをし、軽く400番のサンドペーパーでサンディングし、その上から2液性のウレタンエナメル塗装(ブラック)をしています。
塗料はいつも「おもしろ塗装工房」さんで買っています。
http://www.tosou-ya.comをご覧ください。
2液性のウレタン塗装は、ピアノの様なフィニッシュになります。
完成すると強くて綺麗です。
(塗装工程も色々ありまして相当長くなりますので、今回はこのくらいで・・)

7.完成
いよいよ・・・試聴です。
実際は塗装の前に仮にスピーカーをつないで音出しをしてみたのですが、まずボーカルが良くて、ビックリしました。
全般に音は抜けが良く、スピード感も相当良いものでした。
8cmとは思えない低音の豊かさに、持ち前の高音の抜け。
凄い性能にニコニコ笑いが出てしまう・・・そう言う感じなのでした。
エージングもしていないのに、のっけから凄く良い音で驚きました。
FOSTEXさんの新世代のユニットなのだなあ・・と思いました。
凄いです。
これは、スーパースワンに負けていませんでした。
いや、掛ける曲によっては、上回っていたかもしれない・・くらいでした。
このスピーカーは、軽くて小さいので、結構その後、色々と楽しい事をやりました。
某会社、社長様のオフィスで他流試合もやりました。
相手は先方様の会議室に設置されている名機J○×の、30cmウーファーの3ウェイ。
音質の優劣は、好みの問題もありますので、置くといたしまして、
しかし、それでも社長様、大変驚いておられました。
これがわずか直径8cmのスピーカーからの低音か?!・・・と。
このD-99はその後、あるお友達に大変気に入られ、オレンジ色の台と共に、横浜方面に嫁いでいきました。
かなり気に入ってくださいまして、大事にされているようです。
このオレンジ色の台は相当苦労して作っています。
柱の部分の中に乾燥させた砂を充填しています。
砂の乾燥は、屋外で古い中華鍋に砂を入れ、キャンプ用のコンロの上で砂を炒るのです。
かなり大量の砂を必要としますから、鍋で砂を炒って、新聞紙の上で冷まし、を何回も繰り返しやるのです。
これは相当、根気が要りますが、重量もあって良い台になります。
D-99は、確かに「超ハイCP」の素晴らしいスピーカーでした。
次回は新ユニット用のD-99ESRです。
これは自分の書いた図面ですから、皆さんに公開出来ます。
※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。
耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。
有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。
スピーカーの自作 しょの2
「スピーカーの自作 しょの2」
1本作ると悪乗りして・・・2本目・3本目も・・・と言いますのが、この『しょの2』以降の話です。
今回はスピーカーの自作「偏」の2回目です。(笑)

何しろ自作の趣味は、置き場所も無いのにドンドン台数が増えますから・・・(笑)
スーパースワンの好結果で味をしめて・・・制作して半年くらいから、もう次の作るものを物色し始めていました。
スーパースワンがこんなに良いんだから、長岡先生の設計の然るべき2作目を選択し、それを作って、「2台をスイッチで切り替えて、それぞれの違い」を楽しもう!!等と調子に乗りましたのです。
自作の結果が良いと、「聴くために作る」と言うより、だんだん「作るために作る」と言う調子で、作る事自体が楽しくて、「目的」になって・・行きます。
困ったものです・・。
長岡先生のスピーカー制作関係の本も、この頃では、数冊持っており、熟読していました(笑)。
当時、小生はオーディオにまた目覚め、雑誌も定期購読し始めていました。
月刊ステレオ(音楽の友社)です。
この雑誌には、長岡先生が新作スピーカーを考案されると、そのかなりの部分を発表していました。
特に毎年7月号のクラフト(手作り)の特集では、何作も設計され、成果を出されていました。
D-37・・・という、少々大型のバックロードホーンスピーカー。
FOSTEXさんの、口径16cmの限定ユニットを使用したこのスピーカーが、当時の小生の憧れになっていました。
超強力型バックロードホーン用ユニットを入れた、CW型バックロードホーン。
CW型とはコンスタント・ワイズ型のこと・・・幅が一定で高さ方向が変わる事でだんだんに音道が大きく広がってラッパ状になっているタイプのこと・・・。
ちなみにスーパースワンの音道は、幅も高さも途中でドンドン変わりながら拡大してくるのでCW型ではないですね・・・。
2作目にしては、このスピーカーは大変大物ですが、これを作ろうと決心しました。
ユニットはFE-168SSと言うユニットです。
口径は型番どおり16cmですが、マグネットはなんと2枚重ねで超・超・強力です。
このユニットではコーン紙を強力な磁石が引っ張っているので、(こう言うユニットを「オーバーダンピング」のユニット・・ダンピングし過ぎ・・・と言うようです)コーン紙が軽くは動かないので、普通のバスレフなどの箱に入れても低音不足のひどい音になる・・と言われるユニットです。
しかしバックロードホーンで、設計がうまくピッタリ合いますと、ハイスピードで締まった(豊かな)凄いリアリティーの低音が出てきます。
凄い・凄い、鳴らすのも難しい、手強い強力なスピーカー・ユニットなのです。
チャレンジを開始しました。
板材はまたFOSTEXさんのカット材を利用しました。
このカット済みの材料はお高いですが、カットの精度が良いという事で・・当時はこれを利用していました。(最近は有名な広島のMAKIZOUさんにカットをお願いしています)
このスピーカーは出来る限りの丁寧さで組み立てました。
ユニットの取付けには、開口部のネジ穴部に裏側から「つめ付きナット」と言うのを打ち込んで、表からのネジ止めを可能にし、緩んでボロボロになりやすい不安定な木ネジでスピーカー・ユニットを固定しないようにしました。
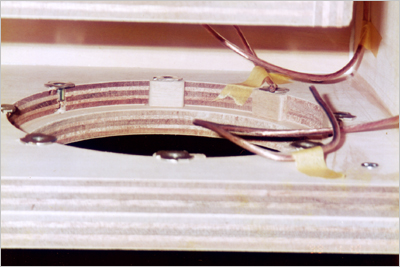
木ネジは木の繊維をネジの螺旋が押しのける分だけの力で効くものですから、金属と木の摩擦の力が限界です。
しかし、金属のネジとつめ付きナットの場合は、文字通り金属のネジ同士の締め込みになるので万全です。
また、木ネジによるユニット取り付けでは、その後の調整などでユニット交換をしたり、2回3回とユニットの着け外しをしますと、ネジ穴が大きくなって、ユルユルのバカになってしまいます。
この工作では、組み立てた音道の直角のカーブや、180度の折り返し部には、外側に三角の板材を付け、音が反射してスムーズに音道を進むようにしました。
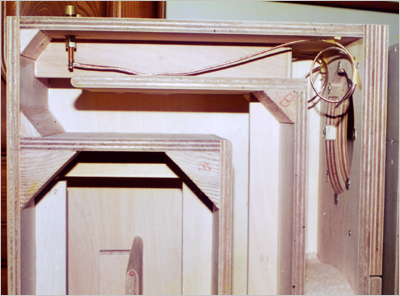
この加工は長岡先生の設計制作レポートには無いやり方です。
先生はそこまで丁寧な事はしないで制作し、性能を測定しています。
何でか?を考えたのですが、長岡先生は、このスピーカー制作で、誰がやっても同じ事ができるように、結果が近づくように、再現性が高いように、板の材料は普通のシナベニヤで作るし、三角材によるスムーズな音道作り・・・の様な難しい加工などをやらないのです。・・・これは本当に見識ですね・・・。
それで変わったモノを選んだり、難しい加工などをしていないのです。
で、実際のバックロードホーンでもこの三角材の効用は諸説ありまして、小生には良いのかどうか、分かりません。
低音の豊かさのためには、かえって、こう言う凝った三角材の工作・配慮をしない方が良いという話もありますので、大変微妙です。
三角材のコーナーの効用は精神安定だけに効果的という方もいるようですから・・・。
まあ、やらないよりはやった方が良さそうだ・・くらいでしょうか。
でも、やるとなると、こう言う加工は本当に根気が要ります。
色々な太さの角材を買ってきて、それを長手方向に斜めに割いて使うのですから・・・。
角材の斜めのカットはDIYのお店では、機械で出来ないので、引き受けてくれませんので、自分の手で鋸で切ることになります。
これはなかなか難しいし、体力的にも結構大変です。
足の裏で角材を踏んで固定して、鋸のたて引きの刃で切ります。
音道を形作るパーツごとに、丁寧に木工ボンドと木ネジで組み立て、それらを組み合わせて側面の板に固定するのですが、その側板への固定には、音道の5cmおきくらいにコースレッドという細身で板の割れ難い木ネジで、パーツを固定するのです。

これで、「箱」はコースレッドでガチガチに締め上げられて、大変強固なものになっているはずです。
素人の工作では、やはり木工ボンドとコースレッドの使用が強度を決めると思います。
強いのは釘よりネジ・・ですね。(しかも接合面は木工ボンドで固めていますから・・。)
当時はまだ2作目で、
①段取りが悪い。なにかと要領が悪い。
②失敗しないように過剰に丁寧で三角材などに拘りすぎ
③仕上げにカシューという乾燥時間が掛かる人工の漆塗りを選択
等のせいで、工作期間は6ヶ月掛かってしまいました。
殆どはカシューと言う塗料の乾燥を待つ時間でしたが・・・。
一回塗ると完全に乾燥して次に耐水の紙やすりで研げるようになるのが3~4日後くらいなのですが、会社の休みの関係で1週間おきにしか作業できませんでした。
塗って、翌週研いで塗って、また1週間後に研いで塗って・・・の繰り返しです。10回近く塗ったでしょうか・・・。とても下手でしたから・・・。
塗装が終わると今度は砂利入れです。長岡先生の設計のバックロードホーンの箱では、D-37のようなCW型の場合、音の出口部分が、だんだん広がる階段のようになっており、その階段の一段一段に砂利を入れて階段の形を整え、かつ砂利で重量を持たせて低音の再生に備えています。
やはり重いと箱の振動を押さえ込めて、低音が前に出るそうです。
綺麗な砂利を・・と思い、茨城県産の寒水石(かんすいせき)という白い結晶質石灰岩の砂利をホームセンターで購入し、水で荒い、天日で乾燥させ入れていきます。結構な量が必要で、洗った砂利を乾燥させるのが容易じゃあありませんでした・・。
本当にすべてが根気でした。
完成したD-37は真っ黒な、文字通りの漆黒。
ピアノブラックのD-37は美しく完成し、なんとか音出しの日を迎えるのです。(6ヶ月は本当に気が遠くなりました・・・息子が2歳の頃だったので子供部屋が工作室に流用できたからこそ・・の工作でしたが・・・)
音出しは、やはり「ひどかった」・・・のでした。
モコモコ不自然なギターの音、鼻をつまんだような女性ボーカル。キンキンして低音が出ない。特定の音で共鳴してカンカン、ボーボー言うような感じがします。
スーパースワンの作りたての時の音より、遥かに酷い音でした。
いや作ったのを一瞬後悔した位、本当に情けないほど酷い音でしたねー。
この頃のパルプでできたコーン紙のユニットはエージング(加齢・・・AGE INGですね。いわば慣らし運転でしょうか)に時間が掛かるようでした。(現在ではコーン紙の素材が変更されて、小生の感覚では殆どエージング不要な程、初めから結構良いそこそこの音が出てます)
こう言うユニットのエージングはユニットの大きさが大きくなる毎に時間が掛かる様に成るとは言いますが、直径16cmの大型のスピーカーだけあって、本当にエージングにも時間を要し、絶好調!!になったのは、なんと、「一年後」くらいから・・・でした。
(このエージングの時間については、知識として本で読んで、知ってはいましたが、実際に一年ほど掛かったのは妙に驚きに感じました。)
しかし、しかしです!!
エージングが進みますと、これまた作りたてとは別物でございました。
高音域の切れ・切れ込み、低音の締まり、量感、中音域はもともと大型とはいえ、フルレンジ・スピーカーですから、大の得意で、澄み切って浸透力がありました。
何を聞いても最高です・・。ジャズ・フュージョンは特に良かったですが・・。
本当に始めて体験する音で、ストレートで情報量が多く、切れも抜群で迫ってくる・・・と言う音でした。
大変気に入りました!!!
これがバックロードホーンの音か!!と感動したものです。
音が「ツブツブ」になって顔をめがけて凄いスピードで飛んできて、「パチパチ」当たるような感じがしました。
音楽が余りにも情報量が多く、かつ凄いスピードでこちらをめがけて飛んでくるので、結果としてイージーな“ながら聞き”には不向きで、音楽と真剣に対峙する聞き方を要求されてしまい、リスニング後は少々疲れてしまうくらいのスピーカーでした。
こういうスピーカーを聞くと、音楽に心が持っていかれてしまう分、他の嫌な事を考える余裕が無いといいますか、忘れているようで、本当にストレスが取れるのを感じました。
D-37はこの後しばらくスーパースワンと2台でエースとして活躍しました。
2台を切り替えて、ジャズ・フュージョンはD-37、クラシックやボーカルはスーパースワンでした。
ですが、また数年後には、このエースも新しいユニットのD-37(ES)を作るために置き場所が無いので、知人に下取られて貰われていきました・・・。
現在は上尾方面で、元気に活躍しているそうです。
こうして、自作のスピーカーを数台作ってみて、なぜ、それがこんなに音が良いと思えるのか?を改めて素人の小生が考えて見ました。(もちろん自分の好みもありますが・・・。)
すると、それは、結局、低音から高音まで一個だけのスピーカーで鳴らすフルレンジスピーカーを使っているからだろう・・・に至っています。
よくある市販のスピーカーのように、低音・中音・高音と三つのスピーカーで鳴らす方式を3WAY(スリーウェイ)方式と言いますが、この場合音を低・中・高と分けるために抵抗やコイルやコンデンサーなどの電気部品を使った回路が必要になります。
この回路=ネットワーク回路と言います・・・が小生の好む音、直截な音、何も足さない何も引かないまっすぐな音、には良くないのだと思います。
微妙に言いますと、音の出るタイミングがズレる様だ・・とのことです。
低音用のスピーカーと中音用のスピーカーと、高音用のスピーカーに同時に音が来ても、回路を通る事で、各ユニットが一斉に動かずに、ほんのチョット動き始めがズレる・・・。
こう言うことを「位相ズレ」とか言うそうですが、こう言う微妙な事が、人間の感覚では分かるようなんです。
フルレンジでネットワークが無いと良い音だ・・という感覚は、アメリカのCESでEPOSという回路を廃したスピーカーの音質に出会った時から、やはり変わらず・・・そうだ・・と小生は思っています。
もちろん諸説有りますようで、高度に設計制作されたネットワーク回路は、相当良い音なのだそうですが、我々素人が作る場合には、メーカーの技術者さんの様な高度な耳がありませんし、コンデンサー1つを決定するのに何十種類も聞き比べて決定するような環境もありません。
ですので、ネットワーク回路の高度なチューニングは、素人には殆ど不可能と言うか、難しいのではと思っています。
ですので、素人の自作スピーカーシステムはフルレンジスピーカーで作ると、結果的に安全ではないかなあ・・・と思っています。
そして、出来ればフルレンジには高品質なスピーカーユニットを使い、低音を補うのは箱(バックロードホーン)というのが、あくまで自作の場合の良い選択では?・・と思っています。
(この後、小生は相当な数のスピーカーを作りますが、1台を除いて全部がフルレンジ・バックロードです。)
長岡先生設計のスピーカーの自作経験では、このD-37の後に、D-102と言うのが有ります。(その後も殆ど長岡先生の設計を作ってますが・・・)
キッカケはスーパースワンに向く新型ユニットが開発されたので、ユニットを交換したからでした。
新型の10cm口径のバックロード用の限定ユニットがFOSTEX社から出ますと、このユニットを無理しても購入し、スーパースワンに導入します。
ユニットを交換をしますと、古いユニットが外されて・・・余ります・・・。
もったいないのです。これが・・。
この余り・・の有効活用で新しいスピーカーを作る大義名分が出来てしまいます・・・。
結局D-102というブックシェルフ型のバックロードホーンを長岡先生の設計どおりに作る事にしました。
このスピーカーは、棚などにも置けるブックシェルフ型であるにもかかわらず、正真正銘のバックロードホーンでありました。
普通の箱の形状の内部に、バックロードの複雑なホーンを折りたたんで収めた設計は、空間を立体的に認識する設計能力・センスの賜物と思われました。
この設計は本当に天才のものだなあ・・と感心し、大変気に入ってつくりました。
安いラワン合板を購入し、ドイトさんで直線のカットだけしてもらい、丸い穴や四角い穴はジグソーを買って自分で加工しました。
例によって図面どおり組み立て、ラッカー塗装で黒く塗り、ユニットを取り付けました。
そこで、スーパースワンとの違いを思い知ったのです。
同じ長岡先生の設計によるバックロードでもこのD-102は・・・設計が古かったのです。
FE-108スーパーのような強力ユニット向きの設計ではなかったのです。
作ってみると、箱に対して余りもののFE108スーパーというユニットが強力すぎました。
低音が全然出ませんでした。
スーパースワンで2年ほど使ってきたユニットなので、もうエージングは十分出来ているユニットです。それでも低音が出ませんでした。
これには参りましたが、結局何の事はなかった?のです。
限定の強力型ユニットの流用を諦め、FE108Σという普通に定番で売っている、やや弱いバックロード用のユニットに入れ替えました。
そうしたらこの箱が生き返りました。低音が元気よく出たのです。
箱とユニットには、設計上の合う合わないがあるのを知りました。
余り品のユニットの活用の筈が、新しいモノに出費することになってしまいました。
もともと、このスピーカーはローコストに作るためにシナ合板を諦め、安いラワン合板を採用し、かつ、ドイトさんで安くカットもしてもらい・・と頑張っていたのに・・・結局2万円ほどの出費でした。
えてして、そう言うものでしょうかね・・・。
このD-102はユニットも標準型で、それほど凄い音では無いのですが、バランスがよく、聴いていて疲れない音質でした。
スーパースワンでは低音の出るラッパの出口は箱の後方に大きくポッカリ開いています。
後方出し・・・なのです。
低音というのは、人間の耳では音のする方向を聞き取れませんので、後ろから低音が出ていても問題は無いはずなのです。
D-102は前面開口・・・。これは、これで気に入りました。
低音は何処から聞こえても良いはずなのですが、小生はこの前面開口で、ユニットと近い「穴」から聴こえる低音を気に入ったのです。
・・・ユニットと低音の出口が近いことから来る自然さ・・もあると思いました。
このD-102スピーカーは一旦は兄にあげたのですが、結局余り活用されず、小生のオフィスに出戻ってきたので、小生が使っておりました。
すると、これを見初めた人がおり、その彼に拉致されました。
現在は代々木方面で放送関係の分析などの仕事をしている友人オフィスで、活躍しているそうです。
その後、このブックシェルフ型のバックロードは大変気に入りましたので、色々類型を作る事になりました。
長岡先生が逝去されましたので、この設計を下敷きに、仕方なく自分でFOSTEXさんの新しいユニットが発売されると、その新ユニットに合わせて、このD-102や同類のD-99をマイナーチェンジして新たに図面を書いてつくっております。
現在では小生は、おそらくこのブックシェルフ型バックロードを最も作った男・・の一人になると思うのですが・・・。
大げさでした。・・・すみません。
自分が設計変更したものも含めて、3台のブックシェルフ型のバックロードを作っただけでした・・・。ごめんなさい。
D-102(長岡先生作品)
D-99(長岡先生作品、FE-88ESと言う8cmの強力限定ユニット使用)
D-99ES-R(先生ご逝去の後、発売された8.5cm強力限定ユニットFE-88ES-R用に、D-99を土台に自分で数値バランスを計算しアレンジしたもの・・ひと回り大きくなり、別物です。これは追って制作記と図面をお見せいたします)
と3台作りました。
設計だけでしたら、10cm用のD-102を現在のFE108ESⅡという最新ユニット用に全面的に変更したものも既に完了しています。
この続きはまた・・・
※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。
耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。
有名なスーパースワンでさえも、お作りになってすぐ後、聞けた物ではないので、捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この自作スピーカーについての内容は、あくまで小生の感覚・自分の好みでございまして、客観的な比較や性能の説明とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。
理想の車
「理想の車」
以前、書きました四角い車・・に続きまして、車については自分の考え・気持ちの変化も有り、最近も考えるところ・・大いにありです。

二つの視点・感覚で考えております。
一つ目は、もう『パワーエリート』って感覚の車は、時代にマッチしないんじゃないのかなぁ?・・という感覚が自分の中で、でき始めていることです。
そう言う変化が、なぜか最近あるのです。
オラオラ走り、ドケドケ走り、割り込み・・等の印象が強いこの車たち・・・。
以前は結構いいな・・と思い、欲しいとも思って、憧れていたこの車たち・・・。
パワーエリート(この言葉、小生は現代的な成功した、ややIT的なお金持ちの社会人・・風に使っています)にフィットする成功の象徴としての車・・・有名なドイツ車などが顕著にこう言う役割と思いますが・・・。
今は、もっと環境に優しい感覚。
自分の主義を身にまとう、質素な感覚の車・・が良い様に「ちょっと」感じ始めております。
で、そう言う視点で考えますとこれはこれで、ピッタリ来るのがなくて、現状の車たちに寂しさを覚えます。
車のつくり方の業界スタンダード??には、封建的な身分制度のような地位・格付けにあわせた車格・ランクが厳然とあるように思うのです。
それが自由なユーザー志向の取り入れの邪魔をしていると思います。
業界常識がお客様と乖離しているのでは無いでしょうか?
以前もSUVのカーゴスペースが小さくて、自動車会社の人はデイキャンプしかしないのだ!!と決め付けた様な事を書きましたが・・・。
ものの本では、現在を不連続線上の市場だといっております。
昨日のよかった事や、昨日の正義や昨日の正解は、一夜にして不正解になる市場だそうです。過去の成功体験、不文律などは通用しないと聞きました。
それでも業界は・・・。
1000ccの大衆車(この言葉がすでに凄いです)より1500ccが上。
1500はセダンからワゴンまでありますよ・・。
若者はこのクラスのハイパワー、ちびっ子ギャングをどうぞ・・。
課長さんになったら2000cc以上をマークしてください。
部長さんは『・・代表的な日本の高級車を・・』ぜひ!!。
経営者さんは、パワーエリートの車を・・高級外車を・・。
値段はきっちりと並んでいるがごとくに、「車格」を踏襲して「階級化」している。
ラインアップが大きく変化はしていないと思います。
蛇足ですが、ヨーロッパの高級車メーカーは、自国内で売っているタクシーなどにも使える安い仕様・モデルを日本には決して持って来ないと聞きます。
バカにした話??ですが、日本人にはお値段の高いモデルを売るそうです・・。
その方が、日本人が喜ぶから・・・だそうですが・・・。
この車格による階級化?には、今や感覚的にも凄い違和感があるのです。
もちろん小型・高級という新しい切り口の車の提案も日産さん、マツダさんあたりを皮切りに、出始めていて、「芽」はあるように思いますが、階級を超える程のものは、まだまだ「無い」ようなのです。
例えばこんなんは?どうでしょう?
1500ccくらいで、手段はともかく何しろ超低燃費、低公害。
ロハス?でしょうかね。
ボディーは小さ目のサイズ・・・以前小生が言っていた、四角くて、車高が高くて・・・にはとりあえず拘らないで、ここでは置いておきます。
小さ目のサイズ・・だけにします。
でも内装は贅を尽くしている。
足回りやボディーの一部やドライブシャフト等にも、カーボンなどのとんでもない高機能な素材が走安性と乗員保護、安全性の向上のため、軽量化による燃費向上のために使われている・・。
新しい高級は、雰囲気・概念の高級ではなく、『素材の高級』だったりして・・・。
で、これに、内装の贅・・・で高級なイタリア産のなめし皮革を大幅に採用したり、もちろんウッドは本物で・・・しっとりと作りこんだら相当説得力ありだと思います。
さらにこれを、もっと冒険する気(根性)があれば、内装やデザインで相当に暴れてもユーザーの支持を得ることもできるように思います。
例えば、シート素材は最高の綿の刺子(さしこ・しころの類とか)など日本の伝統素材を採用し、夏はシートの表面を、い草の寝ゴザのようにしたり・・変更可能にする。
蒸し暑い日本の夏を快適に過ごす古くからの知恵を、美しくデザインして取り込んだり・・・。それをシート表皮の交換だったり、リバーシブルで裏返したりして・・と言う機能で提供するとか・・・。
内装は徹底して和の寛ぎで作り込むのも、そろそろ良いのでは・・・。
内装のウッドの表現もウオールナットやチーク調ばかりでなく「汚れない正目の白木(檜)」・・なども良いと思われますし・・。
まるで清潔な寿司屋のカウンターの雰囲気・・なんてどうでしょう?小生は好きですが・・。
後部座席のウインドウ・ガラスは合わせガラスの2枚のガラスの間に竹製の格子を挟みこみ自然な遮蔽にするとか・・・。
はたまた二枚のガラスにして、それぞれ、外側のガラス戸、内側の障子のように別々に開閉できるような窓にして、内側ガラスの表面に和紙のテクスチャーを加工し障子を演出するとか・・。
そもそも自動車=洋式・・これもそろそろ違って来ても良いような気持ちです。
内装を漆喰や砂壁にしろとは言いませんが、そろそろ新しいモダンな「和」を自動車に溶かし込んでも良いような気がします。
いや、むしろ意識としたら「砂摺りの壁にしよう!!」と言うくらいの根性・発想からスタートすれば、実際に相当な新しい事ができてしまうようにも思います。
さすがに、こういうジャストアイデアを作って下さいとは言えませんが、いずれにしても日本企業の中で、少し尖ったことをやる場合、相当にその責任者の方の人事リスクも高いでしょうから、根性が要ると思います・・・。
本質的に『企画マンが根性無しだと新しい事が出来ない』などと、あえて申し上げたりして・・。
でもです。そろそろ民族の車があってシカルベキ・・な気が「ちょっと」いたします。
おっとっと、脱線していないで、夢の車に戻ります。
乗り心地の追求も、この車の白眉にしたいです。
コスト度外視のアクティブサスを採用している・・とか。
さらに遮音性は相当に良く、トップクラスの高級車のレベルだ・・・とか。
スピードを出せと自動車が人間を追い立てる高性能ではなく、時速60km~80kmが十分楽しめるハンドリング・走行性能と言うのは、いかがでしょうか?
もちろんスピードを出したら十分速いし、どっしりと安定性抜群・・にしたいですが・・・。
亜熱帯に位置する日本(冗談ですが・・)らしく断熱性は世界最高レベルだ。
特にルーフの作りが付加物をつけた香港のタクシーすらを越えていて本当に凄い・・。などなど・・。お笑いですが、いかがでしょう?
(自動車が優れた断熱性能を訴えたって温暖化の昨今、そろそろ良いんじゃ無いでしょうかね・・なんと言っても日本は「亜熱帯?!」ですから)
モノコックシャーシの中に補強で発泡樹脂を入れる人もいますが、冷蔵庫の作り方のようにボディーを外板と内板で作り、その隙間を完全に発泡樹脂で補強断熱する・・・。
この場合、鉄板は相当薄くても強度は十分で断熱性は冷蔵庫の様に良いでしょうし・・・。
クラッシャブルゾーンには向かないでしょうが、樹脂充填で安全なボディーが出来ると思いますが?・・発泡条件の量産時のバラつきで「却下」でしょうかねー。
・・って言うような企画が、失敗を恐れずに350万円以上!!などの値札で売られても・・・正しいような気がするのです。
これは長い間、階級社会だったヨーロッパでは、出来ないのではないでしょうか。
日本だからできそうな気がしています。
時代は、従来のお仕着せの高級感やパワー戦争ではなく、新しい価値観、省燃費、低公害、かつ味わいのある、納得性の高い、新しい高級・・・等に動いているように感じている昨今です。
勝手なことばかり言っております。
お許しください。
でも、このコンセプトの車があったら、小生は責任も感じますので・・は冗談ですが、相当欲しい気持ち・・がございます。
二つ目の感覚ですが・・・。(これは1つ目とはなんら脈絡が無いので恐縮なんですが・・・。)
何で外国の人気車種に負けない車を本気で作らないのか?と言う疑問から来ている感覚なのです。
以前からこれについては単純に・・なのですが、ずーっと不思議でならないのです。
車の世界の常識では、外車は国産車より良いもので、値段が高いもの・・と言う常識があるように感じます。
これ、おかしくないでしょうか?
自動車産業が始まったばかりで、欧米から明らかに劣っていた時代の感覚。
この外車が上!!という感覚はもはや遺物の筈・・ですよね。
でも一方で、作るメーカーの方々にも、こう言う感覚が、もしかして・・・あって、外車と本気で勝負していない理由になっているのでは?と思うのです。
ごく一部の車を除いて、本気で外車を凌駕しに「行っていない」・・と感じられるのです。
なぜか国産車の企画は、『想定するベンチマーク相手の外国車より30%~40%安いのだから、性能面がやや下回るのは仕方が無い・・・』という限界を持っているように思われてならないのです。
価格からして、このくらいの性能が妥当だから・・・等と、勝ちに行かず、戦わない戦場を作り、そこで限定して商売をやっているように見えます。
なんで「完全に勝ってしまえる」ような戦いを仕掛けないのでしょうか?
国産の新興高級ブランドは、これへの挑戦を始めたのだろうとは思いますが、小生は『価格が高いブランド戦略』が必須とは思わないのです。
必要なのは良い車だ・・と。
値段も近づいてしまって、ほんの少し安いだけだが、性能は完全に超えた!!・・・は達成不能でしょうか・・・。
愛する日本のメーカーで本当に出来ないのでしょうか?
絶対的な値段の安さだけが商品企画の正義ではなく、コストとパフォーマンスのバランスで戦うべきだ・・・とは思いますが、そもそも勝つのってそんなに無理なんでしょうか?
これは難しいのでしょうか?
はたまた、このような真っ向勝負をやって失敗し、負けると、ご担当の人事リスク・・批判・・が大きくなってしまい、それに耐えられないから・・・なのでしょうか?
殆ど同じ価格になっても、『言い訳無しで欧州車に勝ってしまって欲しい』のです。
超えてしまって欲しいのです。
日本のメーカーさんは、本当は出来るんじゃないでしょうか?
もしドイツの名車に近い価格で、それらを超えろといったら、実際に超えてしまえる気がしています。
プランドの神話が・・とか、価格が通用するか?とか、理解されるか?とか、そう言う心配は不要だと思います。
そう言う定評はそれこそ、性能で越えてしまって、その後から付いてくると思います。
ブランドの競争は、まず性能で凌駕してから土俵につけるといいますか、始まるのではないでしょうか?
それから・・『神話は次のステージに入る』・・じゃないでしょうか?
超えるとは申しましても、「高級」を作って欲しいとは思っておりません。
性能面で超えて欲しいだけで・・・。
だから例えば、凄いエンジンとシャーシーとブレーキにあまりにも良いモノを投入し、性能を尖らせたので、標準の室内はビニールシートの商用バンのような内装になりました・・とか。
性能はドイツ車にも完全に勝っています。内装などを変更するのはオプションでどうぞ・・・。なーんて言われてみたいです。
これでは極端すぎて少々引いてしまう方も多いと思いますが、「超えた」の一種だと思います。
実際、愛車のスバル・アウトバックなどは、お客さんに、あと80万円、あと100万円のお金を出してもらえるのなら、某ドイツの名車を越える性能を実現できる・・・超えられちゃう・・のでは無いか?・・などと考えます。
WRCのラリーを見てもそう思います。技術的には出来るんじゃないかと・・・。
アウトバックのハイエンドモデルが実際に80万円上がったら、かーなーり厳しいですから、小生が買えるかどうかは全く別としまして、それでも相当ワクワクするとは思います。
逆の面から見たら、勝たない範囲でモノを作っていては、国際的な競争力が少々心配!!とも思います。
国際競争力だけでなく、会社が「尖がった突き詰めたもの」を作れない体質になるのも怖いですが・・・。
おおよそ商品が、他社と同様な、良く似たマトメ方ばかりになるのは、組織の論理のせいだろうと思います・・・。
ヒットしているものを(謙虚に?)パクって・真似ても失敗したんだから、責められない、しょうがない・・・。
チャレンジして失敗したら、それは「お前が悪い」と特定できる・・・。
こんな仕事のあり方は酷く夢が無いですね。
情け無いです。
車のカテゴリーや車格の話は本当に嫌です・・・。
小生もクロカンの機能をボクシーで背の高すぎないミニバン的な四角いボディーで実現して欲しい・・などと、ミニバンとクロカンの合わせ業を切望しておりましたが、ホンダさんからそう言う四角い車が出るそうでして、凄くありがたいのですが、ホンダさん自体か、自動車雑誌さんか?どちらの主導かは知りませんが、これをクロスオーバーカーとか言うジャンルで括っていますので・・それも又、嫌~な感じがします。
カテゴライズは企画をダメにしちゃう気がします。
商品が、適当なカテゴリーに逃げ込んでしまい、尖がった角を失って行くように感じるんです。
小生個人でも1ユーザーとしては、カテゴリーの概念は全く不要です。
多目的、大量積載、四輪駆動、高性能・・・で良いです。
マルチユースビークルとでも何とでも、それらしいキャッチなどつけて、他社を煙に巻いておいてください・・とか勝手に思ったりします・・。
ユーザーとしての自分は、買う前に広さや使い勝手、性能などしっかり検討しますから問題ないのです・・。
・・・きっと業界的には「落ち着きどころ」としても、なんかのグループ名が必要なのかもしれませんが・・。
そうそう、それから、収納に関しても、ルーフボックス無しでもスキーなどの長尺物や、かさばる物が積めるように、インテリアの天井側のルーフシェルフを作ることを真剣に考えて欲しいと前から思っていました。
なぜ何処さんからも出ないのでしょうか?・・・。
小生個人では相当ニーズがあるし、ルーフボックスを屋根に積むより安全で確実な収納なのに?天井を住宅の屋根裏収納のように「二重底にして大きな収納スペースにして欲しいのです。
たまにはスキーに行きますし・・・。
釣竿も長いですし・・。
ボディーを少々ハイルーフにしてもらって、その部分を収納として作りこんで、荷物の出し入れはワゴンのリアゲートを跳ね上げてそこからやる形でも結構なので・・。
いかがなものでしょうか・・。
ワゴン車には標準装備でも良いとさえ思います。
どうせルーフの長い、ライトバンの様な屋根なんですから、使わない手は無いと思うのですが・・。
それから、乗ってみて考えた事なのですが、4輪駆動の車の場合、メカで車が重くなって、また、そこそこのボディーサイズ(積載スペース)があると、総合して2000ccのエンジンでは、やや力不足と言うか、余裕と言う点でつらいのかなぁと感じました。
そこで3000ccをおごるとか、徹底した軽量化で前述の様なドライブシャフトをカーボンで行くとか、ルーフ部やボンネットをカーボンファイバーで作るとか・・そういうチャレンジングな提案や喜びがあっても、きっと車としては良いだろうなあと思っています。
もちろん売れ筋のゾーンでそう言う物づくりは危険でしょうが・・。
それでも小生は、そう言うボリュームのゾーンでさえ、この車は軽くしたかったから万難を排した・・みたいなフィロソフィーに触れたいと思います。
感動したいですね商品に・・。
各社が『きっちり競合する同じような車』ばかりでは、感動できませんし、もう、あてがい扶持の定番はうんざりですからね・・・。
『きっちり競合できている事』も本当は問題ですよね・・・。
命がけで冒険して、担当の方全員、失敗したら左遷されてください。・・・なーんて。
でも、これあながち冗談ではなく、そう言う思い切りや元気が必要なのが、昨今の日本の物づくりと言う気がちょっと・・・いたします。
申し訳ありません・・・自分も出来ていませんが・・。
社内を見て、競合とカテゴリーを見て、相場価格を見て、商品仕様を決定し、ユーザーの真の使い勝手を追及した提案や、オリジナルな提案を行わない。・・と言う事は・・・何を目指してますのでしょうか?。
まるでガチガチに競合する事が目標で、それを目指しているみたいですね。
そうそう、なぜか各社様揃って・・・最近ライトが上を向いていると思います。
プロジェクターヘッドライトや反射板の革新?が背景でしょうか・・。
ガラスの造形に自由度が出来たのだと思いますが・・・。
前照灯じゃなく『上照灯』・・・。これは小生には凄く抵抗があります。
数年前、某社様のクロカン4WD車のデヴュー時にヘッドライトが、ボンネット側へ、ツリ目に上がっていたのが、最初にこの「上照灯」の違和感を感じたキッカケでした。
さらに、この車では、なんとメーカーが斡旋する社外品のアフターパーツのカタログに、この「ツリ目」部分をボディー同色にカバーしてツリ目を無くすパーツが載っていて、またビックリでした。
クロカンのアフターパーツ屋さんはクロカン好きの志向を分かっているなあ・・と思ったものです。
形は機能を示して欲しいです。
意味なくボンネット上面に回り込んだガラスは、何か嫌ですねー。
ガラスが上の方まで「ある」必要性を感じられれば、まだいいのですが、新しい形のためだけだと違和感もあるように思います。
各社さま、そう言うライトが多いのは、皆さんやはりデザイン的な新しさを採っているからなのでしょうか・・・。
小生は「ツリ目」や「悪顔」の車が、とっても『嫌い』であります。
今回も暴言・・ご寛容にお許しいただければと思います・・。
大変、大変、失礼致しました。
スピーカーの自作 しょの1
「スピーカーの自作 しょの1」
とうとう・・こう言うオタクな話の日が来てしまいました。スピーカーの自作編です。
自作「偏」でしょうか・・・まあ冗談は置きまして・・・。

これは今から10年位前のお話です。
長岡先生の傑作設計、スーパースワン(長岡先生の型番で、D-101Sです)の自作が小生の始めての自作スピーカーでした。
その経緯は前回のお話にございました・・・。
ざっくりした流れは・・・。
アメリカのCESでEPOS社のスピーカーに感動し、それからネットワーク回路の排除が良さそうだと学び、さらに秋葉原でFOSTEX社のフルレンジを1発入れたスーパースワン(長岡氏命名のこのスピーカーの愛称)のデモに驚嘆し、調べていくと長岡先生のバックロードホーンの素晴らしさを知る・・・と。いろいろ曲折があってこの自作への挑戦になったのです。
まず自作への第1歩として、設計図面の入手・手配を考えました。
それは、長岡先生の著書のリストから、確か「バックロードの傑作」と言う本を探し出しこれを購入しました。
この本のスーパースワンの説明は、図面も含めてかなり丁寧な解説があり、15ページくらい割いてあったと思います。
バックロードホーンの理論も分かりやすく解説があり納得しました。
つまりはこうでした。
バックロードホーンは小型のフルレンジスピーカー1発で、すべての音声帯域をカバーするための「工夫された箱のスピーカー」でした。
小型のフルレンジスピーカーユニットは、振動板が小さく軽いので、音の信号への反応が速く、中高音は品位が高く、とても良い音の物があるのですが、どうしても振動版面積の小ささゆえに、低音の再生の時にはコーン紙が空気に対して空振りの状態になってしまい、低音不足になるのです。
そこで、小型フルレンジスピーカーの宿命である低音不足を補うために、スピーカーの後ろに出る音(スピーカーは前と後ろに音が出ています)をだんだん太くなるラッパのパイプに導き拡大します。・・・このあたりの話はすべて長岡先生の理論の受け売りです・・・。
この時ラッパの設計で、低音に対して有効で、高音には反応しないようなラッパを設計しているようです。
現在なら故長岡先生の全図面集などがありますので、図面の入手は比較的簡単ですね・・。
小生はこの本を何回もじっくり読んで、内容の把握に努めました。
かなり難しい構造で工作も大変そうでした。写真の様な完成形になるのですが、下側の大きい箱の中は音の通り道が折り曲げられてビッシリ入っています・・・。ラッパですから音の通り道はだんだん大きくなっていくのです。
再塗装前に紙やすりで丁寧にサンディングしました。きれいになります。

小生この工作で、少々でも楽をしようと思いました。
秋葉原で、この手のスピーカー材料を売っていますのは木村無線さんやコイズミ無線さんが有名です。
小生ラッキーにも、たまたま木村無線さんの方でシナベニヤ材のカット済みの商品を発見しました・・・。
ユニットメーカーのFOSTEX製。シナベニヤ板の「カット材」なるものを・・・。
スーパースワンの図面どおりに材料をカットして綺麗に番号などスタンプし、段ボールの箱に梱包してあります。・・これは便利だろう!!と少々高くても買いました。
お値段は1台分確か?3万3千円だったと思います。
ステレオでは2台ですので6万6千円・・ベニヤの材料でもかなりお高いんだなぁ・・とおぼろげに記憶しています。
板材は音響用シナ合板・・などと書いてあり、ダンボールの箱もしっかりとしていて、それらしいものでした。
これ以外の材料も、この時は木村無線さんで買ったのですが、内部配線用のコードが1mくらい・・・ドイツのスピーカーコードでごく普通のものと、ミクロンウールという吸音材を一つ。
東京メタルと言う会社製の粒状の鉛を10キロくらいと、鉛のインゴットを4本。
鉛の重さだけで合計20Kgだったと思います。
スーパースワンにはその箱の中に、音質への効果を狙って鉛を充填する穴が設計されており、そこに鉛を入れろとの指定がありました。
金額は忘れましたが、「鉛」は少々驚くくらい、お値段がお高かったです。
それに、このスピーカーにアンプからのコードをつなぐための端子、・・・ネジでコードを締めて止める端子が、FOSTEX製のT-150?とか言うもの・・・(店の推薦品)2個で3千円くらいでした。
肝心なスピーカーユニットは限定品・・・FOSTEXさんが限定生産で500個とか1000個だけ作る、完全な限定モデルが長岡式のバックロードホーンでは良く使われますのですが、今回のスーパースワンの使用指定は、その限定モデルでした。
FE-108Sというユニットがそれで、このSがスーパーの略です。
外見は良く似たバックロードホーン用の通常の定番ユニット(いつでも買える非限定のもの)FE-108Σ(シグマ)とはコーン紙からマグネットの大きさなどまで異なり、雑誌などでは「別物」と表現されておりました。まあこの限定品は相当の強力型・・・でしょうかね。
すぐ売り切れてプレミアが付いてしまう限定ユニットですが、その時は、それを運良く2個買い求めることができました。30,000円くらいです。
限定品ですから?残念ですが秋葉原でも価格交渉は出来ません。値引きは無いです。
なんやかんやで材料が初期のモデルで10万円くらいかかりましたです。
(その後、このスーパースワンは、ツイーターの追加や新型ユニットへの交換や、贅沢な真鍮の取り付けリング[1個1万3千円くらい]の追加もしています・・写真は最新の状態です)
つまり小生はFOSTEXさんが最新技術の開発で10cm口径のバックロードホーン向きの新型の限定ユニットを販売される度に、これを入手し、同じ箱に入れ替えて取り付けて使ってき
たわけでございます。
オット・・・。まずは作るところでした・・・。
実際の制作はどんなであったか・・と申しますと。
まずは部品のベニヤ板の過不足がないかの確認をして、番号にしたがって並べ、図面の中に記載してある組み立て公式・・例えば(1+2+3)+4は・・・1のパーツに2を着け3を着け、そこまで出来たら4に組み合わせる・・と言う公式です・・・に従って組み立てます。
これは始めての工作で、いきなり部品も多く構造複雑で、組み立ての難しいスーパースワンに挑戦!ですから大変でした。
]
直角を出すのに「差し金」と言うL字型の物差しを買ってきたり、木工ボンドの乾くまでの小一時間の間、材料を固定して締めて置く金具・・「ハタ金」といいます・・・を入手したり。
組み立てていくとズレが生じてくるのですが、それを削るカンナも登場しました。
もともと看板・内装業を家業とするのが生家ですから、小生はかなり木工とかは得意で、道具もそこそこ持っていましたし、日曜大工さんとしては、そこそこのレベルなんです・・。自分で言うか!!
それでも初めてですから一週間も掛けて組み立てました。ちょっとづつ。
木工ボンドと釘の併用で強度は万全です。釘打ちは相当得意です。曲げません。なーんて。
仕上げは初めから真っ黒の塗装をラッカーでやろうと思っていました。
釘を使うので頭が出ますし、木目は無理です。ですので、釘頭をパテで隠したら真っ黒なラッカー塗装です。これはスプレーでやりました。
組み立て。配線。仕上げ前の紙やすり掛け。など、なんだかんだで2週間。
完成しました。
いよいよ音出しです。
鳴らし始めは、実はあまり良い音ではありませんでした。
積極的に「ひどい音?」でした。
低音は不足だし、音自体も硬いというかキンキンします。ボーカルは鼻をつまんだようです。
・・・そうです。これがエージング前の音。作り立ての音なのです。
毎日使ってどんどん鳴らしますと、音がこなれて日に日に良くなります。
箱も工作の時に無理やり釘で固められたり、速乾木工ボンドで固められたりしたので、素材にストレスがあるのですが、これが10日くらいでかなり取れてきて、30日くらいで相当落ち着くようです。
板のストレスが取れると音が良くなります。・・不思議です。
ユニットも音を出して1ヶ月くらいでコーン紙の糊などが落ち着くのでしょうか?相当良い音になります。
一ヶ月くらいで低音が出過ぎる程になり、いよいよ鉛の投入です。
鉛投入で箱の振動が止まったせいか、また低音不足になりました。・・・がさらに一ヶ月でまたバリバリ低音が出始めました。
トータル4ヶ月目くらいでは高音の繊細さ、低音の量感・・すべてに申し分ありません。
いやいや全く凄いスピーカーでした。
小さいユニット一個で低音から高音まで・・・。
凄い反応が早いスピーカーで、音質も良くて、音源は小さな箱なので音場感(おんじょうかん)が抜群で、録音した演奏会場の雰囲気が伝わりました。
小生がこの頃使っていた基準のCD(視聴用のCD)は、リー・リトナーさんの「カラー・リット」というアルバムでした。
エレガットの音の立ち上がり・・・の気持ちよさを聴いていました。
スーパースワンは優秀でした。
大好きなリー・リトナーのギターの音が「カーン」と抜けてきます。
ピッキングのタッチが見えるような感じと言うのでしょうか、エレガットのタッチが分かります。
シンバルやハイハットの「切れ」も抜群と思いました。
低音感も十分で不足は感じませんでしたし・・。
音がシャワーのように顔にぶつかる感じと言いますか・・・長岡先生の言われるハイスピードと言うのはこれなのだと思いました。
ボーカルやクラシックのバイオリンなども涙物でした。
女性ボーカルの生々しさは特筆モノで、目を閉じると「目の前にいる」感じです。言い過ぎかなあ?とも思いますが、あの時、本当に「目の前で歌ってる」・・・そう思いました。
また、室内楽では、録音の良いCDですとバイオリンがホールに響いている・・・素晴らしい音場が展開して、引き込まれてしまいます。
FOSTEXさんの小口径の限定品・超強力ユニットを使ったバックロードホーン・・・(スーパースワンの様な・・)と言うのは凄いスピーカーだと思いました。
しかし、これを体験している方は、おそらく本当に少数の方・・自作の面倒くささと戦った少数派・・・ですので、広く皆さんには・・・なかなか信じていただき難い・・とは思います。
しかし、良い音はちょっと・・・生活を楽しくしてくれます。本物とは行かないですが、感動できるくらいには音楽に浸れますから・・・。
ちょっとだけ得した気分とでも言うのでしょうか・・・。
こうして、この時の体験で小生、スピーカーは自作に限る・・などと思ってしまったのでした。
この時、それまで使っていた愛器。
片側5万円ほどの国産メーカーさんの30cm3WAYスピーカーは、エージングのできたスーパースワンの前では、比較の勝負にさえならず引退させられ、知人に貰われて行きました。
ご苦労様でした。
小生のスーパースワンが、その後10年の長きにわたってエース・スピーカーの座を維持できたのは、2~3年に一度くらいのユニット交換のおかげです。
FOSTEXさんの技術開発の進化で、同じ口径の新型が出て来たおかげです。
ドンドン高性能ユニットが提案されましたので、その度に買い替え・入れ替えで「生まれ変わった音」で楽しめたのですね。
このあたりは本当に自作品の良さ・・ならでは・・・ですよね。・・。
かくして、小生はちょっと『あの音・・』に近づきました・・・。
(この秋、拙宅の狭さの中、新しいスピーカーシステムを制作し、追加・入れ替えをやりましたので、スーパースワンは置き場所が無くなりました。で、泣く泣くですが、友人宅のエーススピーカー就任のお話になり、彼に譲りました。・・最後に紙やすりで丁寧にサンディングして、一生懸命再塗装しました。お化粧でかなり綺麗になって、現在は浦安方面で愛され・活躍しています。彼はこのスピーカーを使い始めてから「まるで外出嫌いな人・・・」のように毎日音楽が聴きたくてたまらないのだそうです。そこで、かつての愛聴盤(ロックからクラシックまで)を全部聴きなおしてみたいとか言っていました・・・本当に音質に嵌ったそうです。彼は若い頃からバンド・楽器をやっていたので、嵌ってしまうのだとも・・・。最近ではカーオーディオもこのスーパースワンとは音が違いすぎて、もう聴く気がしなくなった・・・との事です。・・・本当に良かったです・・・。気に入ってもらえて・・。)
※このバックロードホーン形式のスピーカーは、好き嫌いがはっきり出るスピーカーのようで、全くダメで、嫌いと言う方もいらっしゃると聴いております。
耳が良くて、周波数が分かるようなタイプの方にとっては、低音の特定周波数のピークとディップ(特性の凸凹です)が耐え難くて聴いていられない・・・とか、中・高音が雑で・ラフで、うるさくて聞けた物ではない・・・という方もいらっしゃるようです。
本項のスーパースワンも、お作りになって、聞けた物ではないので、すぐ捨てた・・と言う方もいらっしゃるそうですので、この内容は、あくまで小生の感覚でありまして、自分の好みでございまして、客観的な比較とは申せませんので、その点、一ユーザーまたは小生が譲った友人の方の主観といたしまして、悪しからず、お許し頂ければと思います・・・。
「路上禁煙・・屋外禁煙?」
「路上禁煙・・屋外禁煙?」
小生、非喫煙者になったので、微妙な立ち位置ですが、最近の嫌煙傾向を少々複雑な思いで見ていましたので、チョットお話を・・・と思います。
秋葉原での体験から思った事なんですが、・・あ、秋葉原だけでなく千代田区・中央区とかあちこちにあるでしょうか?

「路上禁煙」と言うのは、賛成であるものの、微妙な感覚も感じていました。
と言うのは、「路上」の「定義」も影響があるものの、『オープンエア』での喫煙の禁止・・と考えたら・・・問題もあるのかなあ・・と思ったからです。
タバコの害を考えますと、隣人に受動喫煙をさせてしまう状態は避けたいです。
「インドア」同室での喫煙は、非喫煙者の方に(強引に)煙を吸引させてしまう状況を作り出しますから、非常に問題です。
これは完全に分煙し、吸わない人と吸う人が同席するのは避けるべき・・(部屋ごと分ける)がよろしいか・・と思っていました。
しかし、『オープンエア』屋外では少々、考え方・定義など、コンセンサス作りと運用が必要かなあと思いました。
と言うのは、小生かねがね、喫煙は本来『インドア』で他人に「避けようが無いひどい迷惑」を掛けてしまうより、『オープンエア』で喫煙する方が良いと・・・もっと言えば喫煙は『オープンエアで吸うのが正しい』とまで思っていました。
ですので、小生的には、その観点からして「路上は屋外」なので、本来はOKな場所!と素直に考えておりましたのです。
当初は相当!違和感がありました。屋外でも禁煙か・・・。と。
・・・ですが、小生、気が付きました。
「路上」は小生が言うところの、本来他人に迷惑を掛けない「屋外」かどうか?と言う視点をデス。
これを真剣に考える必要が出てきました。
つまり、『オープンエア』でも、他人に迷惑のかかる・・迷惑をかける可能性が高い歩道はダメと・・・。
『路上禁煙』この適用は、「ハワイ」でもそうなってきたらしいので、世界的な傾向?でしょうか。
しかし、本来、屋外は一番喫煙に適する場所である・・ことを「そうだ」とお考えいただけるのであれば、路上(歩道)で無く、少々歩道から離れた入り組んだ場所で、人通り・往来が無いとか、歩道まで煙が行きそうも無い場所・・歩道に煙が行くまでに風で薄まり濃度が十分に落ちる場所とか・・・を喫煙して良い場所とした方が・・・つまり締め出すばかりより、その場所を良いとする方が、かえって健全な様な感じがします。
室内は喫煙者一人のプライベートな部屋でのみ喫煙可能・・その部屋以外は全てタバコを締め出しましょう。
人通りのある歩道からもタバコを締め出しましょう。
しかし、屋外で非喫煙者の方から十分離れている場所なら・・・その場所は良い・・とする方が、現実的であり、妥当なのではないでしょうか?
歩道以外の、人々から離れた喫煙場所であれば、「屋外にあっても良い」・・・このマニュフェスト(冗談です)はいかがでしょうか?
微笑ましい?共存のように思うのですが・・・。
逆説的に言いまして、タバコの煙を完全隔離して室内で浄化する・・方法だけが「良い」のだとしますならば、小生は、もっと有害な大型トラック等、ディーゼル車の真っ黒な排ガスや工場の排気なども、室内に隔離して完全に浄化して欲しいなあと切に思います。
タバコは数年、数十年掛けて健康を奪いますが、このような煙は数分で死を招きますから・・・。
禁煙してみました
「禁煙してみました」
小生、今は非喫煙者ですが、もともと沢山・沢山喫煙していました。
1日に50~60本くらいタバコを吸っていました。
ずっとヘビースモーカーで約30年・・・。
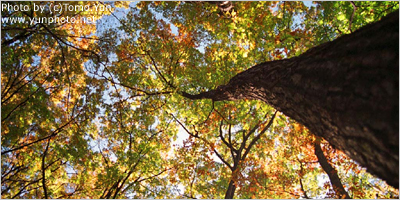
ですが、今年の夏頃、ふと禁煙を考えたのです。
50歳も過ぎて「年も年」ですし、健康に不安が無いわけでもなく・・・。
また、高齢の母からも「最近顔色も悪い」などと脅され・・。
さらに会社の事を想像して「もし僕が倒れたら社員の人はどうなるかなあ・・」などと凄く不安を感じたのが・・・禁煙しようかと考えたキッカケだったと思います。
「タバコ・・止められるかなあ・・」となんとなく考えていたのです。
止めようかと考えると、サマセットモーム?の言葉を思い出します。
曰く『禁煙ほど簡単なものは無い。その証拠に私は何十回も禁煙している。』
確かこう言うお話でした(笑)。
要するに禁煙は大変難しいのですね・・・。
だって、一発で止めていたら「何十回」にもなりませんものね・・・。
そんな事を考えている時、たまたま、コンサルタント業務のお客様に出向いて、担当者の方の前で、このような禁煙がらみの『止めたいの・・・』話!をしていて、その時は確か、禁煙用のニコチン・パッチ(シール状で肌に貼るニコチン補給用品?)の話などが出まして、お医者でこれを貰おうかな?などと話したのです。
そうしましたら、その担当の方が、「禁煙には良い本がありますのでプレゼントします・・・」「別の友人もそれで止めたんですから・・・」などと言ってくれたのです。
早速アマゾンなどを見てくれているようでした・・・。
小生は「へー、禁煙の本?」などと半信半疑の感じでリアクションしてました・・・。
そして、数日後。
アマゾンからプレゼントの『禁煙本』が届きました。
タイトルは、『禁煙セラピー』。著者はアレン・カー氏。訳者は阪本章子氏。
発行所はKKロングセラーズ。
小生、かつて、禁煙して7年くらいの間タバコを止めていた期間がありました。
その時、止めるキッカケに読んだ本は確か・・・「5日でタバコを止める本」
この本は、結構!効果的だったという記憶があります。喫煙の害が怖くなった本でした。
それ以来、「禁煙本」は随分と久しぶりになります。
結論から言いますと・・・。
今回のこの『禁煙セラピー』はかなり禁煙の動機になりました。
従来の禁煙本との違いは、まず、第一章:喫煙の健康被害の話・・などが無いことだと思いました。この手の本で、健康被害や発ガン性の話が無いのを珍しく感じました。
パターンが違うのですね。
ただ、『へー!なるほど!!』と感じた事がいくつかあり、それが禁煙に繋がりました。
禁煙は心の問題。~止める理由を考えるより吸う理由を考える~
タバコは麻薬。喫煙者はニコチン中毒者。喫煙は中毒症。
西側諸国で致死率第1位の麻薬中毒症。
禁断症状が吸い終わってすぐに出始めるハイスピードな麻薬。・・だからチェーンスモーキングになる。
一本吸い終わった瞬間から「もう一本吸いたいだろう」と言う声が聞こえる・・。
しかし禁断症状は非常に弱く、3週間で体から99%排出できる。
止めにくいのは洗脳されているから・・・。
タバコが楽しみや安らぎなどを与えてくれると言う間違った観念が・・・洗脳があるから問題。
と言うような主旨が引っかかりました。
特に一本吸い終わってわずか1時間でニコチンの75%が体から出てしまうので、また吸いたくなる・・・。
1日20本くらいになるのはニコチンの1時間でかなり抜けるという性質からしてしごく当然・・・。
等と言った事を勉強しましたら、喫煙することが少々バカらしいように感じられました。
禁断症状のすぐに出る弱い麻薬の虜になっていたのか・・・と。
いずれにしても「喫煙の効能など精神的なものも含めて何も無い!」と言い切られているので、止める事に繋がったように思います。
なんだか吸う気が無くなったのを覚えています。
でも、果たして今後も禁煙は続けられるでしょうか・・・
少々の不安を伴いながら、105日を越えてまいりました。
その後の魚フライ
「その後の魚フライ」
グルメではないので、食べ物の話は苦手ですが、うまいと思うものを・・・と紹介したキッチン・「ジロー」さんの魚フライ。
最近、日曜の休日出勤のときに、近くの「ジロー」が休みなので、たまたまお茶の水の「ジロー」まで遠征して食べてきたので、その時、ちょっと新しい情報が入りましたので・・・。
安くて旨い・・・これがまったく変わっていないのですが、魚の種類が変更になっていました。「沖目鯛」・・・だった筈なのですが、今は「沖ヒラス」だそうです。
この沖ヒラス。小生見た事はありません。
マグロの延縄漁(ハエナワリョウ)の外道(ゲドウ:つまり狙った獲物では無いが獲れてしまった獲物)だそうです。
いやいや魚の種類は変わっても、相変わらず臭みも無く、甘みがあって美味しいです。
これが・・・!!。

お値段は魚のフライ2枚とキャベツ、ご飯、トン汁で750円。
それから、この御茶ノ水の店舗・・・聖橋口を出て御茶ノ水橋口方面に50mくらい歩き、左に曲がって、坂をずーっと下って300mくらい先の左側・・にありますが、この店内には薀蓄の一杯書いてあるボードが追加で置いてありまして、大変勉強になりました。
薀蓄に曰く、
「ジロー」さん創業して39年余・・とか・・・。
それから、始めはメニューが3品くらいしかなく、お客様と試行錯誤しながら、だんだんにメニューを今の形に育てられたこと・・。
カレーは創業当時からあるメニューで、本当に自信の作であり、内容も手作りのガラムマサラも含めて大変強力なもの・・。
牡蠣フライは、築地でたまたま見つけたとても旨い牡蠣があって、それを仕入れようと夜行列車で広島まで行って交渉したら、いきなり断られたと言うメーカーさんの「もの」だったり・・・。
お米は、かつては確かササニシキ系統だったと思うのですが、今はコシヒカリの産地を混ぜたブレンド米になってましたが・・・変わらず美味しいです。
また、中盛とか大盛とかの量を増やすのは、特に料金の加算が無いのです・・・。
驚きます。
逆に小盛は30円の値引きです!!これって女性には良いですね。なんと良心的なことか!!今時無いですね、こういう姿勢は・・・。
と言うような、読んでいて楽しくなる薀蓄のボードがテーブルに置いてありましたのです。
やはり40年も愛されているお店の考え方は、普遍的といいますか、「凄いなあ」と思います。
お客さんを大事にしていて、食べ物自体の内容を大切にしていて・・・・。
本当に勉強させられました。
基本に忠実で変わらない・・・のですね。
「ジロー」さんを拝見していると、実は僕らゲーム屋稼業でも同じなのではないか?・・・長く愛されると言う事はそう言う、基本から大切にする事、ブレ無いこと・・なのではないか?・・・と感じました。
私たちに出来るでしょうか・・・。
頑張ってやって行きたいと思っております。
(最後にちょっと自慢なんですが、小生の気づきを・・・。)
「ジロー」さんのお店では、
『フライ』と言ったら、魚フライの事です。
牡蠣フライやエビフライではなく・・・。
ですので、魚フライを注文するとウエイターの方は
調理の方に、『フライ』と注文を通します。
うーん「ジロー」さんでは、フライの原点は魚なんだ!!きっと!!
と勝手に悦に入っている私でした。
SACDにビックリ
「SACDにビックリ」
既にお好きな方には、「何、今頃言ってんの?」状態で恐縮ですが、ここ最近で驚いたことをちょっと言います。

高音質のオーディオフォーマットの「SACD」・・・。
スーパーオーディオCDと言います。99年の5月からスタートしているCDにつづく新オーディオ・フォーマットのようです。 ・・・で、
・・・これ『凄い』です。
あらためて、ちょっと感動しました。今更ですが・・・。体験しましたので・・・。
もともと、小生は次世代高音質フォーマットには、ちょっと批判的な気持ちでした。
CDの記録できる周波数の限界を22Khz(キロヘルツ)くらいに設定したのはフィリップスとソニーでしょ?全くもう!!もっと先の事を考えてよ!!的な思いもありましたし・・・。
しかし、これは自分でも分かっていますが、勝手なユーザー的な言い分ですね・・。
だって、CDを開発した当時、まさか人間の聞けない筈の100Khzの音などが、聴感上、音楽の再現性で問題になるとは誰も思わなかったのだろう・・と思いますから。
こう言う事は、後に技術進歩と共に分かった事ですから、本当に仕方が無いのですね・・・。
しかし、分かっていても、やはり個人的には受け入れるのが辛いものです。
CDプレーヤー買って、ソフトも結構揃えて、なんとかデジタルの世の中について来て、今更、何がスーパーオーディオCD(SACDの事)だ!!って感じも正直言ってありましたしねぇ・・。
しかし、聴いてみて本当に驚いて!!しまいました。
小生もともと、SACDのプレーヤーなるものは持っておらず、パイオニアさんのDVDマルチディスクプレーヤーを数年前に購入しDVDプレーヤーとして会社で使っていました。これは2万5千円だか?の普及機です。
なかなか良い機械で、安くてもDVDもDVDのオーディオも、もちろんCDも、そしてなんとSACDも再生できるマルチ機能なのです。
小生、これを会社で不要になったので「私物だしねぇ」・・と、自宅に持ち帰りアンプに繋げてみました。
持っているSACDもたった1枚でしたが・・・。
渡辺 香津美さんのアコースティック・ギターのアルバムで「ギタールネッサンス」というSACDとCDのハイブリッド盤です。
イーストワークスエンタテインメント (2003/02/21)
売り上げランキング: 7,426

 心に沁みます
心に沁みます 価値ある一枚
価値ある一枚
いやあ!!「凄い音」です。
『香津美さんが目の前にいます・・です。』
何と言うのでしょうか、渡辺さんのギターと今聞いている小生の間に、録音した時の空気・空間が存在しているような感じです。
『凄いリアリティーなのです。』
最適な表現は「エアー」なのか「アトモスフィア」(直訳:雰囲気)なのか・・・。
そういう、録音した時のプレイヤーの周囲の音や、空気感を一緒に記録できていると思います。・・・SACDって「ヤツ」は。
当然、「こりゃいかん!」と言う事で、慌てて何枚か購入しました。
CDの頃から大好きな高音質のオクタビアレコードのEXTONレーベル・。
この会社のクラシックを買いました。SACD版で。
『ぶっ飛びます』
本当に。
くるみ割り人形聴きました。たしかアーネム・フィルの・・。
インディペンデントレーベル (2005/09/22)

 買い
買い演奏の音が出る瞬間、空気がオランダ?のコンサート会場なのです。
これ、大げさ?な表現で、皆さんから否定されるかもしれませんが、小生はなんとかお伝えしなきゃ!!と真剣に思いました。
小生のオーディオ機器は高いものは使っていないのですが、一点例外もありまして、それがCDプレーヤーです。
例外と言っても本来のマニア(オーディオファイル)の方からしたら、まだまだ「ハイエンド」の部類には入らない、TEACさんのVRDS-50というものです。
これが小生の大好きなCDプレーヤーなのです。
お値段20万円くらいのものですが、その後のメーカーさんのバージョンアップでメカ部をワンランク上のものにして5万円、DA変換のクロックをクオーツから高精度のルビジウムに変更して5万円追加しているものです。
SACDの音は、この自慢のCDから出る音を、情報量?や空気感等の要素で簡単に超えていると思います。
2万円くらい(現行機種は実売1万3千円?とか・・)のものが、なんやかんやで30万円から掛かっているCDプレーヤーの音を超えていると思います。
これはショックです。
これがフォーマットの差と言うものなのでしょうね。
機器の優秀性などでは、どうこう言えない、超えられない規格の違いがあるのですね。
その後、さらに何枚かのSACDを買いました。
殆どクラシックです。ある意味で、「クラシックを好きになれます」よ・・・。この音ならば・・・。とも言いたいデス。
また、ジャズやポピュラーなど海外のものが結構出ている事も分かりました。
先日アマゾンさんで、カーペンターズのSACDも買いましたが、もともと好きな声(カレン・カーペンターさん)ではありますが、 『もう、やばいっ』 領域でした。
A&M (2005/01/11)
売り上げランキング: 506

 すばらしい解像度
すばらしい解像度 お得な決定版
お得な決定版 サラウンドとは・・・
サラウンドとは・・・『来まくります!!』
身近のアーティストでは、aikoさんが結構沢山SACD出してます。きっと本当に音が分かっているアーティストさんなんですね。
凄いですねやはり・・・。
Gackt(ガクト)さんもSACDを出してますね・・。
ちなみに、山口百恵さんのSACDは沢山有りますよ・・。
高音質体験をぜひ!!と思いました。ので、ご批判あろうかと思いますが、書いてみました。
暴言、お許しくださいませ。
スピーカーの話2
「スピーカーの話2」
ちょっと言いにくい・・ちょっと恥ずかしい?『オーディオの話』の続きです。
前回はアメリカのCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)でEPOS(エポス)という小型スピーカーと出会ってその音の良さに愕然と驚き、またウン十年ぶりにオーディオに関心を持ったところまででした。まるで生音!!でしたから・・。

※EPOSの現行機種からイメージの近いM5を・・・
その後、小生はこの時の体験が引っかかっていて、暇を見て御茶ノ水のオーディオユニオンさんに行ったのでした。
果たしてお店にEPOSのスピーカーは置いてありました。おー!あるんだ!!と言う感覚でした。
このスピーカーの資料としては1枚ものの、白黒印刷の質素なカタログを貰いました。
お店のご担当の話はこのEPOSには割りと淡々としていて、説明も他のスピーカーと比較しても特に力点も置かれず、率直に言うと「余りお薦めではない」ようなニュアンスでした。お値段も小型なのに「お高いぞ」と感じましたし・・・。
試聴もしましたが、棚の上で他のスピーカーとくっついて並んでいるこのEPOSは、CESで感じた感動を・・・それほど再現しているようにも感じませんでした。
あの驚きの生音と同じスピーカーだろうか??
しかし、片鱗はある!!ようにも思いました。なんか音がハッキリとしている。
ただ、それが「もの凄いリアリティーの音」にはなっていないな・・と感じました。
たぶん正確にいうと、音は良いと感じたのですが、その評価に確たる自信を持てるほどの自分では無いので、店員さんの話の雰囲気に巻き込まれて、「そうかなぁ」と刷り込みが入っていた!?のかもしれません。
こう言うときに絶対的な自分の評価を持てる人、持っている人は凄い人・耳の良い人ですね。(小生は自信ありません。ダメです。)
この時小生は、幸か不幸かEPOSを買おうと考えるより、どうしてああいう凄い音だったのだろう・・・と言う考えに向かっていました。
小生にとっての問題・「情報」はこの1枚のチラシの説明の方でした。
設計者ロビン・マーシャル氏は有名なモニターなどの設計を手がけ独立。その氏の信念でダイレクトな音を追求している。
内容はネットワーク回路を排除し、ウーファーはコイルやコンデンサー何も無し!!でスルーで結線(直接結線)。
トゥイーターも音質を吟味したコンデンサー1個だけを使うシンプルな回路。
この情報がかなり気になりました。
小生、電気はダメなのですが、それでも昔のスピーカーの裏側を覗いて見た事くらいはありました。
そこには結構色々な電気部品が繋がっているのは見て、知っていましたので、スピーカーって複雑だなあ・・という印象はありました。
ですので、EPOSには回路部品が殆ど無いという話には『へぇー!』と驚きました。
この事はかなり印象が強くて、心に引っかかりました。
『そうなんだ。余計な回路部品は音を汚すんだ。だからネットワーク回路はシンプルなのが良いのかもしれない』と言う具合に頭に入りました。
そこからが少々の探究の旅??になりました。
回路の無いスピーカーって何者じゃ??と探してみました・・・。
そして、突き当たりました。
ネットワークを排除する考え方に・・・。
これは、フルレンジスピーカー(全帯域対応スピーカー)を使ったスピーカーシステムと言うのがその代表的なものでした(スピーカー・ユニット単体ではなく、箱に入っていて、そのまま使う状態をスピーカーシステムと言うらしいです)
スピーカーの中で、高音から低音まで1個で全部カバーするのがフルレンジスピーカーです。俗にこれを好きな方々は、フルレンジ一発のスピーカーなどと言います。
ちなみに、何個かユニットが付いたスピーカーシステムをよく見かけると思いますが、それぞれのユニットは、
超高音の担当がスーパートゥイーター。
高音だけを担当するのがトゥイーター。
中音だけがスコーカー。
低音の担当がウーファー。
この下にはスーパーウーファーが・・・。と言う感じで周波数を分担しています。
そのため入ってきた音楽を周波数で分割する回路・・・これをネットワーク回路と言うそうですが・・・必要なのです。
このネットワーク回路が「音を汚す」と言う考え方があり、EPOSのロビン・マーシャル氏もそうなのでしょう。小生は興味がありました。
小生は分からないながらEPOSで久しぶりにオーディオに興味を持ったこともあって、このネットワークを極力廃す考えに、仮に賛同しているような立場で情報収集していました・・。
もちろん世の中にはネットワーク回路の弊害を云々するよりも、この回路は必須だから良質に最適設計でやるのだ!と言う考え方の人も多いと思いますが・・・。
この情報収集の過程で、過去の一つの記憶・・の登場!もありました。
30歳の頃、おもちゃメーカーの開発本部の同僚仲間が、休日に会社に出勤し、工作室でなにやらベニヤの部品を組み立ててスピーカーを自作していたことを思い出したのです。
彼は「長岡先生のスワンという名機・スピーカーを自作しているのだ!!」と、かなりの講釈を聞かせてくれました。小生も面白がってこんなに小さなスピーカー1個で高音から低音まで再生できるのか?等、質問したりして興味深く聞いた記憶がありました。
残念なことに、この時、彼「Oさん」のスワンの音を聞いてはいません。組み立てた後すぐに、自宅に持って帰りましたから・・。
フルレンジ一発で追い駆けると小型スピーカーや長岡先生が多く出て来ました。(長岡先生はスピーカー自作派のオーディオ評論家の先生で、多数のスピーカーを設計し自作し、性能を検証してきた方で、本当に有名な、信者の多い先生です。)(先生は残念なことに他界されていらっしゃいますが・・・)
長岡先生が出てくると、小生は過去の記憶の「同僚Oさん」のスワン・・が出てきたわけでした。
さらに、もう一つのチャンスがありました。
試聴する機会です。・・秋葉原のスピーカーユニット屋さん等で、情報を取ろうとウロウロしていますと、コイズミ無線さんというスピーカーユニット販売の専門店さんに行き着きます。
その本店、秋葉原駅前のミツウロコビルの確か5階に、当時(今から10年以上前)完成品のスワンが展示してあったのです。
このスワンは、Oさんのスワンの頃から比べると、その後のフォステックス(FOSTEX)社のスピーカーユニットの進化に伴って、相当進化していて、「スーパースワン」になっていました。
しかも、このショップの独自企画の高性能な箱でした。曰く、木工の専門工場で「さくら」などの吟味した素材で、最高の加工精度で組み立て済み・・・お値段も箱だけで片側15万円くらいする代物でした・・。
この音は凄かったのです。
CESのEOPSで感動したほどではないのですが、それでもかなり驚きました。
音がくっきりと鮮明で、自分の方に向かって、高速に飛んでくる感覚。低音も十分に出ています。たった10cmの口径のスピーカーとは思えない低音です。
音のシャワーが顔にパシパシ当たるような感覚と言うのでしょうか。
長岡先生はハイスピードという表現を使っていますが・・・。
かなり驚いたのでした。
『これだな!!フルレンジ一発のバックロードホーン』と思いました。
バックロードホーンと言うのは箱の形式です。
この形式の箱は、小型のスピーカーユニットを使った場合に、不足しがちな低音をカバーする仕組みを組み込んだ箱なのです。
仕組みと言っても簡単で、ラッパです。
スピーカーの後ろから出た音を、ラッパ状にだんだん大きく広がる音の通路に導いて、低音を取り出す箱なのです。
これで、小生のEPOSの感動の再現は、
①フルレンジスピーカーのユニットで、
②ネットワーク回路を使わず、
③バックロードホーン形式の箱を使い、低音を十分再生する。
自作・工作のプロジェクト(大げさですみません)に相成りました。
・・・そうです。
1台15万円、ステレオで30万円の完成済みの豪華なスーパースワンの箱の購入!!でも当面の狙いは達成できたのですが、当然ですが・・・小生はローコストな自作を選択したのです。
これが、その後スピーカーを設計して作る趣味に・・・繋がってしまうのですが、この頃の小生はそんな考えは微塵も持っておらず、あの時のCESの感動に近づきたいなあ・・とだけ考えておりました。
次回はこの自作の話を・・・。

※小生自作のスーパースワン
沢山作ってますのでじっくりと・・・。
スピーカーの話1
「スピーカーの話1」
悲しいことに最近では、『オーディオ』・・なんて死語でしょうか?
もし、趣味は『オーディオ』・・と言ったら相当、親父くさい?でしょうか?
『オーディオ』と言うこと自体が相当「カミングアウト」もん・・でしょうか?
小生、白状します。オーディオ・・・と言いますか、ステレオで音楽を聴くのが好きです。
たぶん小生の同世代の方たち(40歳代や50歳代)は、少なからずオーディオの洗礼を受けていらっしゃると思います。
今から35年位前は、若い人の欲しい家電品には、必ずのように「ステレオセット」が入っていたと思います。
当時はアナログ・レコードの時代・・・CDなんてまだありませんから・・・。
いい音で音楽を聞ける装置は、憧れでした。
昭和45年頃、高校生の小生は、剣道に明け暮れてはいたのですが、たまに学校の帰りに御茶ノ水の「オーディオ・ユニオン」さんに寄り道して、高級な試聴室の片隅で「音」を聞いたりしていました。
鳴っていたスピーカーはタンノイとかアルテックとかJBL・・・。今でもタンノイやJBLは良く見かけますね・・・。アンプはマッキントッシュやマランツ。
タンノイのGRFだったでしょうか?凄く生々しい音でクラシックを奏でていました。
もう引き込まれるような音の良さ、生演奏?と言うのはこう言うものだろうか?・・とか思ったものです。(本物のシンフォニーなんて聴いたことがありませんでしたから)


※写真は左からタンノイの現行機種ターンベリーHEとJBLの現行のモニタースピーカー4348です・・※
当時でもこういうブランドは、ちょっと揃えると100万円以上したと思います。
本当にお高い商品で、単なる憧れでした・・・。
当時、我々でも手が届いたメーカーは、国産の御三家・・・などと言われるトリオ(現在のケンウッド)山水、パイオニア・・さんですかね。
スピーカーではダイヤトーン(三菱)の評判が良かったと思います。
何しろ、あの厳しいNHKに正式に採用されていたモニタースピーカーは三菱製でしたから・・・。
今では三菱はオーディオから撤退しちゃってます。
・・・本当にこう言う優れた日本の技術の継承ができないことは、社会的な損失のように思いますし、寂しい限りです。
小生の生家では、父がそれなりのセットを揃えてくれていました。
スピーカーはパイオニアCS-E900。アンプとチューナーは山水のAU(TU)888。ターンテーブルはPL-41C。全部・・・今でも覚えていて本人も驚きますが、忘れられない型番です。


※写真は左から愛器のCS-E900とAU-888・・※
そんな高校時代の通過体験?はあるのですが、その後40歳代まで、住宅事情の問題もあり、結局、装置を買っても大きな音では聞けないし、『オーディオ』を忘れつつありました。
ミニコンポ(こだわってミニコンポの中では本格的と言うか、良い物にはしていましたが・・・)を買ったりはしていたので、それなりに好きでしたが、自分の中で優先は下がっていたと思います。
それが、ある時、出張でアメリカのエレクトロニクス・ショウに行っていた時に、大きな転機を迎えます。そこで小生は衝撃的な体験をしたのです。
本来の出張目的は、携帯電話や通信機器、PDAのリサーチだったので、オーディオのブースは覗く程度だったのです。
巨大なCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショウ)の会場を、足を棒のようにしつつ、ブラブラしながら歩いていて、本当になんとなく立ち寄ったブースで、驚くほど心に響く音楽が鳴っていました。
装置は小型のスピーカーでした。
アンプは確か超高級品(フランス製?)だったと思いますが、音の主のスピーカーは、幅25cm、高さ50cmくらいの物でした。
とても生々しくて、音楽が心に飛び込んでくるようで一瞬立ちすくんでしまう程でした。
鳥肌が立ちました。
感動しました。
このスピーカーのメーカーはEPOSと書いてありました。
このEPOSを買うことはなかったのですが、この出会いが、その後の小生のもう一つの趣味、スピーカーの自作へと繋がって行くのです・・・。

※EPOSの現行機種からイメージの近いM5を・・・※
そのあたりのお話は次回に致しますが、若い方々にお薦めなのは、良い装置で音楽を聞くことです。
もちろんCDラジカセは十分に良い音です。
十分以上に水準の音が手軽に楽しめます。
これがあまりに手軽で良い音なので、オーディオの出る幕が無くなったと言って過言で無いほどCDラジカセは良いと思うのです。
ですが、あえてお薦めするのは、面倒くさい「バラバラ」の単品のコンポで、できれば大型のスピーカーで音楽を聴くことです。
それまでに聞いた事の無い音が聞こえると思います。
自分の持っていたCDに、こんなに情報が入っていたのか?と言うくらい違うと思うからです。
実際拙宅に遊びに来られた20歳代の人が、「凄い・・・生みたい・・・僕も作ります・・・。」などと嵌ってしまった例もありまして、体験するのは良いことかと思います。
個人の価値観ですから、「そんな事気にしない・・・」のも、もちろん結構です。
だから、ただのオジサンのお薦め、ご紹介なのです。
人生っていうものは皆さん平等に、一回のチャンスです。
「オーディオ」もお試しになる価値はあると思います。
試して、知っても、それに価値を見出さない時は、それはそれで良いと思いますので、この話、忘れてください。
趣味ですから「好み」もありますが、これがうまく合いますと、音楽を聴くことも人生の楽しみ・・・ちょっと大げさですが・・・になると思います。
では、この続きの「自作話」を次回に・・・。
ランタンのレストア3
ランタンのレストア3
今回は期待していただいていない!?第3回・・ランタンの塗装です。つまらない話?で本当にすみません・・・。
前回は色あわせ・・・これが課題で簡単なウレタン塗料のスプレーから本格的なガン吹き塗装・・・になっていくところでした。
インターネットで探せばあるもので、プロ用ウレタンエナメル塗料の小分け販売をしてくださる塗装屋さんのプロっぽいサイトを発見し、赤・黒・青・黄・緑と100CC単位のものを買い揃え、調色スタートです。(おもしろ塗装工房・塗装屋ドットコムさん)
これですと赤にほんのちょっと黒を・・・とか可能ですし、色の3元、赤青黄色があればかなりの色を作れます・・・。
小生は「暗めの赤」を作りました。
赤は赤で、大して変わらないと言う意見もありますが・・・。
で、道具です。エアスプレーガンとエアコンプレッサーを購入しました。これもピンキリです。エアースプレーガンは3千円くらいから1万7千円(もっと上もありますが)くらいまでが普通です。
圧縮空気を作るコンプレッサーはモーターとピストンと空気のタンクでできていて、素人用で2万から3万。(プロ用は20万とか)
小生はこのエアコンプレッサーもスプレーガンも数点購入に失敗しています。
コンプレッサーも初めはミニサイズ(タンク8リットル)を買い・・・これはプラモデルなどの小物の塗装が限界で、ランタンには小さすぎました。
スプレーガンもやはり1万円くらいする重力式(塗料を入れるカップがスプレー本体の上にあり塗料が重さで降りてくるもの)でノズルの径が0.8mmから1.3mmくらいが良いようです。
(小生は口径0.8mmのデビルビス社のFUNという、ちょうど1万円くらいのモデルを愛用しています)
初めは安価なガンを買ったのですが、空気の量の調節ができなかったり、ノズルが大きすぎたりで、ランタンの塗装に不向きな物でした。
安物買いの銭失い・・・とは言いますが、失敗多数です。
結果として、コンプレッサーは100ボルト、1.5馬力、タンク25リットル、のオイルレスコンプレッサー(コンプレッサーは油を入れて使うものと、オイルレス仕様があります。オイルレス仕様は油の注入が不要でメンテが楽です)で落ち着きました。(2万円くらいでした)・・・マニアックな話で恐縮です。
ガン吹き塗装にはこのくらいの道具の(ホースなど含め3万円強くらい)コストはかかるのですね。
で、ウレタン塗料の赤にほんのちょっと割り箸の先に黒や青等を付けて混ぜ、ランタンに合う様に調色したものにシンナーを入れ、硬化剤を塗料の10%加えてよく攪拌して塗装します。
ランタンは古い塗料を完全にはがしてあり、それをアルコールでよく拭いておきます。アルコールで脱脂しませんと銀色の鉄むき出しのタンクに付着してしまった手の油などが、塗料をはじくことがありますので・・・。
初めてコンプレッサーを使い、勢い込んで塗った時、スプレーから出る塗料が粉っぽくブツブツになって失敗してしまいました。「なんじゃこれはー!!」とビックリしました。
憧れのガン吹き塗装は難しいものでした・・・。
粉粉回避のポイントは、シンナーの量の加減による・・ようでした。
シンナーが少ないと、どうも塗装が粉っぽくなります。空中に出た塗料の霧が、すぐにその場で乾燥して粉状になりタンクに付着する感じ?になるからでしょうか?
真偽の程はやや疑問ですが、小生の感覚では、相当シャプシャプに薄めたら、うまく行きました。薄くした塗料は、塗装中ダラダラとタレやすくなりますが、シンナーは塗料の80%から同量くらい入れると良いようなのです。
この感覚は相当驚きで、かなり思い切って薄めないとこう言う感じになりません。
塗料はかなり薄くなるのですが、塗った後、艶が良くなるように感じました。
塗装は奥が深いと思います。
いまだに、やる時によって、うまく塗装できたり、ダメだったり。
シンナーにだって夏用と冬用があるのですから・・・。
最近でも、ダレてしまう時もありますし、粉粉になる時も、まだ、たまにあります。
難しいものだけに、実力以上にうまく塗れた時は、最高の気分で、「ヤッター」という感じがします。
結果として、最近までにつかんだコツは・・・。塗装がタレても「平気」になって、そのままにしておき、全体の塗装を完了する事!!・・でした。
つまり、タレたままの塗装が乾燥して硬化したら、水研ぎ(1000番位の耐水ペーパーを平面の板などにつけて使用)して、タレた部分を平滑に取り除き、コンパウンドで磨き上げればピカピカなのです。
おー!!素人の塗装とは、仕上げで磨く事と見つけたり・・・なのだなあと言う感じです。
実際、塗装がタレずにうまく行っても、結果として、スプレーの目(ツブツブ)を耐水ペパーで軽く研いでコンパウンドで研磨仕上げをするのが丁寧で仕上がりも美しいようですので、ある意味で、タレてもタレ無くても、やる事・仕上げ方に変わりは無く、やる事は同じだ!!と気が付いたのですねー。
かくして、何とか塗装もやりまして、ランタンのガソリンタンクはレストアが進んでいきますが、その間に、ランタンの各パーツの手入れも同時進行します。
タンクからはずした燃料パイプやバルブを分解し、洗浄し、磨きます。自動車用のキャブレタークリーナーで洗浄したり、ガソリンで洗浄したり・・。錆取り液の「花咲かG」に漬け込んだりもします。
明るさを調節するバルブの部分は分解・清掃し、黒鉛のパッキンが傷んでいたら、ネットオークションなどで探して入手し、ガソリン漏れが起きないように交換しておきます。
また、このバルブの先は円錐形に尖がっていて、円錐の斜めの部分で横から出てくるパーツを上げ下げして燃料の噴出量を加減しておりますし、最後まで閉めると円形の穴のフタをするようになり燃料を止めています。
ですので、この円錐部分は燃料の加減の時からそうですし、止めるためにも締めこみますので、年中穴との摩擦や他のパーツとの擦れで痛んでいます。
特に古いランタンでは、円錐の腹の部分の周囲が、削れて傷が付いているのが普通です。
傷のひどいものでは、ハッキリと螺旋状に削れています。
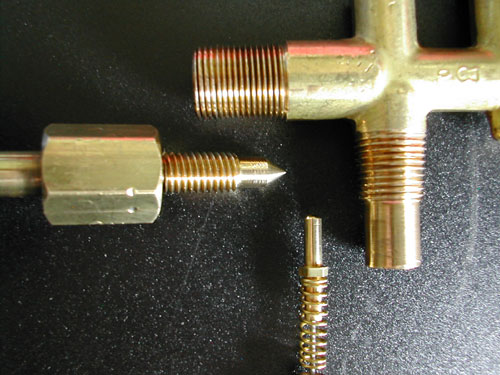
左から バルブの円錐形の先端です
このため小生は、このバルブ自体を電動ドリルに取り付けて、オイルストーン(油砥石)の上で回転させて研磨します。
円錐の角度が変わらないように注意しながら、傷がなくなるまで削って研いでしまうのです。
これで後々のガソリン漏れは・・安心なのです。・・・マニアックな修正ですねー・・。すみません。
タンクに空気を送り込むポンプ部(自転車の空気入れを小さくしたような物)も同じく分解し、清掃し、消耗パーツを交換します。皮やゴムでできたポンプ部のパッキンが傷んでいたりするからです。
またポンプの奥にある、空気の逆流を防止する弁部分(小さな鉄の玉が弁に使われている)も動作に不良があると、タンクの中にガソリンを噴出するための圧力(空気)を蓄えられませんので、そっくり交換することになります。こういうケースもけっこうあります。
消耗品ではジェネレーターというバルブの先に付けるガソリンを加熱気化してガス化するパイプも定番です。
これは完全に消耗品で、よく交換します(清掃で済むこともありますが)・・・。
ガソリンランタンでは液状のガソリンを燃やすのではなく、パイプの中を通るガソリンを熱でガス化した状態にし、それを燃やすのです。
ガス化するパイプの中は、ヤニ状の汚れが付きやすいようです。

錆び錆びのフレームの写真・・これくらいは普通のサビです
タンクの上に載る鉄製のフレームも、紙やすりや錆取りの液剤で錆を落としてから、銀色の600℃耐熱の塗料(オートバイのマフラー用など)で塗装します。
この塗料は乾燥後、オーブントースターに入れて200℃で60分加熱処理をしておきます。
耐熱塗料は塗った後、加熱処理をしないと本来の性能が発揮できないそうです。
ガラスのホヤ(グローブと言います)やホーローの傘(ベンチレーターと言います)は金属磨きのピカールなどでよく磨いて清掃しておきます。
ガソリンタンクのフタ(キャップ)も中のゴム製のパッキンもボロボロに傷んでいることが多いので、空気漏れを起こさないようにパッキンの交換をします。
この時、モデルの年代によっては、パッキンが生産終了で、現在供給されていない場合がありますので、そう言う場合は耐油ゴムの平板からポンチで打ち抜いてパッキンから自分で作ります。(まったく・・・マニアック)
これらの工程は、言って見れば、すべての部品をバラバラにして清掃し、消耗品を交換する・・・・でしょうか。
そして、いよいよ組み上げになります。
バルブの根元には自動車エンジン用のネバネバしたボンド状のシール剤(例えばホルツ社のガスケットシールなど)を塗って締め込んだり・・・。
色々注意しながら組み立てます。
と言う事で、美しく蘇った古いランタンが快調に点灯したときは、面倒と苦労が大きいだけに、こりゃまた!!大きな喜びになるのです・・・。
レストアには本当に苦労しますから・・・。
うまく行った時の感動も最高ですね・・・。お好きでない方には、何が??新品買えば??かも知れませんが・・・。
自分の生年月日と同じ年・月の生産(バースデーランタンと言います)のランタンが50年の歳月を経て、美しく蘇ると小生は妙に感動してしまうのですが・・・??????。

右から2番目がバースデーランタン(50歳)です。
古いランタンには良さがあるのです。だって最近のランタンは折からの製造物責任がらみの訴訟のせい?で、WARNING!とか使い方の説明などの文字だらけ、ステッカーだらけです。
ランタンのタンク全周囲に図解入りの「取り説」や「注意」があるなんて!
それに、古いランタンは明るい・・。最近のものは安全マージンを大きくとるためか、古いものと比べると照度が落ちます・・。
こんなこと、きっと、どうでも良い事なのですが、そう言うことに拘ってしまうところが趣味なのかも知れません。
小生の実兄が仕事を引退後、田舎の古民家を買って、田舎暮らしをするとか言っております。

一つ進呈しようと思います。レストア済みのガソリンランタンを・・・。
三丁目の夕日
ここのところ、あまりこのコーナーの更新ができておりませんでした。反省!!・・・です。
先日、見てきました。映画・・・ALWAYS。
小生にとっては大変、感動的な映画でした。
CGの東京タワーや昭和33年の町並みも映像として本当に自然に感じられました。「CGなどの最新技術もそれが違和感無く見られるようになると、いよいよ本物だ」・・・などと感心しました。
小生も4歳の時、建造なった東京タワーに登っております。階段を徒歩で・・・。
エレベーターが混んでいたそうですが・・・。
もっとも自分ではあまり、徒歩で階段を登り展望階まで行ったと言う記憶が無く、母からの伝聞です・・・。家には小さな東京タワーの置物(お土産)がありました。置物の定番でしたね。
小生は昭和30年生まれです。
今年50歳になりました。
ちょうど映画の中の風景は幼い頃の記憶そのものです。
子供たちは、冬はしもやけ・アカギレがザラでした・・・。
洟垂れ小僧などは本当に普通に存在していました。
当時、日本は戦後の10年で相当立ち直っていたのだと思いますが、今から見たら、まだまだ貧しい暮らしだったと思います。

(画像は弊社企画制作運営のゲーム「昭和レトロゲーム・・少年@時代」より)
小生もそうでしたが、着るものは兄弟のお下がり。夏は下着のランニングに半ズボンで学校へも外出先へも出かけていました。
今なら恥ずかしい?でしょうが、当時はそれが普通でした。
ズボンの膝には「ツギあて」がありました。
映画の中の描写にあったと同様。セーターの肘も肘あてのパッチがあててあったものでした。
セーターもウールではなく、アクリルで、着ていると毛玉だらけになりました。
毛玉をむしり取るのも大変でした。
お小遣いは、10円をたまに貰ってましたでしょうか。駄菓子屋さんにたむろして遊んでいたものです。
今と比べたら本当に貧しかったと思います。
でも、この映画を見て思い出しましたが、隣近所のお付き合いや他人への優しさ、思いやり・・・人間同士のつながりは豊かだったのかなーと思います。
現代、われわれは高度成長の基礎を作った競争社会?や、経済的な豊かさやと引き換えに、他人との関わりや、優しさを失ったのかも・・と思いました。
難しい分析はできませんが、当時は暮らしに「情」や「他人との付き合い」が溢れていた様に感じます。
隣近所の事件も共有していたように感じます。
例えば、当時、酔っ払うと道路の真ん中で寝てしまう近所のおじさんがいましたが、寝ていて車に轢かれないようにと、近所の人々が気遣って動かしたりしていたものでした・・。
「しょうがないなー」と言いながら・・。
小さな町工場を営む小生の自宅にテレビが始めて来た時に、ご近所の方たちにお披露目し、皆さんでプロレスの力道山を見たものですが、これは映画と全く同じシーンが私の生家でも展開されていた・・と言うことです。・・・強く記憶に残っています。
また、近所のおばさんに子供の頃の小生の事情などは筒抜けで、「受験するんだって?勉強頑張りな」などと声を掛けられたものです。
「いたずら」をしていますと、ご近所にしかられました。
いやはや、今思えば「うっとうしい」限りです。
近所の人がある程度、家族のプライバシーに入り込んでいましたからね・・・。
しかし、こういう共に生きている感覚は実はそれなりに重要なのかもしれません。
最近、恐ろしい犯罪も多発しています。
核家族化、個人主義、見栄、比較、嫉妬、、、付き合いが浅いから、人間の持っている悪い部分が出るのかなあ・・と思ったりします。
マンションの建て替えなどで住民が相互のつながり・付き合いを復活させ、コミュニティーを形成し、非常に暮らしやすい環境になったとか・・・。
こう言う話をテレビで見たりしますと、人間はコミュニケーションをとらないとダメな生き物としみじみ思います。
問題になっている「ニート」なども、地域社会のコミュニケーションが盛んなところなら、かなり解決できるのかもしれません。
お他人様に自分の家の恥を知られるのは辛い・・・なのですが、それでもある程度の上手な付き合いがあれば、言う方も聞く方も受け入れられるのでは・・・と思います。(相手の方の人となりにもよりますが・・・)
そうして考えて見ますと、ご近所づきあいは安全へのヘッジだったのかな?とも思います。
どんな奴か分からないと危険だから、話してみて、付き合ってみて、対策をしておく・・。
これは知恵でしょうね。
現在は、どういう奴か分からないから、そっとして付き合わず、知らないままにして、壁を作る。
安全策として高度なのは、昔風な一応付き合ってみる方法かもしれませんね・・・。
今の個人主義的な価値観は時代が形成してきたものですから、よく理解できますし否定しません。
良さもあります。
他人に踏み込まれなくて気楽でもありますから・・。
しかし、通学帰りの子供も守れない昨今、近隣への無関心の限界を少々超えているのかもしれません。

この映画、小生が感動したのは懐かしい映像・ノスタルジー的な側面ではなく、人間ドラマとして、おそらく自分にもこう言う心情があった・・と呼び覚まされたからかも知れません。
コミュニティー・・・、コミュニケーションを再考させてくれる映画でした。
そういえば弊社がサービス開始したゲームも「昭和レトロゲーム」「少年@時代」と言うタイトルです。
この話は次回に・・・。
過剰適応症候群??
日本人って良いですよね・・・。
同胞ですから当然と言えば当然ですが・・・。色々な表現やニュアンスも「阿吽の呼吸」で通じますし・・。同じような体験・・文化の中にいますから心情も理解しやすく・・・日本は良いです・・・。
しかし、一方で先日のAsian Strange Fruitでも書きましたが、日本って世界のスタンダードから見ると案外・・孤児?なのではないか?という危惧もあります。何が原因してこんなに色々問題?が生じているのかなあと残念に感じます。
で、最近、小生が勝手に考えている仮説があります。
日本は過剰適応の風土?文化であると・・・。
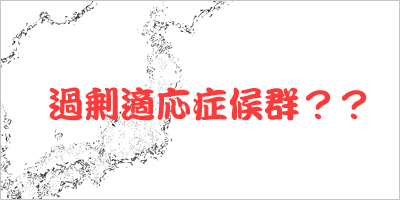
これに似た言葉では、開発の話で過剰性と感動・・・を先日、書きましたが、「これでもかの過剰性」「ここまでやるか」の先に生まれるお客様の感動とは、今回はちょっと意味が違います。
ここでの過剰適応は、日本人って何らかの負荷があった時、かなり苦しんで悩んだ末の結論でも、一旦それを受け入れると腹を決めると、真面目さ、真剣さのあまりアイデンティティー・自分らしさや、ある種の頑固さを失ってまで、環境や役割、立場などに過剰に適応してしまうのではないか?と言うことなのです。
適応が上手なのは、もちろん美徳でもあるとは思うのですが・・・やはりバランス感覚が大切だ・・・とも思うのです。
なんとなく、そんな感じがしていたのですが、小生の着眼点などを並べてみますと、どうお感じになるでしょうか?
まず食生活の変化・・・。和洋折衷とは言いますが、日本の食・・・本当にフュージョンしてます。
何でも受け入れています。小生の愚息等、いったい何人だ?と言うように、マックとか・・ラーメンとかを好物に挙げます。お新香と味噌汁が日本の食とは言いませんが、イタリア料理、中華料理などと比べても、アイデンティティー・ロスト(identity lost)・・こう言う英語あるかどうか知りませんが・・・・そう言う感じがします。
我々には外国から来た食べ物に適応するだけでなく、自国のアレンジを加え、例えば「日本のラーメン文化」・・にまでしてしまったり、カトゥレット?を日本の「とんかつ」にしてしまう程の、どうせやるなら徹底する・・・単なる許容や適応・・・を超える「こなしてしまう」凄い能力もあるように思います。
もしかすると今後、純粋な和食は、特別な時に食べるもの・・・になりつつあるのかも知れません。
終戦後はどうだったでしょうか?
日本の敗戦の頃、駐留米軍に、戦時中のキーワードでは「鬼畜」と言う凄い表現が付けられていたはずの米兵に、「ギヴ・ミー・チョコレート・・・」と言った少年たちは、本当に彼らに対する憎悪があったでしょうか。
憎悪があっても「敗戦」を受け入れていたのかもしれません。米兵も意外なほど抵抗もなく統治がしやすいことに驚いていたりして・・・?!現在でも、敵国だったって言う印象・・・ありますでしょうか?
敵意どころか、白くて背が高い人・・・これがかっこ良い?という感覚で「見上げる目線で見て」いなかったでしょうか?敵国だった国に「正義」を感じ、憧れを抱いていませんでしたでしょうか?
何も悪印象を持ち続けろという趣旨の事ではなく、こう言う日本人のやや特異?な性質を考えています。やることが決まり「腹がくくれる」と突進すると言いますか、目標に向かって真剣で、忠実で、己を捨ててでもやるような適応の徹底振りを感じます。
戦後で言えば、何しろ生き残る。何が何でも復興するという決心で、反米云々より「頑張ること」に無心だったのかも知れないな・・・とそんな風に思います。
良い意味で『日本の集中力』って凄いとも思うのです。
目標に純粋な民族と言う「言い換え」もできるかもしれません。
戦後のイラクの状況などを見ると、当時の日本の統治はしやすかったのでは?と感じたりします。
IVYルックなどとアメリカン・トラディショナルの(IVYリーグの大学出身者が好むような)スーツを着たり・・・アメリカのキャンパス・ライフが最高の憧れだったり・・・。
アメリカの格好よさの模倣をしたりは枚挙に暇なしで・・・。
江戸時代、明治時代にこう言う憧憬がありましたでしょうか?欧米列強のアジアに対する植民地支配を免れるため、急速に国力を発展させ、日本を守ってきた・・・。この頃は、相当日本が輝いていたのでは?と思います。
翻って今日、今の若者たちは、原爆を落とした米国が、今のアメリカと同じ国だ・・・変な言い方ですが、あえて言いますと・・・そう言う感覚があるのでしょうか?
かく言う小生もそうなんです。戦後の生まれだから普通かもしれませんが、日常の生活では、アメリカが敵国だった意識や感覚はほとんどないのです。歴史の知識として言われれば当然「かつては・・・」と答えますが、どちらかと言うと、憧れのアメリカだったと思います。米国の製品は、あこがれの「舶来」の代表でもありましたから・・・。
環境の変化や敗戦を受け入れ、何しろ生きていくことを選択したとも思いますし。それは正しかったと思うのですが、改めて考えますと、引き換えに何かを失ってしまった。そして、過剰適応の能力を発揮し始めたような気もするのです。
日本が復興し立ち直る時、形振りなど構っていられなかった。何しろ懸命に生きてきたのだ・・・。
真面目さと我々の素直さでしょうか。不可能を可能にし、経済は目を見張る発展を遂げたと思います・・。それこそ、復興と言う最高の「プロジェクトX」を成し遂げる過程で、日本は自分を少しだけ捨てたのかも知れません。
民族衣装・・・。これも今更・・ですね・・・。
サラリーマンの社会はどうでしょうか?どなたかの分析を読んだり、団塊の世代の先輩と話したりしたのですが、学生運動をやっていた彼らは、その後、過剰に社会に適応した・・・と言う話がありました。
つまり学生時代は共産主義に傾倒し、反体制を謳い、ゲバ棒を振った。デモでは機動隊に殴られ敗北感があった・・・。しかし、就職の時が来た。髪を切り、スーツを着て面接試験を受けた。学生時代の反動からか、反体制どころか社会に適応するとなると徹底して保守的に生きた。会社人間になり、組織に少々媚びた。
協調性を尊び、浮かない、出過ぎない、主張しない・・・そんな感じで生きた・・・・。と。
小生などが団塊世代の方を保身的だ・・・等となじると、良く「俺達のことを分からん奴が・・」と叱られました。でも、これも、生きていく知恵として、分かりますが、過剰適応?ではないでしょうか?
もっともこのような勝手な例示で、過剰適応=日本などと決めつけて言うつもりもありません。ただ、そう言う勝手な分析を考えますと小生は個人的に「腹に落ちる」気がしています。自分なりに納得できる気がしております。
分析的に正しいかどうかは恐縮ながら置かせて頂いて、これからどうするべきなのかな?が、かなり気になっております。
少々「日本らしさ」を主張したいなと思います。
Identityを主張できる日本。
理不尽には怒れる日本。
世界で通用する普通の国、日本。
日本らしい日本。
頑張り屋で、思い込みが激しく、口下手で、しかし素直で、人が良くて、水に流すけど自分のしたことも忘れっぽい日本。
今、アジアで問題にされているこのあたりの話も、実は日本の日本人の一生懸命な過剰適応の性質との引き換えの、「問題点」の表出のようにも思えてまいります・・・。
浅薄な話で恐縮でございました・・・。
ランタンのレストア2
今回は、前回の「チャラリ~、鼻から牛~乳~」の原因となりました・・・マニアックな「錆取り」の話しからです。恐縮です。
小生の場合、通常ランタンのタンクの錆び取りには、リン酸塩系の錆び取り剤を使用するのですが、(商品名は「花咲かG」・・オートバイのガソリンタンク用)これを使いますと錆び取り後にリン酸塩の皮膜ができ、数ヶ月の防錆効果もあるそうですので、かなり便利な錆び取り剤です。

この錆取り剤のことはインターネットのランタンのサイトで知りました。変な名前だなと思いつつ東急ハンズさんに探しに行きました。ラベルも「花咲かG」で大笑いでした。これはランタンに関係の無い錆びた物に・・色々日曜大工に使えそうですので、ご参考に・・っていらないですね!こんな情報・・・。
まずタンクの中を、台所からこっそり運び出した食器用洗剤で洗って、油分や汚れを取り除きます。そして、錆取り剤を指定の濃さ20倍に水で薄めたものをタンクに投入します。
この錆び取り剤は遅効性・・と言うのでしょうか、早くても数時間、錆のひどいときは数日くらいの時間をかけて錆を取るタイプです。錆が液に溶けるんです・・・これ。
タンクの中の液を排出しますと、デロデロが一気に出てきて中が綺麗に鉄の銀色になります。(この出てきた液はろ紙で漉してまた使えますが・・)50年間の錆を取るのですから、時間がかかっても当たり前かもしれません。
ヒドイ錆びの時や、処理を急ぐ時などはトイレの掃除でおなじみのサンポールなどの希塩酸・・・酸を使う事もあります。酸で錆を溶かすと、効果は絶大ですし、反応も速く15分くらいでピカピカですが、この後は、すぐに水でよく濯ぎ、(おそらく)アルカリ系の薬剤などで中和?防錆処理をしないとすぐにまた茶色い錆だらけになってしまいます。酸ですから・・・。(最近では錆の再発が心配で、酸はあまり使っていませんが・・・。)
やはりサンポールのような酸は、タンクのように閉鎖された手の入らない物にでなく、表面の錆取り・・・例えばゴルフのクラブ・・・サンドウエッジの表面の錆取りなどのほうが、向いています。外部に使用した場合、錆取り後に表面をいじれますから、防錆の処理などが楽です。
錆取り後の状況によって異なりますが、タンク内部の元からの錆止め塗装の剥がれがひどい場合などは、念のため、さらに丁寧な防錆をします。ウレタン塗料をシンナーで薄く薄めたものを、タンクの中に入れてチャポチャポ振って内部を塗装し、少しでも錆の再発を抑えるようにするのです。
また、すぐには使う見込みの無いタンクの場合は、手間のかかる塗装よりも手を抜いて、防錆用のシリコン・スプレー(CRC556など)をたっぷり吹き付けて、保管しておきます。うーん錆取りだけでもかなりマニアックでしょうか・・。
さて、この後の工程が小生の好きな作業・・・タンクの外側の塗装です。タンクの外側が錆で傷んでいて、元からの塗装をそのまま使えないボロボロな状態の時は、元の塗装を紙やすりで削り、金属の面が露出するようにじっくり綺麗にします。塗料をはがしたタンクは銀色でピカピカです。
この作業はかなり根気がいるんですが、2時間くらい紙やすりでタンクをゴシゴシです。
道具は布ヤスリの100番や紙ヤスリ240番だけです。
全くクラフトって感じですか・・。塗装を完全に剥がすのが重要です。
塗装での大きな問題は、ガソリンタンクですから、給油の時など外側にもガソリンがこぼれて付着してしまう事です。
つまり、ガソリンで溶ける塗装では大問題なのです。
しかし、素人が考える通常のラッカーなどの塗料は、ガソリンであっという間に溶けてしまうのです。
簡単に溶けていたら、また「トッカータとフーガ」・・・鼻から牛~乳~!・・・ですから・・・。
この件を東急ハンズさんで相談しましたら、ウレタン塗装ならガソリンで溶けないですよ!!と教えられました。
ウレタン塗装・・・かつて聞いたことはありました。
本職は「ウレタンを吹く」・・と言う言い方をしていましたっけ。プロの塗装ですね本来・・。
「ウレタン塗装」というのは、ウレタンエナメル塗料の塗装で、2液性の塗料を使っています。
硬化剤を入れて混ぜてから塗る塗装・・・。
代表的な用途では、自動車のボディーの塗装や高級家具に使う高級塗料だそうです。
塗料に硬化剤を入れ、シンナーで適宜薄め、良くかき混ぜ、エアコンプレッサーとスプレーガン・・・塗装屋さんのプロが使うような道具・・・を使って塗装します。
通常のラッカー塗料の様に乾燥するという感じの塗料ではなく、硬化する、「固まる」という感じの塗料です。
硬化剤を入れてかき混ぜた後、この塗料を放置すると8時間後くらいには、かなり固まるのです。素人には難しい感じですね。
しかし良いものがありました。設備が無くてもウレタン塗装ができるスプレーが・・。
スプレー缶型で内部が2重になっており、ノズルを石などにぶつけることで、内側の容器を割ると中の硬化剤と塗料が混ぜられて使える物が販売されていました。
イサム塗料の「エアーウレタン」と言うスプレー塗料商品でした。
スプレー塗料なのに大変高価(確か1本2000円くらい)で、しかも一度混ぜると固まってしまいますので、使い切らなければ無駄になるのです。
1本でランタンのタンク3個分くらいを塗れますので、レストアするタンクを貯めておいて一気に塗装する・・・と言う感じになりました。
面倒な塗料ですが、使用してみますと効果は絶大で、艶、塗料の乗り、強さ、申し分ありませんでした。ガソリンにも溶けていないようでしたし・・。
実際、素人がウレタン塗装しようと言うのが、そもそもチャレンジなんですが・・・。なんとかできました。
塗装して乾燥・硬化後にコンパウンドと言う自動車用の磨き剤を付けたボロ布などで根気良く時間をかけて磨きますと、塗料の霧の細かい粒がならされて、本当にツヤツヤになります。
このツヤツヤは本当に美しくて・・凄いです。
高級な塗料ですから当然かもしれませんが・・・。良い塗装でした。
しかし、ここで大きな問題にぶち当たります。スプレーの色「赤」が一種類しかないのでランタンの上部にある傘(ベンチレーターと言います)とタンクの色が合わない場合があるのです・・・。
ここまできて結局、調色・・・色あわせ・・・が課題になってきました。
一難去ってまた一難です。
プロ用のウレタン塗料の小分け販売をネットで発見してしまってから、これなら茶色っぽい赤でも、小豆色っぽい赤でも、何でも色あわせができると思いました。
で、・・・・とうとう道具一式を買い揃える羽目になります。
こんな事態の方がよっぽど「鼻から牛~乳~」なんですが、ものづくりって、課題を解決できると思うと一直線になってしまいがちで困ったものです・・・。
つづく ・・・って期待されていないですよねー。
ランタンのレストア
趣味の話です。前回の好きな物に引き続き、キャンプ用のランタン(夜、テントの周りを明るく照らす、光る奴です)のレストアの話を少々・・・。
実はこれ、最近小生が嵌っている趣味であります。古いランタンのレストア(restore:復元・修復)が趣味なんです。
キャンプで夜の明かりと言いますとランタンです。ランタンには、ホワイトガソリン、灯油、ガス、電池等の種類があります。
それぞれ特徴があるのですが、ホワイトガソリンはシンナーのような物で引火性が高いので、取り扱いには注意しないと危険でもあり、ある意味で不便ですが、点ければ明るいです。白熱電灯で150W以上・・と言うような明るさが出ます。
灯油燃料のランタンは燃料が安価で、引火性が低く安全ですが、点火の前に燃料が通るパイプの予熱が必要で、手間がかかる・・などの特性があります。明るさはガソリンと同等以上でしょうか。
ガス(カートリッジ式)は取り扱いが簡単で、点火もワンタッチですが、一般に光量はやや落ちます。ガスボンベ式は点灯して暫くすると、ボンベが気化熱を奪われ、冷えてしまい、気化効率が落ち、暗くなるのが普通です。寒い時はガスボンベが冷えてしまうので、なおさら効率が落ち、性能・明るさが低下します。(対策の冬用のボンベなどありますが・・)
電池式は燃えたら困る物の側で使う・・・例えばテント内や歩行時の明かり用で使います。
で、小生が嵌っていますのは、アメリカ製の古いランタンでコールマン社の200Aと言う機種があるのですが、その古いホワイトガソリン・ランタンの整備・レストアなのです。(この後ホワイトガソリンはガソリンと省略して書きます・・)
写真をご覧下さい。


右の写真のグリーンのランタン2個はコールマン社(カナダ)の1970年代のもの・・・。
左の写真の赤いランタンは「赤ランタン」の愛称でファンの多いアメリカのコールマン社製の200Aと言う型番です。1950年代の初めくらいから製造されており、タンクの底に製造年の刻印などもあり、確認もできるものです。一番左が50年くらい前のもので、写真中央が68年製。ちなみに右は小生オリジナルの改造品・・・・。
キャンプを始めたのは1990年の頃ですが、当時から「赤ランタン」と呼ばれる「名品」があることは知ってはいました。しかし、その頃の時点で、既に数年前(1980年くらい)には廃盤になっていた商品なので、「手には入らない物」と諦めていました。
それが2年ほど前、あるオークションサイトで比較的簡単に入手できると知って、気になり始めました。
50年位前のものを一つ買って見ると、本当に可愛いデザインのランタンで、明るさも程良く、気に入りました。しかし、メカ物を買うとメンテをしたくなる小生は、やはりまっとうなコレクターにはなれ??ませんでした。
この手のオールドランタンの趣味は収集の趣味(コレクター)がやはりメインと言いますか普通の王道のようです。傷や古さを「味」と称して尊ぶと言いますか・・・。小生もちろん、その手の古い物の収集は理解していますが、ことランタンに関しては、
1: アウトドアで使う物
2: ガソリンが危険を伴うこと
を考え、趣味の方向を2つに分けました。
当時のオリジナルを美しく留めるような状態の良い(ミント・コレクション等と言うそうです)ランタンは点火ができるような基本的なメンテだけをしてコレクション用にし・・。
程度の悪い物(塗装のはげ、錆び、オリジナルでない部品の使用など)は完全にいじって、レストアして、アウトドアで使い倒す!
こんな考え方で、ランタンに接するのですが、いざランタンを点検し始めると、さすがに50年近く経ったものは問題が多く、コレクションにするものでも、点火可能にするとなるとかなりの手入れ・メンテナンスが必要でした。
この手間・・・実はこれが「良い」のですが・・・。



レストアでは、あるサイトが本当に勉強になりました。オールド・コールマンの販売をされている方のサイトに掲示板があり、その掲示板の過去の履歴がメンテナンスの知恵の宝庫でした。
情報は探せばあるものですし、教えてくださる方もいるものですね・・・。本当に感謝しています。
ランタンの分解をしてタンクの中に豆電球を入れて点灯・確認した時、内部のひどさに驚いたのが、レストア趣味のキッカケ??でした。
やっとオークションで落札し、来た来たと喜こびつつ、タンクの内部を覗いて「愕然」「呆然」と言う感じです。頭の中にあの曲、『トッカータとフーガ』が鳴り響きました。メロディー、ご存知でしょうか?「チャラリ~、鼻から牛~乳~」のあれです。
錆と汚れが本当に凄いのです。ドロドロ、デロデロとでも言うのでしょうか、茶色、黒、青の錆と汚れがガソリンタンクの中全体にびっしりと、カビかコケでも生えているように付いているのです。
外側に錆が無く一見綺麗なランタンでも中はひどい錆だったり・・・その逆もありましたが・・・。
情報に従い、錆び取り液などを駆使して錆を溶かして洗浄しますと本当に綺麗な銀色の鉄の色にはなるのですが、やったと思った瞬間、また『トッカータとフーガ』が鳴り響く事もあります。
運が悪い時は、錆を取ったために、今まで錆で埋まっていた穴が開くのです(ピンホールと言う小さな穴です)。そして、あってはならないガソリン漏れが始まるのです。
錆び取りをしないわけにもいかず、取ればピンホールができてしまうリスクがあります。ピンホールは溶接技術の無い小生では塞げないので、これが確認できた時点でそのガソリンタンクのレストアは終了・諦めです。(実際はこう言うタンクのランタンは電気のランタン・スタンドに流用したりして活用します。タンクに穴を開け電気のコードを通し、電球のインテリア照明として流用するのです)
ピンホールでガソリンが漏れた時は、本当にガッカリします。その刹那、「失意のズンドコ・・もとい・・どん底」・・・大げさですね・・・。
つづく・・・。
Asian Strange Fruit

以前、人から聞いて、そう言うものの見方をするのか?と衝撃(大袈裟ですが)を受けたことがあります。
『日本は今や二流の国で、世界から相手にされていないんだよ・・』と言う話でした。
話は成田に着いた海外からの来客の話で始まりました。確かイタリアから来たお客さんを迎えた時の話だよと・・・説明してもらったのです。
まず成田に着いたら、成田がとても遠いので驚かれた・・・。社用の車でお迎えし、高速で東京に向かっている時に素朴な疑問を言われた・・・。『あなたは税金を払っていないのか?』『高速道路を通るだけで、何でそんなに高額なお金を払うのか?』といわれたそうです。
彼らの常識では高速道路は無料・・・一部新規開通区間などが有料の時もあるが、安価な負担だし、数年で無料になる。あなたがこんなに高速道路に払うのは、税金を未納で問題があるからではないのか?なんて・・・。
『常識』の違い・・・とはそう言うものかと思いました。税金をきちんと払っている国民が道路を使うのは、タダが当たり前・・・。これが世界の常識なんだな・・・と。
その海外からのお客さんは、色んなことに驚いて帰って行かれたそうです。
電話料金が高い。
航空券が高い。
食品に消費税が掛かるのか?などだったと思います(多少うろ覚えですが・・・)
いずれにしましても、日本が世界のスタンダードから、かけ離れている事は結構多いのだそうです。真偽は確かめておりませんが、イタリアでは一般の食品(日本で言う米・味噌・醤油)には税金が掛からないそうです。食品では例外的に非常に贅沢な品目2つ・・くらいだけ税金が掛かるのだとか・・・。どこか産のメロンと、何かもう一種だけに。
しかし、この2品目でさえ、税を掛ける掛けないでもめて、国中が論争になったとか・・・。一方で、フェラーリは税金が高くて2倍の価格になると言う話もありました。イタリア人は国内ではフェラーリを買わないとか・・・これは随分前に聞いた話ですから、EUとなった現在でも他国でフェラーリを買っているかどうかは分かりませんが・・・。
日本人はおとなしいね・・・。そのイタリア人が言ったそうです。「イタリアなら日常の食品に税金が掛かったらその政権は、間違いなく持たない・・・」
文化の差と言いますか。知らなかった。と言いますか・・。
海外の法人で日本に極東の本拠を持とうとする会社は殆ど無い。オフィスを買っても借りても、電気を使っても、物を輸送しても、通信しても日本はハイコストだからだそうです。
日本をうっすらと軽蔑?しているのでしょうか・・・。世界では非常識でも、それを日本の常識にしている国ですから、「何かこの人たちは変だ・・・」と言う視点で見られているのでは・・・と言う主旨の話でした。日本は「Asian Strange Fruit」(アジアの奇妙な果実)とでも言うのだろうな・・と言う事でした。
これは小生、ショックでありました。日本は良い国だと思っていますから・・。
日本人とはビジネスで組む事は無いが「良いお客さん」なのだそうです。
そう言われてみれば、日本にヴィトンもシャネルも直営店があった?!・・・。
マーケットだけが魅力的な、とても一緒にはビジネスをしたくない国・・・日本。アジアの拠点を置くことは無い国・・・日本。悲しい話です。
このことから小生は、「日本が世界のスタンダードと違う事をやっている場合、そこには、何か日本独特の冗費が掛かる?構造的な問題があったりするんだろうな」と考えるようになりました。
こう言う着眼で考え始めますと、いろいろ「日本」については思い当たる事が出てきます。・・・道路建設が・・年金の保養施設の無駄遣いが・・・などなど。きりが無いほど「気が付く」と言いますか・・。
一度、識者の方に日本と諸外国との違いを一覧表にしてみて欲しいくらいですね。
それからもう一つ考えましたのは、ヨーロッパとは民主主義の本質と年季、深さが違うんだな・・と言う事です。
血を流して封建制を倒し、革命を経て、民主国家を勝ち取った国民性と、日本のように戦後、他国から与えられた制度で民主主義なのは国民意識に大きい違い、差があるのだなとも思いました。
ヨーロッパでは市民の方に筋金が入っている。普通の批判眼が社会に根付いているとでも言うのでしょうか・・・。大人の文化と言いますか、歴史・文化の大きな差と思うようになりました。
日本では、学生がそう言う視点でものを見るチャンスが与えられているでしょうか・・・。
そういう教育などの様々な日本の問題点が、『ビジネスで相手にされない国』として、ツケが回るように跳ね返ってきているのではないでしょうか?
非常に寂しい話になってきてしまいましたが、納得性、正当性が低い事を国中でやっていると、井戸の中のカエルの国・・になってしまうのだろうなあと思います。
高度成長の頃、必要とされたビジネスマンの資質は『協調性』だったと思います。
そう言う当時の日本ではそれが良かった・・・長いものに巻かれて・・・等の論理で走ってきた事は、その時代を反映していたのだと思います。
しかし、やはり『1+1=2』と言うような当たり前のことを当たり前の答えで確認できない国は、世界ではダメなんでしょうね。
特定の人々が『1+1=3』と言い、そうだねとなっているような国はいかんのでしょうね。そこでしか通用しない論理はたぶん相当危険なんだと思うのです。
戦後60年を記念して色々な番組が戦争を取り上げていますが、私たち市民が意外に真実を知らされていないのでは・・と思います。
マニラの大虐殺
米兵の捕虜に死の行進をさせた・・・
南京大虐殺
真珠湾攻撃(奇襲)
全部知った上で、日本が戦争犯罪を犯した国・・・に異論を唱える人は少ないのではないでしょうか?アジアの国から日本は謝らないと言われていることに、違和感があるのですが、相手国から見たら謝らない・・・のでしょうね。
その辺りの構造もわからないです。侵略をした・・戦争で残虐な行為をした・・・こう聞けば素直に申し訳ない気持ちですから・・・。
ただ、歴史認識までが外交のカードに使われるような残念な様は、情けないものです。
謝罪は謝罪。
反論は反論。
普通にできない日本に、すっきりしなくて、違和感があるのは小生だけでしょうか?
Asian Strange Fruit なのでしょうか。
日本・・・もうちょっと頑張れませんですかねー。
好きな物(過剰性の話から~)
先日過剰性に感動する話を書きましたが、そういえば自分の好きな物を、こう言う過剰性のある無しなどの視点で洗ってみると、どうなんだろう?とか、今、世間で定評のあるものはどうなんだろう?と思えてきました。
小生、やはり、「ここまでやるか?」が好きなようです・・。
まず車から・・・。
金銭的な理由も大きいのですが、国産・・・良いと思います。
ランエボ(三菱のランサー・エボリューション)とかインプ(スバルのインプレッサSTI)なんて、ヨーロッパでは500万円以上?の高価格車だそうで、2000ccで280馬力以上。ハンドリングも素晴らしくて、とんでもない車だそうです。凄いと思います。

三菱のランサー・エボリューション

スバルのインプレッサSTI
個人的にはマニュアルミッションの車を運転する技量が無いのと、それほど走り屋さんではないし、楽がしたいので、オートマの車を買いますから、この手の車には縁がありませんが、近い性能でオートマチックのワゴンがあったら欲しいですねー。
実際に、今乗っていますのはスバル車ですが、スバル車は過剰性がかなりあると思います。
性能の過剰性もさることながら、小生に刺さっているのは、開発姿勢の過剰性です。スバル車には開発の方の情熱、技術者の判断として良いものを追求する、ものづくりが見えるように思います。
足回りの見えないパーツがアルミだったり、こだわったところにお金を掛けていたりします。
素人に刺さるように・・・ならもっと分かり易い内装のウッド(木目)などの高級感に走るでしょうが、この会社さんは、「走る事」にお金を掛けているように思います。
驚いたのは、新型車の発売後も毎年改良を続け、開発をやめないことです。同じ車でも年々進化していく。販売的に好評でも、毎年のように追加開発の成果を製品に反映する。これって凄いことで、普通の企業論理だと、「ユーザー的には満足しているのだから金をかけるのは止め、利益率を高めよう・・・」となる筈なんですが、そうならないところが驚くところで、素直に尊敬の念を感じます。
スバルはメジャーじゃないかもしれませんが、面白い車だと思いますし、いい車だと思います。
今後もっと過剰性に自信を深められて、もっと徹底され、ユーザーが外車よりこっち、積極的にスバル・・・と言うところまで行ってしまって欲しい・・なんて思います。全車種とは言いませんが、ハイエンド商品は値上がりしても良いので、世界を相手にしても『スバルの方が凄い』とユーザーが胸を張れる過剰性を持って頂けたら、もっと素晴らしいと思います。
トヨタの車もハイブリッド車など「本当にここまでやるか?」と感動します。
セルシオやレクサス・・今後の高級車の展開も楽しみですね。
車以外で過剰性を感じる好きな物はどうでしょうか?
カメラ・・・・デジカメもいよいよ本物と思います。
デジタルの一眼レフ・・・。いいですね。ニコンのD70とか。なにしろ、現像しないで結果が見られる。しかも600万画素を越えた現在、画質面もほとんど問題を感じませんし・・。レンズ・・・もちろんメーカー純正は憧れますが、タムロンさんのレンズが好きです。ある意味純正とは違う価値・・・軽い・高倍率ズーム・安い・・と言った非純正らしい「ならでは」の特徴があって好きです。

ニコンのD70
28mmから300mmまでを一本のレンズがカバーするなんて!!しかも小さくて軽い・・・旅行とか荷物の多い時は、これ一本で充分!?でしょうか。(自分のレンズシステムは結構、中古屋さんで買った物ばかりで構成されていますが・・・)
それからキャンプグッズ・・・。
不便なアウトドアを快適にしようと言うアイデアには嵌ります。例えばキャンプの椅子・・・収納性と重量が実は重要なんですが、キャンプ初心者の頃は安物買いの銭・・・になってました。今まで色々失敗した買い物の後、小さくしまえて、軽くて、使っている時快適で、壊れにくい物を発見しています。コールマンの「スリム・キャプテン・チェア」が小生の悩んだ末の選択です。一脚4000円くらいはしますが、車の荷室が小さい時、一番の選択と思います。構造・収納方式が本当に良くできています。

コールマンのスリム・キャプテン・チェア
テントは好みがありますが、ジュラルミン(アルミ)フレームのもの。タープはパティオタープ(アルミフレーム)で開いて4本の柱を引っぱるだけで簡単に設営可能なのが気に入ってます。オプションのネットでスクリーンタープ(蚊帳)にもなりますから・・・。安くて最高のタープと思います。収納時少々嵩張りますが、構造的にも良くできています。
火気の類は色々悩みましたが、簡便性では家庭用のカセットガスを使用する製品が良いですね。キャンプ用のガスに比べて燃費が安く済みます。ガス製品は点火して10分位すると気化熱を奪われたカセットボンベの低温化による気化効率低下、火力低下が問題なんですが、ボンベを温めるデバイスなどを装備し、良く考えられた製品なら、アウトドアでもかなり使えます。
カセットガスの製品はラインアップも良好です。暖房用のストーブやツーバーナー、ランタン・・・ほとんど入手できます。カセットガスは簡単にセットアップできますし、不足したらコンビニで買えます・・・。
火力を重視しつつ、キャンプらしい雰囲気を味わうなら、ホワイトガソリンですね。特にツーバーナーの火力は変えがたい魅力です。
纏めますと、簡便性でカセットガス。らしさと雰囲気でガソリンでしょうか。こう言うキャンプグッズは並べて眺めているだけで楽しくなりますね。
真空管アンプ。これも大好きなものです。
過剰性・・今更真空管ですから・・・。デジタルの時代に全くのアナログ回路のこの製品に惹かれます。音が良いように感じるのです。
ここは、説明するのが難しいので、言葉にしません。ただ、機会がありましたら真空管のアンプで良質なスピーカーを鳴らした音をお聞きになる事をお勧めします。小生はローコストなキット製品を買って自分で組み立てた物を使っています。
デジタルアンプ。実はこれも好きなものです。
真空管と矛盾すると思うのですが、浜松の方のベンチャー企業さん「フライングモール」さんが作った小さなデジタルアンプの音が真空管アンプに通じる良さがあり、驚きました。モノラル4万円、ステレオ(2台)で8万円。家電としたら高いですが、オーディオとしたら安い値段です。音は本当に凄いです。技術の先端と昔の真空管技術の音が似通っているのも面白いと思いました。

フライングモールのデジタルアンプ
まだまだ好きなもの、沢山ありますが今回はこの辺で失礼します
・・・。
よもやま話・・・絵画・・・
絵は良いですね。
絵に救われた事が「かつて」ありました・・・。
昔、就職したばかりの時、新入社の社員研修で2ヶ月間愛知県の西尾市に滞在した事があります。毎日毎日なれない肉体労働や作業などで、疲れ果てていました。この研修は就職した組織でおこなわれるのではなく、関係はするものの、まったく別の取引先に出向いて実務研修をするものでした。
研修といっても日曜は休みですが、知らない街で過ごす休日ですから、友達もいません。かと言って新幹線で毎週東京に帰ることも金銭的に全く無理でした。(当時の月給は11万円くらいでしたでしょうか)
寂しいですし、ともに研修を受けている会社の新入社員仲間はもう一人いたのですが、彼は大阪出身だったので、「近いから」と言って良く大阪に帰っていました。そのため、小生は結構一人の休日を過ごすハメになっていました。
大学出立てのサラリーマン研修生は当然貧乏で、車も持っていませんし、何もすることが無かったのです。「足」が無いのは厳しいです。この「暇」には本当に参りました。研修の気疲れや肉体的な疲労で、落ち込んでいました。
そんな時、西尾の駅の近くの喫茶店でよく時間を潰したのですが、そこに朝日グラフでしたでしょうか、絵画の写真の本が置いてあったのです。
東山魁夷さんの絵を特集したグラビア雑誌でした。
小生は絵に興味など無く、趣味も見識もありません。(未だにです)ですが、この絵に深く感動しました。絵の題は「緑響く」・・・でしたか?この絵の中、湖畔に白馬がおりました。
緑は深く、湖は深く澄み、森林の匂いがしてくるようでした。絵を見ているだけで森林浴になりそうで、そっと深呼吸したりしてみました。何かストレスが少々ほどける・・様な感じがしました。
東山魁夷さんの絵画は何点も掲載されておりましたが、全て素晴らしく小生を魅了しました。満開の月夜のさくら・・・花明かり・・・もあったでしょうか。全体的な印象では、深い緑と白馬がとても印象に残りました。『絵が精神に効く』・・・そう言う感じがしました。
過去を振り返って考えて見ますと、前述のごとく、もともと小生は絵画の趣味など無く、その見識・常識にも欠けますが、良いものは良い・・と言いますか、今までに何点か感動した絵があります。
高校時代に見たモネの一連の作品・・睡蓮でしたっけ・・・。それから・・・チューリップ畑・・・。特にチューリップ畑の方が気に入って印刷物でも欲しいなあ・・・とおぼろげに考えたりしていました。
で、開発屋の小生はいつか暇になったら、これらの絵の資料と首っ引きで、「模写」などやって時間を過ごしたいと思っています。
先の楽しみに取っておくのが、好きな絵の模写・・・。オリジナルを美しく書く実力など無いですから、せめて模写・・。
大して上手くもできないでしょうが、そう言う時間を使うのはちょっとした夢になっているように思います。
『絵』って文章のような・・・響いてくる魅力がありますですね。
腕時計の話
腕時計は・・・。ある人々にとってはアクセサリーでしょうか・・・。
しかし、私には「機能」です。
「ブランド」「高価さ」よりも何よりも機能です。
「機能」に憧憬のようなものを感じます。

(*)好きな腕時計
もちろん機能的で、私的にデザインの良いものが、より良いのですが、個人的な趣味もあり、なかなか両面でぴったりする腕時計を見つけるのは、むずかしいものです。
ですので、どうしても「機能中心の選択」になります。太陽光発電。電波時計。10年電池。キネティック発電。高精度のクオーツ。そう言う技術の数々には本当にワクワクします。
ソーラーもキネティックも電池の交換が不要で、ズボラでいられるなんて最高の機能です。
ましてやクオーツの月差±10秒なんて、昔なら夢のまた夢の高性能です。
ブランドの時計でもこういった高性能・高機能があればなお良いのですが、これはなかなか両立していないと思います。
今の私のエースの時計はセイコーのチタンボディーで、太陽光発電クオーツ。実売2万円にも満たない物ですが、最高だなと感じます。チタンは何しろ軽いし、汗をかいても痒くならないです。
肌への物性が磁器などに近いと聞きましたが、そうなのでしょうね。
さわやかな感じです。
真夏の強い日差しなら、数時間の充電で6ヶ月分くらいの充電ができるとか・・・。
堪らない便利さですよね。そして、アナログ時計。針の位置によって視覚的に時刻認識ができますし、計算しなくても残り時間を目で見ることができる。
色々捨てられない時計がありますから、ご覧いただきたいと思います。セイコーのクロノグラフ・・・白さが堪らなく、針たちのバランスも最高です。これは就職して最初に買った、20年以上昔の・・・当時としては大金の(3万円以上だったと思います)時計です。
裏がガラスで中の発電メカ・・・キネティックが見える時計(*1)。表のシンプルさも良いです。これはテレビ通販物です。
シチズン(*1)の1万円くらいの時計です。
やはり白さとデザイン(厚さ)が良いです。珍しくデザインに惚れて買った時計です。本当に綺麗ですよ。
このデザインでR社とかB社とか・・有名なブランドロゴが書いてあったらどうなんだろう・・・・とかも思います・・・・・。難しいですねー価値って・・・。

(*1)左/キネティックが見える
右/シチズンの時計
私は機能的な時計に本来「良さ」を感じているのですが、デザインだけを切り出しますと、その美しさで、たまにはB社のアルミニュームとかいう時計やR社のクロノグラフの時計にも目が行きます・・・。
それはそれ、ブランドもそうなんですが、良いデザインですねえ。
今後も機能とデザインの両面を満たすものをじっくりと楽しんで探していくことと思います。
時計は楽しいです。
シャープペンシルの話
シャープペンシル・・・・電気製品のシャープさんが特許を持っていらっしゃるからシャープペンシルと言うそうです・・・どこかで聞いた話なんですが・・・なるほど・・・それでシャープペンシルかと思ったものです。
実はとても手離せないシャープペンシルがあるのです。
PILOTのシャープペンシル(*1)で、1000円の・・・もともとは製図用だと思います。
15歳の時に初めて偶然買って以来33年・・・これを愛用しています。
こだわりと言うのでは無いのですが・・・書きやすさで手放せません。
それからメカ的な優秀さ・・・これが堪らないのです。

(*1)愛用中のPILOTのシャープペンシル2本
上:1000円のもの
下:1500円の重いタイプ
ツーノック(*2)とか言う機構で、メカ全体が出し入れできるように動くノックと、芯の出し入れのノックが2段で動作する・・・これはメカが引っ込んでいれば、落とした時に繊細なペン先を曲げてしまわずに済む優秀な機構なのです。

(*2)ツーノックという機能
また基本性能・・・芯が先端の細いパイプの中でぐら付かず踊らないのです。芯がぐらぐらしないできっちりした感じ・・・・重すぎず軽すぎないバランス。疲れないで書ける性能。真のシャープペンシルの名機と勝手に思うのであります。
上位機種で金属部品の多い1500円のモデルも持っていますが、ややバランスが悪く、先の方が重過ぎると思われ、やはりこの1000円のがBESTです。
高校1年生から使っているのですが、幾つも壊したり無くしたり・・・
しかも他のシャープも買ってみるのですが、不思議に結局これに戻っているのです。
33年間・・・。長い間です。普段は常に数本買い置きしてありました。
先日、メーカーのPILOTさんには未確認ですが・・・ある文具店の店頭で・・・廃盤・・・と言う文字を見ました。悲しいです。シャープペンのMY名機も役割を終えるのでしょうか・・・。
確かにこのシャープペンシルにスポットライトは当たらないのかも知れません。数は売れないのかも・・・。でも、色々使ってみてこれが最高と言う商品が消えるのは堪らなく寂しいものですね・・・。
PILOTさんのこれを開発した技術者さんに本当に敬意を表します。
すばらしい物を長年有難うございました。
現在は廃盤?とはいえ、つい最近・・・去年くらいまで?初期の頃からの変更は、わずかにプラスチックパーツの表面のシボ(模様)が変更になるくらいで、ほぼ同じ物が同じ値段で買えた。
この事が画期的で本当にありがたかったのです。
文具はある意味でファッション商品だと思います。そう言う厳しい市場で、このような商品(良品)を30年間も供給してくださったPILOTさんは、本当に凄いメーカーさんだと思います。
私の会社などでは、こう言うことができるだろうか?と考えますと、30年間は本当に長い月日であり、重いです。・・・自信がありません・・・。
今後も最後の買い置きを大事に使い続けます。
四角い車の話
私は四角い車が好きなのです。
ですが、最近の車には四角いのが無くて困っているんです。
・・・と言うわけで、ちょっと車に関して独断で恐縮ですが、私的な意見を書いてみます。
デザインって何でしょう?デザインは形を心地良くしたり、美しくしたりするとは思いますが、本質的に何なのか?は上手く語れません。
私は語るほどわかっていないと思います。
ですが、結果として出てくる商品・製品に対しては、ユーザーとして見ても、必ずしも「ハマっている」物ばかりではない・・・と感じられます。
デザインのためにデザインする場合・・・これは作品であって製品では、・・・いや「商品」では、疑問だと思います。
私自身は展覧会用の品物、尖がった先端デザインを欲してはいません。
進歩的なフォルム。珍しい試み。私は買わないだろうなーと思います。
自動車は好きです。メカニズムが堪らないです。機能が堪らないです。ですが、形には納得いかないものが多いと思います。
それは商品企画面からもそう感じます。
ユーザーの志向を勝手に決め付けているのでは?と思うのです。
エンタテインメントは滅私奉公だ・・・これは小説についての五木さんの言葉ですが、本当に名言と思います。含蓄が深いと思います。
商業的な開発では、全く「滅私奉公」が当て嵌まると思うのです。
全てはお客様のために・・・です。
業界内のウケなどこの場合不要ですし、業界内でのカテゴリ合致性なんてお客さまには不要だと思うのです。
そもそも、このカテゴリーの存在に違和感を感じますし・・・。
だって、例えば7人家族の移動を快適に行える車と言うテーマでも、会社の考え方の違いで本当に多数の回答に分かれる事になる筈だと思います。
例えばある会社はロングのジープの様な回答でしょうし、また伝統の四輪駆動のメカでハードなワンボックスを提案してくる会社もあるでしょう。
また、ある会社はオフロードは完全に無視してリムジンの様な提案で、またさらにある会社は車高の高いワゴンを・・・と言う風に得手・不得手などで商品性は分かれる筈なんです。
回答のバリエーションが市場に色々バラエティー豊かにあふれるのが普通の筈なんです。
でも現実には、どこかの会社がちょっと当てるとコピーばかり・・・。ミニバンと言うカテゴリーばかり・・。
今、私はミニバンとクロカンの商品性にも疑問を持っています。ミニバンとクロカンの中間が欲しいのです。
あれだけ多数のメーカーがあって、何で画一的に一方向にしか企図されていないのか・・・と感じてしまいます。不思議ですらあります。開発段階のユーザー調査のデータが改竄されていないか?とさえ思うほどです。
SUVと言えばSUVばかり・・・。ユーザーの小生は欲していませんが・・・。
例えば、クロカンは終わったと言われますが、そんなことは無いと思っています。軽快で多機能なクロカンはありだと思うのです。
一時大好きだったパジェロ(*1)。前のモデルは四角くてクリーンなデザインだったし美しかった。後期はオーバーフェンダーなどがぶち壊しかなと感じましたが・・・初期型は美しかった。

(*1)かつての愛車パジェロ
ユーザーはクロカンブームにパジェロを体験し、その運転席の高いこと、見通しの良さから来る運転しやすさ、快適さ、逞しい乗り味を知ったと思います。
でも一方で車の重さ、ディーゼルのスモークの汚さ(私も肩身が狭かった)を知ったとも思います。
また走行性能も都市では鈍重だった・・・ディーゼルの出足は遅かった。4駆性能もほとんど宝の持ち腐れだったし・・・。
でも結果、良さも悪さも含め、「体験」は残った。
ある意味、家族臭がしなくて素敵な車(ファミリーカー)だった。
一方、ミニバンはどうでしょう。ワンボックスタイプは3列シートで、これでもか・・・と言うほどの過剰に便利な室内。両側スライドドア。家族臭の塊。走行性能は妥協。以前のエルグランドや最近ではノア、特にVOXYが何とか良いなと言うデザインでしょうか・・・。
オデッセイの類型はどうでしょう。走行性とミニバンの使い勝手・広さを上手く纏めていると思うのですが、一つ売れたら、皆こればっかり。最近ではミニバンが車高の低さを訴えています・・・。同じようなデザインばかりと目に移りますし。
メーカー間でお互いに売れたモデルのコピーをして、結果として同一の商品性の百花繚乱。多すぎてうんざりだし、家族の車。
男の車じゃない。(ごめんなさい。言い過ぎですが、ちょっと本音です。)
という状況で私はこんな車が欲しいのです。
クロカンの感覚。ミニバンのラゲッジスペース。フルタイム4駆の走行性能。軽さ。でも後輪が滑ってから四駆になるパートタイム型よりもっと本物の4駆。
性能のイメージはスバルのアウトバック 6発。これを四角く高くデザインしてキャビンを大きくし、5人乗りで(基本が5人乗り・・・これは重要と思います)ラゲッジを大きく高くした感じでしょうか。
「クロカンのテイストでミニバンをデザインした四角いフォルムの車。」とも言えるでしょうか。
これをさらに色んな言い方で説明します。
四角いフォルムで、4輪駆動(フルタイム)のMPVを作り、車高を高くして(最低地上高200mm)タイヤをでかくする。
以前のパジェロのエンジンフード部を短くして、その分をキャビンスペースにあて、ラゲッジを拡大。但しフルフレーム構造はクロカンに譲りモノコックボディで・・・。エンジンはガソリン。
ラゲッジの拡大にこだわるのは、キャンプ用品がワゴンの荷室には積み切れないからです。
以前のパジェロやレガシーのラゲッジスペースでも全く不十分ですから・・・。5人乗りで良いのでMPVのスペースが欲しいのです。
SUVがあると言う声が聞こえてきそうですが、SUVには納得できないのです。ハリアーもムラーノも丸くて、デザインし過ぎで、荷室が狭い。
だったらセダンかクーペにすれば・・・と感じてしまいます。
BMWのX5も狭くて・・・。5シリーズのワゴンの後部を切り落としていますが、なぜ切り落とすのか・・・本来は延長すべきと思うのですが・・・。確かに速くてどこでも走れて一杯積めてと言うとSUVっぽい企画ですが、現行のSUVはオンロードの走りのイメージに振り過ぎのデザイン・・・と感じますし積載量が少なくてダメなんです。
キャンプ用品・・ランタン・テント・ツーバーナー・人数分のシュラフ・テーブル・椅子・タープ・焚き火台などの用品・クーラーボックス・クッキングウエア・衣類・小物類・・・・こう言う多数のアイテムを、いざと言う時に楽に(なんとか)積めるのが、ユーティリティービークルなんだと思うのですが・・・。
自動車会社の企画の方はデイキャンプ・・・日帰りバーベキューくらいしかしないんだ・・・などと思ったりします。
私はこう言う本格的なキャンプに、見飽きてしまったワンボックスやミニバン以外の格好の良い男の車で行きたいと思います。
7人のりの3列目の簡単な撤去のアイデアや低いフロアと高めの車高の演出の両立・・・色々な課題はあると思うし、ましてやアウトバック並みの走行性能・・・・実現は大変でしょうが、私は欲しいです。四角くてラゲッジが広大な新しい四駆。クロカンからの派生でなく、ワゴンやミニバンからの派生でも良いのですが・・・。
今売っている車に関しての個人的・私的な意見・・・。
パジェロ・・・変に丸くデザインしてあり、顔が複雑な造形でいやだし、グラスエリアとウエストラインから下のバランスが悪いと思います。グラスエリアのみ3cmくらい高くし、車高も上げたいくらい・・・。かつてのユーザーを完全に裏切ったのはフロントフェンダーの妙なふくらみ・・・。私はディーラーの発表に行って本当にがっかりしたものです・・・。
買いたいと思って待っていただけに、呆然とするくらいでした・・・。
ランクルプラド・・・顔やテールランプのデザインに違和感。真四角で良いのにヘッドライト部のガラスの造形などで奇をてらった感じがいやです・・・。
アメリカで売っているGX430?の方がはるかにハマル様に感じます。
ハイラックス・・・顔が・・・。(少々ブタ鼻系で)残念です。(*2)

(*2)ハイラックスの顔
オデッセイ・・・良いと思いますが、ロングワゴンでしょう・・・と言う感じです。私的には車高は高い方を好みます・・。
MPV・・・四角かったら相当良いのに・・・。四角いMPVのハイト&大径タイヤ版・・・次作に期待したくなる感じです。
XTRAIL・・・相当良いですがグラスエリアは高くしたいくらい・・・。全体に小さいです。ムラーノではなく、ラージ・エクストレイルがあったなら欲しいと思います。(*3)

(*3)ラージサイズが欲しいXTRAIL
CRV・・・もっと四角く・・・。(マイナーしましたが)4駆を本物にして欲しく・・・。全体に小さいです。
MDX・・・相当良いのですが、大きすぎ・・・。丸すぎ・・・。アメ車と感じます。
ハリアー・・・カテゴリが違う車。セダンに近い感覚だと思います。
・・・と言うわけで、四角い車が無い・・・または、少ない。企画面が決め付けられている感じで、本当に欲しくなる車が無い。
という嘆き?でした。
完全に独断・偏見です。謝ります。大変失礼致しました。
魚フライの話
グルメではないので、食べ物の話はする資格無いのですが、日頃美味いと思うものを・・・。
安くて旨い・・・これが刺さるんですが、実はこれ懐かしい味に弱いのかもしれません。
と言うのは、どうも学生時代に食べた物の懐かしさを追いかけているようなので、それが結局、安いにつながる・・・になっているのかも知れませんので・・・。
で前置きはこれくらいで、好きな食べ物の話。
小生、キッチンジローさんの「魚フライ」(*1)・・これが好きなんです。

(*1)好きな魚フライ
もともと、どちらかと言うと洋風に調理した魚は匂いが油に閉じ込められているようで、臭み?が気になり嫌いでした。魚は炭火で塩焼きに限る・・・本来これが持論です。ですが・・・。吟味された魚のフライも旨いんですね。
学生時代、水道橋界隈をウロウロしていましたので、この店にはよく行ったのですが、何となく、「たまには魚を」と思って注文したら、この魚フライはいけましたんです。
それ以来、この店では焼肉・ハンバーグより魚フライです。
嬉しいのは味が変わっていない事です。初めて食べてから、もうかれこれ20年以上経っていると思います。当時から旨さに変わりはありません。この店のフライはパン粉が良いのか?フワっとしていて良いのです。
店の説明の文章では築地に入荷する沖目鯛・・・とか言う鯛をキッチンジローが殆ど仕入れ魚フライにしているそうです。
どんな魚かフライ以外の姿を見たことも無い沖目鯛・・・。
このフライ、臭みが無く独特の甘みがあって、堪らないのです。50歳に近づいても、たまにキッチンジローに行ってこれを食すのです。
この店の良さは、大衆向けの定食屋でも、こだわりがあるようで、米が意外に?旨いし、豚汁もそれなりに旨いし・・・です。
食べ物の趣味ですから、これを旨くないと仰る方も、もちろんいらっしゃると思いますが、お許しの程を・・・。